壁新聞展示中!
こんにちは。今年もあとわずか。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。

昨日は、淡海こどもエコクラブ活動交流会の様子を紹介させていただきました。
そして、今日は各エコクラブさんが作られた壁新聞展の紹介です。
各クラブさんの力作ぞろいです。読み応えあります。
1/17(日)まで、展示をしていますので、ぜひお立ち寄りください。(博物館の無料空間のアトリウムで展示しています)
現在展示中のこどもエコクラブさん
・たまて林の会
・ぼてじゃこワンパク塾
・油日小学校
・NPOこどもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブ
・瀬田北中学校科学部
・伊香立中学校アクアリウム部
・大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDS
・しがkidsエコクラブ
・湯田小学校5年生ゆ~たん
今後順次増えていきますので、お楽しみに!

昨日は、淡海こどもエコクラブ活動交流会の様子を紹介させていただきました。
そして、今日は各エコクラブさんが作られた壁新聞展の紹介です。
各クラブさんの力作ぞろいです。読み応えあります。
1/17(日)まで、展示をしていますので、ぜひお立ち寄りください。(博物館の無料空間のアトリウムで展示しています)
現在展示中のこどもエコクラブさん
・たまて林の会
・ぼてじゃこワンパク塾
・油日小学校
・NPOこどもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブ
・瀬田北中学校科学部
・伊香立中学校アクアリウム部
・大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDS
・しがkidsエコクラブ
・湯田小学校5年生ゆ~たん
今後順次増えていきますので、お楽しみに!
淡海こどもエコクラブ交流会 実施しました!
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
環境学習センターでは、滋賀県のこどもエコクラブの事務局として、県内の皆さんの活動を支援しています。
「淡海こどもエコクラブ活動交流会」は、活動を発表し、みんなが刺激を受けて、知恵や力をもらって、次の活動へ励んでもらおうと毎年実施しています。
先日の12/20(日) 琵琶湖博物館 ホールで実施しました様子をお知らせします。
参加団体は、13エコクラブ、なんと177名がご参加くださいました。
(ちなみに、滋賀県全体では今年度126団体、5713名のメンバーと483名のサポーターが活動してくださっています。11月末時点)
午前中は各クラブの発表、午後は体験交流プログラムと表彰式です。

◆1番目の発表は、栗東市で活動しておられる「たまて林」さん。
今回は、子どもたちがフィールドの畑でお芋を育て、下戸山はなもも市の子ども出店で販売し、次の活動や販売に向けて企画していくということを発表されました。
1番ということでしたが、堂々と発表してくださりました。

発表後は、審査委員と質疑応答です。審査委員は、篠原琵琶湖博物館館長、辻村さんMOH通信編集長、古谷さん滋賀県総合教育センター主幹の3名です。

◆2番目は、大津市のぼてじゃこワンパク塾さん。
フィールドのぼてじゃこ繁殖池や農園を中心として、生きもの大好きの子どもたちが生物調査をした活動です。

それぞれ、とても深く調べてくださっていて、発表だけでは収まらないことが想像されます。

◆3番目は、アイキッズ エコアイディアキッズびわ湖さん
食をテーマに活動し、今年は琵琶湖八珍を全て活動で取り上げて、琵琶湖での食材の確保から調理など地域の方や専門家と一緒に行い、滋賀の食について考えておられます。

これら全てを食べられたんですね。うらやまでぃーです。
来年はどのような食のテーマを掲げられて活動されるのでしょうか。楽しみです。

◆4番目は、甲賀市の油日小学校エコ委員会さん。
なんと、カラフルな忍者が登場しました!ビオトープに薬草園があるそうで地域由来の10種の薬草を育て、学習で活用しておられるそうです。忍者と薬のまち、甲賀ならではです。

エコ委員さんが油日小学校の活動の中心となり、学校のヒーローだそうです。

◆5番目は、NPO子どもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブさん。
太鼓の音と共に子どもたちが活動とその思いを大きな声で発表してくれました。

琵琶湖の源流の森での体験から川を経て琵琶湖、沖島での食など、上流から下流までをぐるっーと体験されました。
琵琶湖の外来魚問題では、「外来魚を食べて減らそうと言うけれど、売ってないやん!」と子どもの視点で表現してくれました。

沖島には、これからの暮らしのヒントがあるそうです。昨年度ESD研修会が沖島で催されましたが、子どもも沖島の暮らしを見て、これはっ!と思っているんですね。子どもの思い、大人の思い、それぞれを出し合うと、いい未来が作れそうです。

◆6番目は、なかす野洲川たんけん隊、やすたんの皆さんです。
地域の昔話の紙芝居で聞いて、その昔話を実際に地域で体験されました。

たらい舟に乗って野洲川へ漕ぎだしたり、昔話の舞台となっている地域でおじいさんおばあさん達に昔の様子をインタビューしたりと、今と昔を比べながら自分たちのまち野洲を体験しておられました。
スライドも紙芝居風にアレンジしておられ、工夫を感じます。

◆7番目は、大津市立瀬田北中学校 科学部の皆さんです。
長年続けておられる地域を流れる長沢川の研究活動を発表してくださりました。

地域の川を科学的な視点で研究を続けてくださっていることが、他の活動の目標にもなります。
スライドも生徒さんが作り、操作も自分たちでやってくださります。

◆8番目も、中学生による発表、大津市立伊香立中学校 アクアリウム部の皆さんです。
学校にはたくさんの水槽があり、そこで魚類を始めとする水生生物を繁殖しておられます。

特にメダカを育て、地域の祭などで販売し、そのお金を東日本大震災で被災した石巻へ送る活動を中心に行い、先輩たちから引き継ぎ、これまでの5年間で50万円以上を寄付しておられます。

◆休憩をはさんで、9番目は、大津市の浜大津保育園さんのおやおや?浜保クラブさんです。
お手製の映像と音楽と共に、子どもたちが歌い話してくださります。

長等公園へお散歩にでかけた時に、1匹のカエルと出会いその世話を通して生き物の世界と向き合っていく様子が表現されていました。
町中の保育園さんですが、自然と関わることはいっぱいあるんですね。

◆10番目は、大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDSさんです。
KIDSさんは、中高校生が中心となり、子ども会のリーダー活動だけでなく、外来魚を釣り食べるびわこエコフィッシングを企画し運営しておられます。

制服姿で登場され、劇を演じ、さらに動画と連動させておられました。

◆11番目は、大津市の和邇で活動しておられる、しがkidsエコクラブさんです。
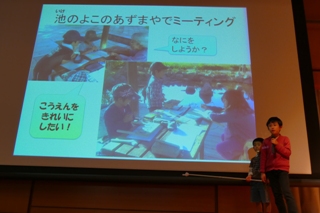
今年の夏頃から活動を始められ、子どもたちが地域の公園で会議をして活動を決めて、実施しておられるそうです。
ほんのすぐ近くの身近な場所を好きになる活動へつながっています。

◆12番目は、長浜市の湯田小学校 5年生ゆ~たん さんです。
5年生90名を代表して、子どもたちが参加してくださりました。

5年生が1年間「生きものがたり湯田小から」として、琵琶湖と地域のつながりを学ぶ学習を発表してくださりました。
大きな絵図には、たくさんの付箋が貼られ、子どもたちの発見や学びが書かれています。

◆最後の発表、13番目はGOキッズ 下之郷遺跡キッズクラブさんです。
貫頭衣や弓矢を身につけての登場です。
遺跡?歴史?と思われるかもしれませんが、昔と今の暮らしを体験し、未来につながっていく活動です。

火おこしや織物体験、そして当時の人が食べていたであろう食の体験や地域の人との交流を通して多くのことを学んでくださっています。
と、休憩をはさんで午前中2時間半、皆さんが発表をし、また聞き、時には質問をして(時間の関係で少ししかお聞きできず申し訳ありませんでした)、過ごしてくださりました。
午後は、博物館の自由見学と、体験コーナーです。

琵琶湖博物館のはしかけグループ「ほねほねクラブ」さんが、骨にさわってみよう体験を実施してくださりました。
自分の身体の中にある骨なのですが、普段、骨って意識していません。
あらためて、動物の骨を触りながら、身体の骨格の仕組みを体験しています。

こちらは、「地球温暖化防止活動推進員さん」による、食とエネルギー体験。
食べ物の旬クイズや旬以外には多くのエネルギーを費やして生産されていることなどを楽しく学びます。
そう言えば、昨日はクリスマスでした。ケーキに乗っているイチゴ。旬は冬と勘違いしていませんか?

こちらも、「地球温暖化防止活動推進員さん」による体験。火おこし体験。
中学生がうまくコツをつかんで、火をおこしていました。
火は人間の生活の基本のはずですが、オール電化や都市化など、火を見る使う機会がなくなりつつあります。

ホール前には、皆さんが作られた活動の壁新聞が貼られ、発表だけで伝えきれなかった活動の良さや詳細を知ることができます。
また、サポーターの方同志と立ち話で交流しておられたり、私もサポーターの方々とこどもエコクラブ活動の運営やこの交流会のあり方などを話したりしていました。
普段活動で横のつながりがなかなかできないサポーターの方同志が集える場にも、わずかですがなっていました。
さてさて、1日を掛けて行ってきた交流会も終盤、表彰式です。

今回は、大賞が「NPOこどもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブ」さんに決まりました!
奨励賞は、「ぼてじゃこワンパク塾」さん、「瀬田北中学校科学部」さん、「伊香立中学校アクアリウム部」さん、「湯田小学校5年生ゆ~たん」さん、「GOキッズ下之郷遺跡キッズクラブ」さん
審査委員特別賞は、「なかす野洲川たんけん隊」さん、活動賞は、「たまて林の会」さん、「アイキッズ エコアイディアキッズびわ湖」さん、「油日小学校」さん、「おやおや?浜保クラブ」さん、「大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDS」さん、「しがkidsエコクラブ」さん
が受賞されました。

最後は、環境学習センター所長 ビワマス博士の桑原所長から「来年のガンバロー」とエールが送られ終了しました。
参加してくださった皆さん、支えてくださったサポーターの皆さん、見に来てくださった保護者の方、本当にありがとうございました!
午後の体験でご協力いただいた滋賀県地球温暖化防止活動推進員の皆さん、ありがとうございました。
また、教師塾からお手伝いくださった7名の学生の皆さんもありがとうございました。地域で様々な子どもの活動があることを知ってもらう機会となりました。
そして、交流会の運営や参加してくださったクラブへご支援くださっている公益財団法人平和堂財団さんにも、本当に感謝申し上げます。
来年に向けて、皆さんにどんな支援ができるか、交流会としてどんな形にすべきかなど検討して皆さんに喜んでもらえる交流会にしていきたいと思っています。ご期待ください!
環境学習センターでは、滋賀県のこどもエコクラブの事務局として、県内の皆さんの活動を支援しています。
「淡海こどもエコクラブ活動交流会」は、活動を発表し、みんなが刺激を受けて、知恵や力をもらって、次の活動へ励んでもらおうと毎年実施しています。
先日の12/20(日) 琵琶湖博物館 ホールで実施しました様子をお知らせします。
参加団体は、13エコクラブ、なんと177名がご参加くださいました。
(ちなみに、滋賀県全体では今年度126団体、5713名のメンバーと483名のサポーターが活動してくださっています。11月末時点)
午前中は各クラブの発表、午後は体験交流プログラムと表彰式です。

◆1番目の発表は、栗東市で活動しておられる「たまて林」さん。
今回は、子どもたちがフィールドの畑でお芋を育て、下戸山はなもも市の子ども出店で販売し、次の活動や販売に向けて企画していくということを発表されました。
1番ということでしたが、堂々と発表してくださりました。

発表後は、審査委員と質疑応答です。審査委員は、篠原琵琶湖博物館館長、辻村さんMOH通信編集長、古谷さん滋賀県総合教育センター主幹の3名です。

◆2番目は、大津市のぼてじゃこワンパク塾さん。
フィールドのぼてじゃこ繁殖池や農園を中心として、生きもの大好きの子どもたちが生物調査をした活動です。

それぞれ、とても深く調べてくださっていて、発表だけでは収まらないことが想像されます。

◆3番目は、アイキッズ エコアイディアキッズびわ湖さん
食をテーマに活動し、今年は琵琶湖八珍を全て活動で取り上げて、琵琶湖での食材の確保から調理など地域の方や専門家と一緒に行い、滋賀の食について考えておられます。

これら全てを食べられたんですね。うらやまでぃーです。
来年はどのような食のテーマを掲げられて活動されるのでしょうか。楽しみです。

◆4番目は、甲賀市の油日小学校エコ委員会さん。
なんと、カラフルな忍者が登場しました!ビオトープに薬草園があるそうで地域由来の10種の薬草を育て、学習で活用しておられるそうです。忍者と薬のまち、甲賀ならではです。

エコ委員さんが油日小学校の活動の中心となり、学校のヒーローだそうです。

◆5番目は、NPO子どもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブさん。
太鼓の音と共に子どもたちが活動とその思いを大きな声で発表してくれました。

琵琶湖の源流の森での体験から川を経て琵琶湖、沖島での食など、上流から下流までをぐるっーと体験されました。
琵琶湖の外来魚問題では、「外来魚を食べて減らそうと言うけれど、売ってないやん!」と子どもの視点で表現してくれました。

沖島には、これからの暮らしのヒントがあるそうです。昨年度ESD研修会が沖島で催されましたが、子どもも沖島の暮らしを見て、これはっ!と思っているんですね。子どもの思い、大人の思い、それぞれを出し合うと、いい未来が作れそうです。

◆6番目は、なかす野洲川たんけん隊、やすたんの皆さんです。
地域の昔話の紙芝居で聞いて、その昔話を実際に地域で体験されました。

たらい舟に乗って野洲川へ漕ぎだしたり、昔話の舞台となっている地域でおじいさんおばあさん達に昔の様子をインタビューしたりと、今と昔を比べながら自分たちのまち野洲を体験しておられました。
スライドも紙芝居風にアレンジしておられ、工夫を感じます。

◆7番目は、大津市立瀬田北中学校 科学部の皆さんです。
長年続けておられる地域を流れる長沢川の研究活動を発表してくださりました。

地域の川を科学的な視点で研究を続けてくださっていることが、他の活動の目標にもなります。
スライドも生徒さんが作り、操作も自分たちでやってくださります。

◆8番目も、中学生による発表、大津市立伊香立中学校 アクアリウム部の皆さんです。
学校にはたくさんの水槽があり、そこで魚類を始めとする水生生物を繁殖しておられます。

特にメダカを育て、地域の祭などで販売し、そのお金を東日本大震災で被災した石巻へ送る活動を中心に行い、先輩たちから引き継ぎ、これまでの5年間で50万円以上を寄付しておられます。

◆休憩をはさんで、9番目は、大津市の浜大津保育園さんのおやおや?浜保クラブさんです。
お手製の映像と音楽と共に、子どもたちが歌い話してくださります。

長等公園へお散歩にでかけた時に、1匹のカエルと出会いその世話を通して生き物の世界と向き合っていく様子が表現されていました。
町中の保育園さんですが、自然と関わることはいっぱいあるんですね。

◆10番目は、大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDSさんです。
KIDSさんは、中高校生が中心となり、子ども会のリーダー活動だけでなく、外来魚を釣り食べるびわこエコフィッシングを企画し運営しておられます。

制服姿で登場され、劇を演じ、さらに動画と連動させておられました。

◆11番目は、大津市の和邇で活動しておられる、しがkidsエコクラブさんです。
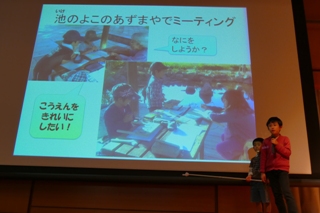
今年の夏頃から活動を始められ、子どもたちが地域の公園で会議をして活動を決めて、実施しておられるそうです。
ほんのすぐ近くの身近な場所を好きになる活動へつながっています。

◆12番目は、長浜市の湯田小学校 5年生ゆ~たん さんです。
5年生90名を代表して、子どもたちが参加してくださりました。

5年生が1年間「生きものがたり湯田小から」として、琵琶湖と地域のつながりを学ぶ学習を発表してくださりました。
大きな絵図には、たくさんの付箋が貼られ、子どもたちの発見や学びが書かれています。

◆最後の発表、13番目はGOキッズ 下之郷遺跡キッズクラブさんです。
貫頭衣や弓矢を身につけての登場です。
遺跡?歴史?と思われるかもしれませんが、昔と今の暮らしを体験し、未来につながっていく活動です。

火おこしや織物体験、そして当時の人が食べていたであろう食の体験や地域の人との交流を通して多くのことを学んでくださっています。
と、休憩をはさんで午前中2時間半、皆さんが発表をし、また聞き、時には質問をして(時間の関係で少ししかお聞きできず申し訳ありませんでした)、過ごしてくださりました。
午後は、博物館の自由見学と、体験コーナーです。

琵琶湖博物館のはしかけグループ「ほねほねクラブ」さんが、骨にさわってみよう体験を実施してくださりました。
自分の身体の中にある骨なのですが、普段、骨って意識していません。
あらためて、動物の骨を触りながら、身体の骨格の仕組みを体験しています。

こちらは、「地球温暖化防止活動推進員さん」による、食とエネルギー体験。
食べ物の旬クイズや旬以外には多くのエネルギーを費やして生産されていることなどを楽しく学びます。
そう言えば、昨日はクリスマスでした。ケーキに乗っているイチゴ。旬は冬と勘違いしていませんか?

こちらも、「地球温暖化防止活動推進員さん」による体験。火おこし体験。
中学生がうまくコツをつかんで、火をおこしていました。
火は人間の生活の基本のはずですが、オール電化や都市化など、火を見る使う機会がなくなりつつあります。

ホール前には、皆さんが作られた活動の壁新聞が貼られ、発表だけで伝えきれなかった活動の良さや詳細を知ることができます。
また、サポーターの方同志と立ち話で交流しておられたり、私もサポーターの方々とこどもエコクラブ活動の運営やこの交流会のあり方などを話したりしていました。
普段活動で横のつながりがなかなかできないサポーターの方同志が集える場にも、わずかですがなっていました。
さてさて、1日を掛けて行ってきた交流会も終盤、表彰式です。

今回は、大賞が「NPOこどもネットワークセンター天気村こんぺいとうクラブ」さんに決まりました!
奨励賞は、「ぼてじゃこワンパク塾」さん、「瀬田北中学校科学部」さん、「伊香立中学校アクアリウム部」さん、「湯田小学校5年生ゆ~たん」さん、「GOキッズ下之郷遺跡キッズクラブ」さん
審査委員特別賞は、「なかす野洲川たんけん隊」さん、活動賞は、「たまて林の会」さん、「アイキッズ エコアイディアキッズびわ湖」さん、「油日小学校」さん、「おやおや?浜保クラブ」さん、「大津市子ども会ジュニアリーダークラブKIDS」さん、「しがkidsエコクラブ」さん
が受賞されました。

最後は、環境学習センター所長 ビワマス博士の桑原所長から「来年のガンバロー」とエールが送られ終了しました。
参加してくださった皆さん、支えてくださったサポーターの皆さん、見に来てくださった保護者の方、本当にありがとうございました!
午後の体験でご協力いただいた滋賀県地球温暖化防止活動推進員の皆さん、ありがとうございました。
また、教師塾からお手伝いくださった7名の学生の皆さんもありがとうございました。地域で様々な子どもの活動があることを知ってもらう機会となりました。
そして、交流会の運営や参加してくださったクラブへご支援くださっている公益財団法人平和堂財団さんにも、本当に感謝申し上げます。
来年に向けて、皆さんにどんな支援ができるか、交流会としてどんな形にすべきかなど検討して皆さんに喜んでもらえる交流会にしていきたいと思っています。ご期待ください!
親子しぜんあそびの広場 12/22 のお知らせ
こどもと自然の研究所さんからのお知らせです。

「親子しぜんあそびの広場」
・日にち:2015年12月22日(火) ※火曜日ですので、お間違えなく!
・時 間:10:00から14:00(途中帰りもOKです)
・対 象:2~4才位の子どもと保護者の方 10 組
・場 所:琵琶湖博物館 生活実験工房 (古民家風の建物)
・内 容:森や田んぼでの自然遊びや、昔のくらしの体験をします。みんなと一緒に遊んだり、保護者の方と遊んだりして過ごします。
・持ち物:飲み物、お弁当、動きやすい格好、帽子、着替え、タオル、レジャーシートなど
・雨の時:雨でも遊びます。カッパや長靴などがあれば持参ください。
・参加費:無料です。受付時に駐車場の無料券もお渡しします。
・お申込み:eco.imasaru ★ mx.bw.dream.jp ★を@に変えてください。
件名に「あそび広場」と
保護者の方のお名前
お子さんのお名前・年令
お電話番号
をお知らせください。
来年1月は、1/27(水)の予定です。(博物館が第3週は休館日となっています)
こらもご覧ください。Fun with Nature まっちゃのブログ

「親子しぜんあそびの広場」
・日にち:2015年12月22日(火) ※火曜日ですので、お間違えなく!
・時 間:10:00から14:00(途中帰りもOKです)
・対 象:2~4才位の子どもと保護者の方 10 組
・場 所:琵琶湖博物館 生活実験工房 (古民家風の建物)
・内 容:森や田んぼでの自然遊びや、昔のくらしの体験をします。みんなと一緒に遊んだり、保護者の方と遊んだりして過ごします。
・持ち物:飲み物、お弁当、動きやすい格好、帽子、着替え、タオル、レジャーシートなど
・雨の時:雨でも遊びます。カッパや長靴などがあれば持参ください。
・参加費:無料です。受付時に駐車場の無料券もお渡しします。
・お申込み:eco.imasaru ★ mx.bw.dream.jp ★を@に変えてください。
件名に「あそび広場」と
保護者の方のお名前
お子さんのお名前・年令
お電話番号
をお知らせください。
来年1月は、1/27(水)の予定です。(博物館が第3週は休館日となっています)
こらもご覧ください。Fun with Nature まっちゃのブログ
「第5回よばれやんせ湖北」 に参加してきました
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと、池田勝です。
11/29(日)、長浜バイオ大学で開催されました「第5回よばれやんせ湖北 に参加してきました。
これまでの第1回から第4回までは、琵琶湖の美味しいビワマスやジビエ料理などをメインにして、まずは触れて食べてもらい、そして語らうという場を作って来られましたが、今年度はフォーラムとしてパネルディスカッションや講演を基本にして、未来を探ろうとのことで、開催されました。
(これまで、美味しそうな食がメインになっていましたが、全く参加できずでした。。。)
今回のテーマは「循環型社会における生産者と消費者のあり方」です。
そこに湖北の地産地消とそのビジネス展開が絡んで、どのような内容になるか楽しみです。
環境学習センターとしては、湖北が地産地消で元気になり、さらに循環型社会のモデルとなればなぁとの期待があり、そこに環境学習の要素を活かしていけないか、ヒントがあるかなぁと思っての参加でした。
まずは、循環型社会システム研究所代表の森建司さんの基調講演「地産地消で地域おこし~まず食から~」です。
旧びわ町出身で、新江州株式会社の社長を務められていた森さんは、主に企業向けの包装材料を扱っておられましたが、顧客のために何が出来るかを考え、「包装を減らそう」と動かれました。
例えばスーパー1店では約5万点の商品があり、その全てが包装され、行く行くはゴミになっていきす。
包装を減らすために、包装を扱っている会社自ら協議会を立ち上げて、減らそうと動かれました。
そのように、会社は自己矛盾を抱えています。同様に世の中の全ては自己矛盾があると話されました。
大量消費で使い捨てが流行ることに対して、もったいない(M)の心が必要であり、またこれまでの世代とこれからの未来の世代への共生を考えるおかげさま(O)、拡大社会に対してほどほど(H)に抑制することのMOHの精神の大切さを話されました。
ある会で、「ほどほどとは何ごとかと、それでは経済は発展しない!」と言われたそうです。しかし、現代の欲望が拡大を続け結果、未来の世代はどうなるのか、誰が未来に責任を持てるのかと反論したそうです。いまやハウスメーカーは、住宅でさえ25年程度の消耗品と捉えています。大企業は、人件費をいかに減らして競争に勝ち残るかを考える経済論理上にいますが、地域企業は、社員が家族であり、生産者と消費者を分ける必要はなく、常に同じ生活者で回っています。
さらに、食は生きていくために絶対に必要なものであり、経済至上主義の利益を目的とした経済活動から外すべきです。その食を生産する地域の農業が安心して生産が続けられる状況を守るシステムが、持続可能性社会となる第一歩ですと話されました。
途中、会場が思わず笑ってしまうようなエピソードやびっくりする事例などを交えながらお話しくださりました。
今回の会場では、ミナミハマぶどうジュースを試飲することができました。
ぶどうをそのまま絞ったジュースです。濃縮還元ではなく、そのまんまのぶどうです。美味しかった~

こちらは、ウッディパル余呉さんの商品。山焼きをされてつくられた赤かぶドレッシングも並んでいます。

ヨコタ農園さんのブース。イチゴソースがさわやかで美味しかったです。イチゴジャムと、ソースそれぞれ作り分けておられるんですね。
後半は、パネルディスカッションです。
コーディネーターを実行委員長の前川さん(ウッディパル余呉)がつとめられ、パネラーは、馬場さん(北びわこ水産)、横田さん(ヨコタ農園)、山本さん(旅館紅鮎)、コメンテーターは森さんです。
パネラーはそれぞれ、市場や流通に詳しい馬場さん、生産者として、また六次産業化を目指す横田さん、観光やサービス業からの山本さんと、立場が異なるため、話題は多岐に渡ります。
パネルディスカッションで、話されたことからいくつかあげますと、
・地産地消と言うが、それだけでは売りにくい。価値あるものでないと。また価値があれば、県内だけでなく、県外(外貨)を稼ぐことができる。その価値を発見するアイデアや育成、販売戦略が必要であり、モノ、人、金に合わせて、情熱と愛着があればこそである。
・最近、インバウンドや爆買いなどの訪日客の増加が報道されているが、長浜に来られるのは、ほとんどが金沢~京都、大阪の途中でついでという感じである。
・食の価値観が、以前のお腹の満足から、舌の満足、そして安心安全へと、頭の満足へと変わってきている。
・県外の方は、まだまだ滋賀の特産物への理解が浸透しておらず、高級な鮒ずしやコイ、アユなどを食べられない方も多い。
・今すぐの日常に使える地産地消は限定的であろう。しかし、世の中は確実に変わっていく。変わっていくという前提で、どのような方向性に向かうかを考えておくべきである。
・長浜という地域を考える際、対岸の高島を見て比べていることがある。高島は比較的移住者も多く出入りがあるが、長浜はどちらかというと閉鎖的ではないか。しかし、ここぞで集まれる強さを持っているのも長浜である。
・組織のトップは、「次のトップは誰にするか」を考えるのが仕事でもある。部下の仕事を奪うのではなく、トップしかできない仕事をし、計画的に物事を進めるべきである。
・WEBやSNSを活用して、自分をアピールしている。そこからのつながりや縁を感じ、それが元気になっている。また、後継者不足に対しては、まちおこしや農業従事者を増やす気概で事業を行っている。
特に印象に残ったのは、
「中学校の環境学習で習ったのは、多様性の大事さである。生き物にとって多様性が大事であるが、人も会社も多様性がないと元気になれない。」と、当時、湖北中学校が環境学習を熱心に取り組んでいたからこそ、今の考えや生き方につながっていると山本さんがお話しされたことです。
このフォーラムで、直接的に「環境学習」の言葉を聞くとは思ってもおらず、ビックリ、うれしい言葉でした。
環境学習は、直接環境行動を促すだけでなく、長い年月を経て、人を導くものであるものだと理解できたひと時でした。
パネルディスカッションに先だって、前川さんが「この会では、何かまとめるものではないが、たくさんのヒントがもらえる場となる」と話しておられたように、流通から、生産者から、サービスから、それぞれ長浜や地域の未来を考える人と出会い、学びのヒントをもらえたように思います。
来年は、どのような会になるのでしょうか。楽しみにしています。
11/29(日)、長浜バイオ大学で開催されました「第5回よばれやんせ湖北 に参加してきました。
これまでの第1回から第4回までは、琵琶湖の美味しいビワマスやジビエ料理などをメインにして、まずは触れて食べてもらい、そして語らうという場を作って来られましたが、今年度はフォーラムとしてパネルディスカッションや講演を基本にして、未来を探ろうとのことで、開催されました。
(これまで、美味しそうな食がメインになっていましたが、全く参加できずでした。。。)
今回のテーマは「循環型社会における生産者と消費者のあり方」です。
そこに湖北の地産地消とそのビジネス展開が絡んで、どのような内容になるか楽しみです。
環境学習センターとしては、湖北が地産地消で元気になり、さらに循環型社会のモデルとなればなぁとの期待があり、そこに環境学習の要素を活かしていけないか、ヒントがあるかなぁと思っての参加でした。
まずは、循環型社会システム研究所代表の森建司さんの基調講演「地産地消で地域おこし~まず食から~」です。
旧びわ町出身で、新江州株式会社の社長を務められていた森さんは、主に企業向けの包装材料を扱っておられましたが、顧客のために何が出来るかを考え、「包装を減らそう」と動かれました。
例えばスーパー1店では約5万点の商品があり、その全てが包装され、行く行くはゴミになっていきす。
包装を減らすために、包装を扱っている会社自ら協議会を立ち上げて、減らそうと動かれました。
そのように、会社は自己矛盾を抱えています。同様に世の中の全ては自己矛盾があると話されました。
大量消費で使い捨てが流行ることに対して、もったいない(M)の心が必要であり、またこれまでの世代とこれからの未来の世代への共生を考えるおかげさま(O)、拡大社会に対してほどほど(H)に抑制することのMOHの精神の大切さを話されました。
ある会で、「ほどほどとは何ごとかと、それでは経済は発展しない!」と言われたそうです。しかし、現代の欲望が拡大を続け結果、未来の世代はどうなるのか、誰が未来に責任を持てるのかと反論したそうです。いまやハウスメーカーは、住宅でさえ25年程度の消耗品と捉えています。大企業は、人件費をいかに減らして競争に勝ち残るかを考える経済論理上にいますが、地域企業は、社員が家族であり、生産者と消費者を分ける必要はなく、常に同じ生活者で回っています。
さらに、食は生きていくために絶対に必要なものであり、経済至上主義の利益を目的とした経済活動から外すべきです。その食を生産する地域の農業が安心して生産が続けられる状況を守るシステムが、持続可能性社会となる第一歩ですと話されました。
途中、会場が思わず笑ってしまうようなエピソードやびっくりする事例などを交えながらお話しくださりました。
今回の会場では、ミナミハマぶどうジュースを試飲することができました。
ぶどうをそのまま絞ったジュースです。濃縮還元ではなく、そのまんまのぶどうです。美味しかった~

こちらは、ウッディパル余呉さんの商品。山焼きをされてつくられた赤かぶドレッシングも並んでいます。

ヨコタ農園さんのブース。イチゴソースがさわやかで美味しかったです。イチゴジャムと、ソースそれぞれ作り分けておられるんですね。
後半は、パネルディスカッションです。
コーディネーターを実行委員長の前川さん(ウッディパル余呉)がつとめられ、パネラーは、馬場さん(北びわこ水産)、横田さん(ヨコタ農園)、山本さん(旅館紅鮎)、コメンテーターは森さんです。
パネラーはそれぞれ、市場や流通に詳しい馬場さん、生産者として、また六次産業化を目指す横田さん、観光やサービス業からの山本さんと、立場が異なるため、話題は多岐に渡ります。
パネルディスカッションで、話されたことからいくつかあげますと、
・地産地消と言うが、それだけでは売りにくい。価値あるものでないと。また価値があれば、県内だけでなく、県外(外貨)を稼ぐことができる。その価値を発見するアイデアや育成、販売戦略が必要であり、モノ、人、金に合わせて、情熱と愛着があればこそである。
・最近、インバウンドや爆買いなどの訪日客の増加が報道されているが、長浜に来られるのは、ほとんどが金沢~京都、大阪の途中でついでという感じである。
・食の価値観が、以前のお腹の満足から、舌の満足、そして安心安全へと、頭の満足へと変わってきている。
・県外の方は、まだまだ滋賀の特産物への理解が浸透しておらず、高級な鮒ずしやコイ、アユなどを食べられない方も多い。
・今すぐの日常に使える地産地消は限定的であろう。しかし、世の中は確実に変わっていく。変わっていくという前提で、どのような方向性に向かうかを考えておくべきである。
・長浜という地域を考える際、対岸の高島を見て比べていることがある。高島は比較的移住者も多く出入りがあるが、長浜はどちらかというと閉鎖的ではないか。しかし、ここぞで集まれる強さを持っているのも長浜である。
・組織のトップは、「次のトップは誰にするか」を考えるのが仕事でもある。部下の仕事を奪うのではなく、トップしかできない仕事をし、計画的に物事を進めるべきである。
・WEBやSNSを活用して、自分をアピールしている。そこからのつながりや縁を感じ、それが元気になっている。また、後継者不足に対しては、まちおこしや農業従事者を増やす気概で事業を行っている。
特に印象に残ったのは、
「中学校の環境学習で習ったのは、多様性の大事さである。生き物にとって多様性が大事であるが、人も会社も多様性がないと元気になれない。」と、当時、湖北中学校が環境学習を熱心に取り組んでいたからこそ、今の考えや生き方につながっていると山本さんがお話しされたことです。
このフォーラムで、直接的に「環境学習」の言葉を聞くとは思ってもおらず、ビックリ、うれしい言葉でした。
環境学習は、直接環境行動を促すだけでなく、長い年月を経て、人を導くものであるものだと理解できたひと時でした。
パネルディスカッションに先だって、前川さんが「この会では、何かまとめるものではないが、たくさんのヒントがもらえる場となる」と話しておられたように、流通から、生産者から、サービスから、それぞれ長浜や地域の未来を考える人と出会い、学びのヒントをもらえたように思います。
来年は、どのような会になるのでしょうか。楽しみにしています。
栗東走井でつけもの講座がありました
こんにちは。環境学習センターのまっちゃこと、池田勝です。

先週の11/28(土)に、栗東市走井でありました「つけもの講座」に取材に行ってきました。
走井地区は、棚田ボランティア活動を受入れておられ、収穫祭「ハーベスタ走井」など地域おこしイベントを実践されるなど、元気に活動しておられる地域です。
今回は、棚田ボランティア活動の一環として、たくあん漬けの講習をされるとのこと。
走井地区には棚田の草刈りやハーベスタ走井とお邪魔しているので、そりゃーおもしろそうだ!と思い、秋晴れの土曜日に出かけました。

講師は、走井地区の世話役中西さんのお兄さんです。草津市内の道の駅にも、お漬物を卸しておられる農家さんです。

今回は、地域でつくっておられる山田ねずみ大根のたくあん漬けを作ります。
山田ねずみは大根の先っちょが、ネズミのしっぽのように可愛く細長いのです。
草津では昔から作られた滋賀ならではの野菜です。
1週間ほど、干しておいてくださっています。

参加されたのは、地元走井や、栗東市内、湖南市、草津市と11組の方です。
よく漬けもの作りをされる方がさらに勉強と思って来られたり、やったことあるけど失敗して再チャレンジという方、浅漬け程度しかやったことないので今回を機会に漬けものづくりをしたいという方など様々です。
募集は8組だったのですが、すぐに定員となり、急遽11組まで枠を広げたという盛況ぶりです。

で、早速たくあん漬けの準備。まずは葉っぱと根を切り分けます。

約4キロの大根の重量を量ります。
さすが農家さん、量りが年代物の天秤ばかりです。

こちらが、大根以外の材料のネタ。ぬか、塩と、漬けものの素です。
漬けものの素は、色付け用のウコンと甘みをつけるサッカリンが含まれています。
サッカリンの代わりにグラニュー糖を使う方もおられるとのこと。
「素がない昔はどうしておられたのですか?」と聞きますと、
「ぬかと塩だけのたくあんやったよ。また、甘味が欲しい時は渋ガキを剥いた時の皮を干しておいてたくあんを漬ける時に入れた」とのこと。渋ガキの皮が甘味を出すんですね。不思議です。
他に、なすびの葉っぱを干して入れたという情報もあり、漬けものの多様性や地域性の奥深さを感じます。

材料が出来たら、ビニール袋を入れた樽に、ネタと大根を交互に入れていきます。
隙間には大根の葉っぱを入れて(この葉っぱが美味しいとのこと。漬けものとして出来たら、刻んでご飯にまぶして、ちょっとお醤油を掛けて食べるとグッド!とのこと)、隙間なくならべていきます。
大根は井型にはせず、同じ方向にするそうです。その方が、取り出したり、順番を変えたりする際に崩れないそうです。

皆さん、心をこめて漬けていかれます。「おいしくなーれ」

樽の中の、途中の様子。

最後は、みんなではいチーズ。
約3週間ほど、お正月前には食べられるそうです。
終了後には、いろいろと質問が出てきます。
Q:重石はどれくらいが良いですか?
A:大根の重さの二倍以上がいい
Q:塩っ辛い時はどうすれば?
A:水に漬けたりしないで、ぜいたく煮にすると良い。
Q:置き場所は?
A:温度が一定で、日陰の涼しい所が良い。
Q:手入れはしたらよいの?
A:しなくて良い。食べ始めと、中、終わりでは味が変わる。漬けものは発酵食なので、だんだん酸っぱくなる。3週間から5週間頃が食べごろ。
Q:土用越しの漬けもの(夏まで漬ける)にしたいんやけど。
A:塩を倍にして漬けると良い。
Q:残った樽の糠の利用方法はあるか?
A:走井では、獣害対策で、檻をおいているので、そのエサに使うので、残ったら走井まで持って来てください。
皆さん、とっても熱心です。
最後に中西さんからの言葉 「漬けものは、経験と勘と度胸!」の言葉で締めくくられました。
ど素人の私にも分かるほど、簡単な方法でたくあん漬けができるんです。
(最初ぬか漬けと思い、手入れとか大変なのではと、勘違いしていました)
皆さん、これからいろいろな漬けものにチャレンジしてみたいとお話ししておられました。
「また走井に来て、教えてもらわないとね」とも
棚田地域の持つ技や文化と、都市の人たちの発見が、漬けものをきっかけにマッチしたようです。
ぜひ、皆さん棚田ボランティアへ、お出かけください。
人と地域とつながって、たくさんの発見と学びがありますよ。
おうみ棚田ボランティアの12月から3月の活動予定はこちら。

先週の11/28(土)に、栗東市走井でありました「つけもの講座」に取材に行ってきました。
走井地区は、棚田ボランティア活動を受入れておられ、収穫祭「ハーベスタ走井」など地域おこしイベントを実践されるなど、元気に活動しておられる地域です。
今回は、棚田ボランティア活動の一環として、たくあん漬けの講習をされるとのこと。
走井地区には棚田の草刈りやハーベスタ走井とお邪魔しているので、そりゃーおもしろそうだ!と思い、秋晴れの土曜日に出かけました。

講師は、走井地区の世話役中西さんのお兄さんです。草津市内の道の駅にも、お漬物を卸しておられる農家さんです。

今回は、地域でつくっておられる山田ねずみ大根のたくあん漬けを作ります。
山田ねずみは大根の先っちょが、ネズミのしっぽのように可愛く細長いのです。
草津では昔から作られた滋賀ならではの野菜です。
1週間ほど、干しておいてくださっています。

参加されたのは、地元走井や、栗東市内、湖南市、草津市と11組の方です。
よく漬けもの作りをされる方がさらに勉強と思って来られたり、やったことあるけど失敗して再チャレンジという方、浅漬け程度しかやったことないので今回を機会に漬けものづくりをしたいという方など様々です。
募集は8組だったのですが、すぐに定員となり、急遽11組まで枠を広げたという盛況ぶりです。

で、早速たくあん漬けの準備。まずは葉っぱと根を切り分けます。

約4キロの大根の重量を量ります。
さすが農家さん、量りが年代物の天秤ばかりです。

こちらが、大根以外の材料のネタ。ぬか、塩と、漬けものの素です。
漬けものの素は、色付け用のウコンと甘みをつけるサッカリンが含まれています。
サッカリンの代わりにグラニュー糖を使う方もおられるとのこと。
「素がない昔はどうしておられたのですか?」と聞きますと、
「ぬかと塩だけのたくあんやったよ。また、甘味が欲しい時は渋ガキを剥いた時の皮を干しておいてたくあんを漬ける時に入れた」とのこと。渋ガキの皮が甘味を出すんですね。不思議です。
他に、なすびの葉っぱを干して入れたという情報もあり、漬けものの多様性や地域性の奥深さを感じます。

材料が出来たら、ビニール袋を入れた樽に、ネタと大根を交互に入れていきます。
隙間には大根の葉っぱを入れて(この葉っぱが美味しいとのこと。漬けものとして出来たら、刻んでご飯にまぶして、ちょっとお醤油を掛けて食べるとグッド!とのこと)、隙間なくならべていきます。
大根は井型にはせず、同じ方向にするそうです。その方が、取り出したり、順番を変えたりする際に崩れないそうです。

皆さん、心をこめて漬けていかれます。「おいしくなーれ」

樽の中の、途中の様子。

最後は、みんなではいチーズ。
約3週間ほど、お正月前には食べられるそうです。
終了後には、いろいろと質問が出てきます。
Q:重石はどれくらいが良いですか?
A:大根の重さの二倍以上がいい
Q:塩っ辛い時はどうすれば?
A:水に漬けたりしないで、ぜいたく煮にすると良い。
Q:置き場所は?
A:温度が一定で、日陰の涼しい所が良い。
Q:手入れはしたらよいの?
A:しなくて良い。食べ始めと、中、終わりでは味が変わる。漬けものは発酵食なので、だんだん酸っぱくなる。3週間から5週間頃が食べごろ。
Q:土用越しの漬けもの(夏まで漬ける)にしたいんやけど。
A:塩を倍にして漬けると良い。
Q:残った樽の糠の利用方法はあるか?
A:走井では、獣害対策で、檻をおいているので、そのエサに使うので、残ったら走井まで持って来てください。
皆さん、とっても熱心です。
最後に中西さんからの言葉 「漬けものは、経験と勘と度胸!」の言葉で締めくくられました。
ど素人の私にも分かるほど、簡単な方法でたくあん漬けができるんです。
(最初ぬか漬けと思い、手入れとか大変なのではと、勘違いしていました)
皆さん、これからいろいろな漬けものにチャレンジしてみたいとお話ししておられました。
「また走井に来て、教えてもらわないとね」とも
棚田地域の持つ技や文化と、都市の人たちの発見が、漬けものをきっかけにマッチしたようです。
ぜひ、皆さん棚田ボランティアへ、お出かけください。
人と地域とつながって、たくさんの発見と学びがありますよ。
おうみ棚田ボランティアの12月から3月の活動予定はこちら。








