夏休みのイベントいっぱい!そよかぜきまぐれ通信を発行しました
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
滋賀の環境学習メールマガジン(2012.7.18発行)
そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」
発行:琵琶湖博物館 環境学習センター
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします
+------------------------------+
|琵琶湖博物館の今、ホットな話題|
+------------------------------+
琵琶湖博物館の来館者数が800万人を突破しました!
これを祝して、記念セレモニーが先月29日に開催されました。
今後とも琵琶湖博物館をよろしくお願いいたします。
+------+
|もくじ+---------------------------------------------------
+------+
1. ビワマス博士・桑原所長のコラム
2. 7月から8月の参加イベント
3. 講座・お楽しみ、など
4. 助成金・募集、など
*---------------------------------------------------------*
予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。
+---+
| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム
+---+-------------------------------
「ビワマスの夏がやってきた!!」
今回は、夏の琵琶湖を代表する湖魚「ビワマス」を紹介します。
ビワマスは、サクラマスやサツキマスに近縁なサケ科の魚で、琵琶湖の
固有亜種とされています。サケ科の魚ですから、本来冷たい水でないと生
きていくことができません。それでは、なぜ夏の魚になるのでしょうか。
6月になるとビワマス漁が始まります。ビワマス漁は、小糸網と呼ばれる
刺し網を使って行われます。6月頃になると、表層の水温が上昇し、北湖で
は水深20mくらいのところに水温躍層という急激に温度の下がる層ができま
す。冷たい水の好きなビワマスは、水温躍層より上層を泳ぐアユを食べる
ために、水温躍層付近に集まって来ると考えられます。そのため、漁師は
この層に小糸網をかけることで、ビワマスを効率よく漁獲することができ
るのです。漁期は9月末までで、10月・11月は産卵保護のため禁漁になりま
す。その後、禁漁開けの12月から5月頃までは、琵琶湖全体の水温が下がる
ことからビワマスの泳ぐ層が決まらず、効率よく漁獲できなくなるため、
ビワマスを専門に狙う漁は行われません。ビワマスが夏の魚とされるのは、
このような理由によるものです。また、真夏はビワマス漁以外の主要な漁
はほとんど行われず、漁の端境期となるため、漁師にとっては夏の貴重な
漁獲魚ともなっています。
さて、このビワマス、湖魚の中でも最も美味しい魚の一つとされ、刺身
や塩焼きを初めとして、いろんな料理で美味しく食べることができます。
ぜひこの機会に、一度ビワマスを食べてみてください。
続きを読む
滋賀の環境学習メールマガジン(2012.7.18発行)
そ よ か ぜ 「きまぐれ通信」
発行:琵琶湖博物館 環境学習センター
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(号外)環境学習に関する情報を、きまぐれにお届けします
+------------------------------+
|琵琶湖博物館の今、ホットな話題|
+------------------------------+
琵琶湖博物館の来館者数が800万人を突破しました!
これを祝して、記念セレモニーが先月29日に開催されました。
今後とも琵琶湖博物館をよろしくお願いいたします。
+------+
|もくじ+---------------------------------------------------
+------+
1. ビワマス博士・桑原所長のコラム
2. 7月から8月の参加イベント
3. 講座・お楽しみ、など
4. 助成金・募集、など
*---------------------------------------------------------*
予約などについてご確認の上、各イベントにお出かけください。
+---+
| 1 + ビワマス博士・桑原所長のコラム
+---+-------------------------------
「ビワマスの夏がやってきた!!」
今回は、夏の琵琶湖を代表する湖魚「ビワマス」を紹介します。
ビワマスは、サクラマスやサツキマスに近縁なサケ科の魚で、琵琶湖の
固有亜種とされています。サケ科の魚ですから、本来冷たい水でないと生
きていくことができません。それでは、なぜ夏の魚になるのでしょうか。
6月になるとビワマス漁が始まります。ビワマス漁は、小糸網と呼ばれる
刺し網を使って行われます。6月頃になると、表層の水温が上昇し、北湖で
は水深20mくらいのところに水温躍層という急激に温度の下がる層ができま
す。冷たい水の好きなビワマスは、水温躍層より上層を泳ぐアユを食べる
ために、水温躍層付近に集まって来ると考えられます。そのため、漁師は
この層に小糸網をかけることで、ビワマスを効率よく漁獲することができ
るのです。漁期は9月末までで、10月・11月は産卵保護のため禁漁になりま
す。その後、禁漁開けの12月から5月頃までは、琵琶湖全体の水温が下がる
ことからビワマスの泳ぐ層が決まらず、効率よく漁獲できなくなるため、
ビワマスを専門に狙う漁は行われません。ビワマスが夏の魚とされるのは、
このような理由によるものです。また、真夏はビワマス漁以外の主要な漁
はほとんど行われず、漁の端境期となるため、漁師にとっては夏の貴重な
漁獲魚ともなっています。
さて、このビワマス、湖魚の中でも最も美味しい魚の一つとされ、刺身
や塩焼きを初めとして、いろんな料理で美味しく食べることができます。
ぜひこの機会に、一度ビワマスを食べてみてください。
続きを読む
須原魚のゆりかご水田観察会
■□■お魚ホントにいるのかな?
6月23日(土)、滋賀県の野洲市で行われた須原魚のゆりかご水田観察会に参加してきまし
た。(主催:須原魚のゆりかご水田協議会)
魚のゆりかご水田では、田植え後の雨の日、水をはった田んぼに琵琶湖からの魚が遡上し
てきます。魚たちは田んぼで卵を産んで、孵化した稚魚は田んぼで育ちます。前の週に台
風が来て、雨が降ったけど、魚は田んぼに上がってきているかな?卵からかえった赤ちゃ
んの魚を見られるかな?
■□■カエルがいっぱい
最初に見つけたのは、小指の先ぐらいの小さなカエル。まだ、おたまじゃくしの頃のしっ
ぽがついたままのカエルを見つけた男の子もいました。
■□■外来種もいたよ。
赤い卵を産むジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)やザリガニがたくさんいました。これ
らは外来種と言って、もともと日本にいない生物たち。田んぼにもたくさん外来種がいる
なんて、複雑な気分。

■□■鳥の足跡発見!
ぬかるみに鳥の足跡を発見しました。何の鳥かな。田んぼの周りには、魚や貝、カエルに
鳥、いろんな生物がいるんだね。

■□■念願のフナ発見!
なかなか、魚が見つからなくて、不安になってきた頃、「あっ魚がいた!」
よくよく見ると、魚の背びれが見えたり、魚のいるあたりは水路の水が渦を巻いていたり
します。魚を見つけるには、魚がどこにいるかしっかり見つける「目」が必要みたいです
ね。

■□■魚をさわってみよう
取った魚をバケツや小さなプールに入れて、みんなでさわってみることにしました。少し
濁った水にこわごわ手を入れて、魚をつかんでみるけど、ツルッと滑ってしまいます。で
も、だんだん慣れてくると魚を簡単につかめるようになりました。つかんだ魚をバケツに
入れて、次はどんな魚がいたか、お話を聞きましょう。

■□■どんな魚がいたのかな
滋賀県立大学の皆川先生が取った魚を大、中、小に分けて、水槽に入れてくれました。見
たことないぐらい小さい魚の赤ちゃんに、みんなかわいいーと声をあげていました。一番、
多くいたのは銀ブナやニゴロブナ。他にはドジョウにナマズ、メダカもいました。メダカ
の学名は田んぼにいる平たい魚という意味で、昔から田んぼで見られる魚だそうです。

■□■魚はどうして田んぼに来るの?
先生の質問に、「流れがゆっくりだから」「食べ物がたくさんあるから」「天敵がいないから」
子どもたちが、ぽんぽんと答えていきます。先生も「みんなよく知っているね」と目をま
るくしながら、田んぼの水は温かくて、卵がかえりやすいこと、たくさんプランクトンが
いて栄養が豊富なこと、そして、食べられるような敵がいないことを説明してくれました。
「みんな、ごはんを食べる時に、田んぼには魚がいたな、楽しく遊んだな、と思い出して
ください」と皆川先生は言いました。ごはんを食べながら、魚を想う。ごはんと魚がつな
がっているなんて、今まで考えたことがありませんでした。

■□■ゆりかご水田米と須原の野菜カレー
最後にゆりかご水田米と須原の野菜を使った美味しいカレーを食べました。須原の新鮮な
野菜は販売もしていました。
初めて参加したという男の子。最初は魚を怖がっていたのに、カレーを食べた後は「僕、
もう平気」と魚をさわっていました。いろいろな発見や子どもたちの成長がみられ、大満
足の半日でした。
観察会の様子はびわこ放送で
7月21日(土)13:00~13:30、
22日(日)18:30~19:00に放送されます。是非、ごらんください。
環境学習推進員 正阿彌 崇子
6月23日(土)、滋賀県の野洲市で行われた須原魚のゆりかご水田観察会に参加してきまし
た。(主催:須原魚のゆりかご水田協議会)
魚のゆりかご水田では、田植え後の雨の日、水をはった田んぼに琵琶湖からの魚が遡上し
てきます。魚たちは田んぼで卵を産んで、孵化した稚魚は田んぼで育ちます。前の週に台
風が来て、雨が降ったけど、魚は田んぼに上がってきているかな?卵からかえった赤ちゃ
んの魚を見られるかな?
■□■カエルがいっぱい
最初に見つけたのは、小指の先ぐらいの小さなカエル。まだ、おたまじゃくしの頃のしっ
ぽがついたままのカエルを見つけた男の子もいました。
■□■外来種もいたよ。
赤い卵を産むジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)やザリガニがたくさんいました。これ
らは外来種と言って、もともと日本にいない生物たち。田んぼにもたくさん外来種がいる
なんて、複雑な気分。
■□■鳥の足跡発見!
ぬかるみに鳥の足跡を発見しました。何の鳥かな。田んぼの周りには、魚や貝、カエルに
鳥、いろんな生物がいるんだね。
■□■念願のフナ発見!
なかなか、魚が見つからなくて、不安になってきた頃、「あっ魚がいた!」
よくよく見ると、魚の背びれが見えたり、魚のいるあたりは水路の水が渦を巻いていたり
します。魚を見つけるには、魚がどこにいるかしっかり見つける「目」が必要みたいです
ね。
■□■魚をさわってみよう
取った魚をバケツや小さなプールに入れて、みんなでさわってみることにしました。少し
濁った水にこわごわ手を入れて、魚をつかんでみるけど、ツルッと滑ってしまいます。で
も、だんだん慣れてくると魚を簡単につかめるようになりました。つかんだ魚をバケツに
入れて、次はどんな魚がいたか、お話を聞きましょう。
■□■どんな魚がいたのかな
滋賀県立大学の皆川先生が取った魚を大、中、小に分けて、水槽に入れてくれました。見
たことないぐらい小さい魚の赤ちゃんに、みんなかわいいーと声をあげていました。一番、
多くいたのは銀ブナやニゴロブナ。他にはドジョウにナマズ、メダカもいました。メダカ
の学名は田んぼにいる平たい魚という意味で、昔から田んぼで見られる魚だそうです。
■□■魚はどうして田んぼに来るの?
先生の質問に、「流れがゆっくりだから」「食べ物がたくさんあるから」「天敵がいないから」
子どもたちが、ぽんぽんと答えていきます。先生も「みんなよく知っているね」と目をま
るくしながら、田んぼの水は温かくて、卵がかえりやすいこと、たくさんプランクトンが
いて栄養が豊富なこと、そして、食べられるような敵がいないことを説明してくれました。
「みんな、ごはんを食べる時に、田んぼには魚がいたな、楽しく遊んだな、と思い出して
ください」と皆川先生は言いました。ごはんを食べながら、魚を想う。ごはんと魚がつな
がっているなんて、今まで考えたことがありませんでした。
■□■ゆりかご水田米と須原の野菜カレー
最後にゆりかご水田米と須原の野菜を使った美味しいカレーを食べました。須原の新鮮な
野菜は販売もしていました。
初めて参加したという男の子。最初は魚を怖がっていたのに、カレーを食べた後は「僕、
もう平気」と魚をさわっていました。いろいろな発見や子どもたちの成長がみられ、大満
足の半日でした。
観察会の様子はびわこ放送で
7月21日(土)13:00~13:30、
22日(日)18:30~19:00に放送されます。是非、ごらんください。
環境学習推進員 正阿彌 崇子
ニゴローの大冒険 はじまるよ!
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
琵琶博では、明日7/14から企画展「ニゴローの大冒険~フナから見た田んぼの生き物のにぎわい~」が始まります!
今日はその一部だけをこそっと紹介します。
入り口では、紹介役の大塚学芸員(そっくり)と今回の主人公ニゴロブナのニゴローが迎えてくれます。
ダルマガエルも田んぼにいる仲間です。展示模型は、めっちゃでっかいです。
プランクトンが田んぼで大発生。それをニゴローたちが食べてすくすく大きくなるんですね。
タマミジンコってこんな形してるんですね。立体的に、しかもこんなにでっかい模型はビックリです。
「田んぼの一年」の屏風。すごい迫力です。大きすぎて、斜めからしか撮れませんでした。
田んぼと言えば、コサギ(左)やアマサギ(右)の鳥たち。
コサギは、田んぼの真ん中で何かをつついている(食べ物を探してるのでしょうね)のが、印象的です。
アマサギは、田起こしの際トラクターの後ろについてまわってる大胆な鳥です。
田起こしで出てきたミミズや虫たちを食べてるのでしょうね。
田んぼにいる虫たちも標本で展示されています。ゲンゴロウってこんなにいろいろと種類いるんですね。
のほほんと見学していると、いきなり天井からニョキーンッ!なんじゃこれ?
正解は展示をじっくりみてもらうと分かります。(ヒント:食べられないようにね)
こんな男の子も登場します!これもまた何で・・・?という感じですが、展示を見てるとフムフム分かってくるのです。
段ボールで出来た階段?そうニゴローのための階段なんです。
(注意:人は登っちゃだめよ!)
田んぼの研究者たち。田んぼと言えども、いろんな研究してはるんやなぁと感心。
手作りのフィギュアも並んでます。研究者や学芸員だけでなく、一般の方も協力してくださっています。
君も檻に捕らえられてみよう!って言うのはおかしいのですが、ニゴローの気持ちになって、仕掛けに入ってみましょう。
人が捕まる仕掛けだけでなく、ちゃんとニゴローたち魚を捕る本物の漁の道具も展示しています。
たくさんの展示のほんの一部を紹介しました。
ぜひ来場して、ニゴローの気持ちになって、探検してみてください。お待ちしてます。
・・・追加でお知らせ・・・
同時開催として、「ぼくらは田んぼの合唱団 -滋賀にすむカエルたち-」も開催しています。
カエル好きは必見!そちらもこちらのブログで紹介しますので、お楽しみに!
琵琶湖博物館 第20回企画展示 ニゴローの大冒険 ~フナから見た田んぼの生き物のにぎわい~
日時:2012年7月14日(土)~11月25日(日) 9:30~17:00(入館は16:30まで)
場所:琵琶湖博物館 企画展示室
観覧料金:小中学生 100円、高校大学生 160円、一般 200円
再生可能エネルギー地域フォーラムin湖南
6月3日(日)、湖南市共同福祉施設で行われた「再生可能エネルギー地域フォーラムin湖南」に参加してきました。(主催:こにゃん支え合いプロジェクト推進協議会)
7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されました。湖南市でも以前から取り組んでいた共同発電にさらに発展させ、福祉や食と組み合わせたプロジェクトが始まります。フォーラムでは、共同発電や市民が主人公であることの意義などを、講演、分科会を通して考える内容でした。市内外から102名の参加がありました。
■自然エネルギーは市民が主人公-市民共同発電の挑戦-
はじめに、日本環境学会会長の和田武先生の「自然エネルギーは市民が主人公-市民共同
発電の挑戦-」という題目で基調講演がありました。
和田先生は、再生可能エネルギーの特性や日本での可能性をグラフや数値などを用いて、
説明してくださいました。
■自然エネルギーで地域を魅力的に
再生可能エネルギーが普及することにより、衰退している地域を魅力のある地域に変えら
れる可能性があることを、ドイツの過疎地域の話などを交えてわかりやすく話してくださ
いました。ドイツでは、再生可能エネルギーを取り入れたことで、若者が都市部から帰っ
て来られた町や、住民が太陽光発電の土台を開発し、今は海外に輸出までしている町など、
写真を交えての話に多くの人が農山村での再生エネルギーの可能性を感じました。
■地域と市民が主役でないと意味がない
和田先生はたとえ再生可能エネルギーが増えても、企業や国がその主体では意味がない。
市民、自治体などの地域主体を含む広範な主体が再生可能エネルギーに取り組みことで、
地域を魅力的に変えることにつながると強調されました。

2部は「自然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?」と「自然エネル
ギーを地域のものとする制度・政策のあり方」の2つの分科会に分かれました。私は「自
然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?」に参加しました。
■自然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?
1部の基調講演をふまえ、こにゃん支え合いプロジェクト会長の溝口弘氏がコーディネー
ター、谷畑英吾市長、ひがしおうみコミュニティビジネス推進協議会の橋本憲氏がパネ
ラーで分科会が進められました。
谷畑市長はクリーン・エネルギー、障がい者福祉、地産地消の食材、の3つをキーワー
ドとしたまちづくりについて、橋本氏は東近江氏で行われた太陽光発電事業によるコミ
ュニティビジネスのしくみについて発表されました。
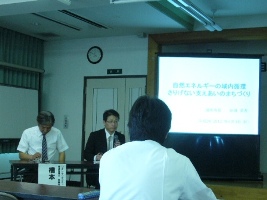
■ 市民が主役と分かっていても…
発表後の質疑や議論では、市民共同発電などについて市民的盛り上がりをいかに作って
いくかが議論の焦点になりました。意見の中には市民共同発電をつけた障がい者施設を
災害避難場所に指定し、停電をしていても太陽光発電で電気を使えるということを売り
に市民に関心を持ってもらってはどうかというアイデアもでました。
■湖南市、自然エネルギー基本条例案を発表
フォーラムを通して、市民や地域が主体となって、再生可能エネルギーを作っていくこ
とが大切であるが、多くの市民とその盛り上がりを作って行くのには、課題が残ってい
ることも分かりました。
フォーラム後の7月3日、湖南市は自然エネルギー基本条例案を発表しました。条例案
では、自然エネルギーを「地域に根ざした主体が、地域の発展に資するよう活用する」
と規定しています。また、市民共同発電所の計画を後押し、売電による収益を地域通貨
にして、地域福祉や特産品の振興にあてるとしています。
私たちは湖南市のような課題を持ちながらも一歩一歩進んでいる地域から、いろいろな
ことを学んでいくことができると感じました。
環境学習推進員 正阿彌 崇子
7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されました。湖南市でも以前から取り組んでいた共同発電にさらに発展させ、福祉や食と組み合わせたプロジェクトが始まります。フォーラムでは、共同発電や市民が主人公であることの意義などを、講演、分科会を通して考える内容でした。市内外から102名の参加がありました。
■自然エネルギーは市民が主人公-市民共同発電の挑戦-
はじめに、日本環境学会会長の和田武先生の「自然エネルギーは市民が主人公-市民共同
発電の挑戦-」という題目で基調講演がありました。
和田先生は、再生可能エネルギーの特性や日本での可能性をグラフや数値などを用いて、
説明してくださいました。
■自然エネルギーで地域を魅力的に
再生可能エネルギーが普及することにより、衰退している地域を魅力のある地域に変えら
れる可能性があることを、ドイツの過疎地域の話などを交えてわかりやすく話してくださ
いました。ドイツでは、再生可能エネルギーを取り入れたことで、若者が都市部から帰っ
て来られた町や、住民が太陽光発電の土台を開発し、今は海外に輸出までしている町など、
写真を交えての話に多くの人が農山村での再生エネルギーの可能性を感じました。
■地域と市民が主役でないと意味がない
和田先生はたとえ再生可能エネルギーが増えても、企業や国がその主体では意味がない。
市民、自治体などの地域主体を含む広範な主体が再生可能エネルギーに取り組みことで、
地域を魅力的に変えることにつながると強調されました。
2部は「自然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?」と「自然エネル
ギーを地域のものとする制度・政策のあり方」の2つの分科会に分かれました。私は「自
然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?」に参加しました。
■自然エネルギーは地域のもの~地域・市民はなにができるの?
1部の基調講演をふまえ、こにゃん支え合いプロジェクト会長の溝口弘氏がコーディネー
ター、谷畑英吾市長、ひがしおうみコミュニティビジネス推進協議会の橋本憲氏がパネ
ラーで分科会が進められました。
谷畑市長はクリーン・エネルギー、障がい者福祉、地産地消の食材、の3つをキーワー
ドとしたまちづくりについて、橋本氏は東近江氏で行われた太陽光発電事業によるコミ
ュニティビジネスのしくみについて発表されました。
■ 市民が主役と分かっていても…
発表後の質疑や議論では、市民共同発電などについて市民的盛り上がりをいかに作って
いくかが議論の焦点になりました。意見の中には市民共同発電をつけた障がい者施設を
災害避難場所に指定し、停電をしていても太陽光発電で電気を使えるということを売り
に市民に関心を持ってもらってはどうかというアイデアもでました。
■湖南市、自然エネルギー基本条例案を発表
フォーラムを通して、市民や地域が主体となって、再生可能エネルギーを作っていくこ
とが大切であるが、多くの市民とその盛り上がりを作って行くのには、課題が残ってい
ることも分かりました。
フォーラム後の7月3日、湖南市は自然エネルギー基本条例案を発表しました。条例案
では、自然エネルギーを「地域に根ざした主体が、地域の発展に資するよう活用する」
と規定しています。また、市民共同発電所の計画を後押し、売電による収益を地域通貨
にして、地域福祉や特産品の振興にあてるとしています。
私たちは湖南市のような課題を持ちながらも一歩一歩進んでいる地域から、いろいろな
ことを学んでいくことができると感じました。
環境学習推進員 正阿彌 崇子
「保存食を科学する」シリーズ第1弾!湖魚をつかって佃煮づくり
7月7日(土)、琵琶湖博物館の実習室で「湖魚の佃煮」講座が開催されました。
実際に調理する様子を見学しながら、保存食としての佃煮のナゾにせまります!

今回使用した湖魚は小アユ。
たっぷり1kgあります。

まずは、鍋のなかに調味料を入れて加熱します。
ここで調味料をよーく混ぜておかなければ、あとで砂糖が焦げついてしまうそうです。
混ぜきったところで小アユを投入し、しばらく煮詰めます。

小アユに味をしみこませている間、学芸員さんが佃煮のフシギをわかりやすく紹介。
佃煮の調理過程を見てゆくと、何気ない作業に小魚の保存性を高めるための「科学」がひそんでいることがわかりました。

さて、煮詰めた小アユは一度ザルに移します。
煮汁は再びなべに戻して沸騰させ、小アユにかけていきます。
完成品はこちら!

今回お味は2種類。
左は地元の漁業協同組合さんから教えていただいたレシピでつくったもの。
まさに佃煮といったお味で、噛めば噛むほど甘みが口の中に広がっていくのを感じました。
右は学芸員さんによる味付け。
こちらは煮汁のかけ足しはせずに、身が少しふっくらしたまま盛りつけたものです。
小アユの苦みと山椒の香りが絶妙に絡み合った、煮付け風のお味でした。
どちらも美味しくいただきました
食べていくうちに、ちりめんモンスターならぬ佃煮モンスターを発見しました!

左から、ブルーギル、小アユ、エビ。
召し上がった方いわく、ブルーギルのお味は「しわい」。
「しわい」とは「かたくて筋張っている」という意味で、鳥取県や岡山県では日常で使うそうです。
「保存食を科学する」は、今後「ふなずし」と「かんぴょう」をテーマに実施される予定です。
http://www.lbm.go.jp/event/index.html#kouza
お気軽にご応募ください。
実際に調理する様子を見学しながら、保存食としての佃煮のナゾにせまります!
今回使用した湖魚は小アユ。
たっぷり1kgあります。
まずは、鍋のなかに調味料を入れて加熱します。
ここで調味料をよーく混ぜておかなければ、あとで砂糖が焦げついてしまうそうです。
混ぜきったところで小アユを投入し、しばらく煮詰めます。
小アユに味をしみこませている間、学芸員さんが佃煮のフシギをわかりやすく紹介。
佃煮の調理過程を見てゆくと、何気ない作業に小魚の保存性を高めるための「科学」がひそんでいることがわかりました。
さて、煮詰めた小アユは一度ザルに移します。
煮汁は再びなべに戻して沸騰させ、小アユにかけていきます。
完成品はこちら!
今回お味は2種類。
左は地元の漁業協同組合さんから教えていただいたレシピでつくったもの。
まさに佃煮といったお味で、噛めば噛むほど甘みが口の中に広がっていくのを感じました。
右は学芸員さんによる味付け。
こちらは煮汁のかけ足しはせずに、身が少しふっくらしたまま盛りつけたものです。
小アユの苦みと山椒の香りが絶妙に絡み合った、煮付け風のお味でした。
どちらも美味しくいただきました

食べていくうちに、ちりめんモンスターならぬ佃煮モンスターを発見しました!
左から、ブルーギル、小アユ、エビ。
召し上がった方いわく、ブルーギルのお味は「しわい」。
「しわい」とは「かたくて筋張っている」という意味で、鳥取県や岡山県では日常で使うそうです。
「保存食を科学する」は、今後「ふなずし」と「かんぴょう」をテーマに実施される予定です。
http://www.lbm.go.jp/event/index.html#kouza
お気軽にご応募ください。








