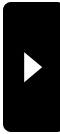NPO法人比良の里人さんを訪問しました。
こんにちは。淡海ネットワークセンターの牧野(=^・^=)です。
おうみネットサポーターの小久保さんから、平成17年から「比良の景観を愛し、その麓に暮らす”里人”として人と人のつながりを大切にしてゆきたい」という思いで、魅力探訪の散策会の開催や河川の水質調査、休耕田の利活用など様々な活動を続けておられる「NPO法人比良の里人」さんの取材報告が届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
NPO法人「比良の里人」の専務理事である石塚政孝さんを訪問した。
その事務所は、湖西線蓬莱駅を過ぎて161号線の道沿いにあった。比良山系の山の端が迫り、右手には、琵琶湖が数条の浪縞を見せ、静かにその蒼さを見せている。石塚さんもこの地で造園業を経営しながら、地域への想いもあり、永年この「比良の里人」で中核的な活動をされてきた。
先ずは、「比良の里人」について話を伺った。
1.「比良の里人」について
「比良の里人」という名前には、「比良の景観を愛し、その麓に暮らす“里人”として人と人のつながりを大切にしてゆきたい」という思いが込められている。この法人を立ち上げるにあたっては、 「滋賀県の西部に聳える比良山系は標高1000メートルを超える山々が連なり琵琶湖を臨んでいる。そしてその麓には棚田が築かれ、人々は長い歴史を自然と共に暮してきた。日本の里山を象徴するような、この景観は日本人の原風景とも言える。
しかし今この景観が大きく失われてきている。これは、第1次産業の衰退、土地の乱開発、地域コミュニティの喪失など、景観を維持してきた人々の暮らしに大きな変化が生じている為とも思っている。私たちは、営々として築かれてきたこのすばらしい景観を後世に残す為の調査や、地域での社会教育・まちづくり・環境保全の推進事業、学術・文化・芸術・スポーツの振興事業、更には地域の自立を目指した経済活動の活性化事業及び福祉の推進事業などを展開することで、比良山麓の豊かな自然と景観を活かした未来の地域を創造し、社会に寄与していきたい」と考え、この組織を設立した。
今もこの考えに沿って会員や地域の支援者とともに活動を進めているといわれる。
既に法人となって10年が経過した(平成17年4月設立)が、「比良の里人」として、頑張ったのが法人設立記念に催した「比良里山まつり」であったという。放置林の間伐、休耕田の再生、地域の魅力の再発見。市街地域にはない魅力や景観がここにはある。市街地に住む人たちとの交流を通じて、多くの人に比良の魅力を知ってほしいと思っている。このため、「花畑事業」と「放牧事業」の二つの事業を取り組んでみた。いずれも休耕田の有効利用のアイデア募集で採択された事業で、比良の自然な生態系に配慮しつつ、経済性と持続性を考えたものである。「ここは古くから石の文化が栄えたところ。景観は人が自然とのかかわりあいの中でつくっていくもの。景観も文化も所詮は人の為せる業、と
石塚さんは語る。


しし垣の調査 花畑事業の様子
2.比良の里を少し紹介
それでは、この比良の里を少し見て行きたい。
比良の里は、大津市の北部、比良山系の麓に広がり、今でも、琵琶湖との間に豊かな自然を残している。この自然とのつながりが身近に感じられる里に魅かれて、様々な職業の人が多く移住して来ている(これについては以前のレポート「かんじる比良」で伝えている→紹介記事http://ohminet.shiga-saku.net/e1159241.html)。豊かに湧く比良山系からの水が幾筋もの川をつくり、四季折々に様々な色合いを見せる木々の群れ、更には、古代から大陸からの交通の要衝、文化の中継地でもあり、比叡山の仏教文化の影響や比良三千坊と言われる寺院が散在し、歴代の天皇が祭祀したという神社など、多くの神社仏閣とともにかつての文化集積の地でもある。司馬遼太郎の「街道をゆく」の第一巻がこの比良の里周辺から書き始められているのは、偶然ではないのであろう。
また、比良八荒と呼ばれる春を告げる強い風の里でもあり、比良山系を通ってきた清らかな水が湧き出る里でもある。さらには、石の里でもある。神社の狛犬、しし垣、石灯篭、家の基礎石、車石など様々な形で使われて来た。古くは、多数存在する古墳に縦横3メートル以上の一枚岩の石板が壁や天井に使われている。古代から近世まで石の産地としてその生業として、日々の生活の中にも、様々に姿を変え、密着してきた。例えば、南小松は江州燈籠と北比良は家の基礎石等石の切り出し方にも特徴があったようで、八屋戸地区は守山石の産地で有名であったし、木戸地区も石の産地としても知られ、江戸時代初期の「毛吹草」には名産の一つに木戸石が記載されている。
コンクリートなどの普及で石材としての使われる範囲は狭まってはいるが、石の持つ温かさは、我々にとっても貴重な資源である。明治十三年(1880)にまとめられた「滋賀県物産誌」には、県内の各町村における農・工・商の軒数や特産物などが記録されているが、その中の石工に関する記述の中で特筆すべきは、旧志賀町周辺(比良の里も含む)の状況である。
この地域では「木戸村」の項に特産物として「石燈籠」「石塔」などが挙げられているなど、石工の分布密度は他地域に比べて圧倒的である。また、木戸村、北比良村(いずれも旧志賀町であり、現在は大津市)では戸数の中において「工」の占める比率も高く、明治時代初めにおける滋賀県の石工の分布状況として、この地域が特筆されるべき状況であった、と言われる。いまでも、八屋戸地区の家々の庭には、守山石と言われるこの地域で多く採れた石が庭の石畳風景として見られるし、山からの水を引く水路や昔は洗い場として使われた「かわと」、害獣対策としてのしし垣など生活のあらゆる場所で垣間見られる。
3.10年間の活動より
石塚さんの話から活動の範囲について簡単にまとめると、
事業項目として、以下の様な活動を進めてきた。
・地域の特性を生かした自立できるまちづくり/社会環境教育
・地域の自然・文化環境の保全・回復
・第1次産業の活性化(農林業の維持育成、交流)
・景観の維持・創造
・人的ネットワークを広げる
・まちづくりの政策提言
・自然との共生をテーマにした研究と提言
・芸術、文化の発展
などとの事。
さらに、10年間の様々な活動について色々とお話を聞いたが、その活動の広さはまさに「この地を好きだから」が活動の原点にある様だ。
1)比良里山まつりの開催
平成17年から平成21年まで開催し、八屋戸地区の棚田を中心に様々なイベントを実施した。
2)比良の里山の魅力探訪
日本全国で見たとき、これだけまとまった地域に大きな湖があり、山があり、多様な環境、歴史、いろんな資源、生物があるというのは恵まれすぎる位、恵まれている所であり、それを活用する気になれば何でもできそうなものを一地域で備えている。これを知ってもらうため、設立当初から開催して来た。
【例えば】
・南小松・里山歩き~石にまつわる文化的場所・里山の植物観察~
コース:八幡神社→天狗杉→弁財天→野小屋→トンボ車(増尾邸)→琵琶湖湖岸
「江戸時代から、南小松では200軒~300軒、ほとんどの家が石材加工業を営んでいたが、後継者が無く、現在ではほんのわずか数える程になった。しかし石は人々の生活に今も溶け込んでいて改めて、石材加工業の拠点であることを実感した」という。
・比良登山・アシュウスギとブナ原生林を見に行く
比良リフト乗り場→ロープウェイ乗り換え駅→比良明神→カラ岳→八雲が原湿原→金糞峠→アシウスギ原木→青ガレ
「岩ウチワや、シャクナゲ、においこぶし(良い匂いがします)の花がきれいであった。八雲が原湿原付近には、赤ハラも生育し、金糞峠の水には鉄分が染み出していた」の感想もある。
3)石積みの川復活プロジェクト


石積みの川復活プロジェクト活動の様子
平成20年より、びわ湖自然環境ネットワーク“石組の川復活プロジェクト”に参画した。比良山麓をはじめ、県内各地で小河川においてもコンクリート化が進められ、これまで使用され、保存されてきたてきた石積みの川が消滅寸前にある。びわ湖自然環境ネットが進める石積みの川を保存するとともに、壊された所は復元を目指す事業に参画した。
大道川の上流で石積みの残る場所に行き、現地を調査した後、樹木伐採・運搬班、上流・下流石組補修班の2班に分かれて作業を開始。樹木伐採班は、川沿いのスギとヒノキの大木を伐採処理、上下流の石組班は数台の重機を使って壊れた石組みの箇所を次々と補修し、中には直径1メートルもある大石もあったが、3箇所の主な破壊場所を見事に補修できた。参加者は、比良の里人、造園協会、一般・学生など計20名ほどであった。
更にこのプロジェクトは2回ほど行い、大道川の石組区間約300メートルを3回の作業で補修を完成させることが出来た。毎回20名弱の参加者があり、楽しくしかもしっかりとした補修となった。
4)雑木林と間伐整備作業
平成17年11月の2日間、雑木林整備事業を行った。NPO法人としての初仕事であったが、15名ほどの会員が集まり、雨という悪条件でもあったが、無事事故も無く終了した。
5)河川水質調査
平成18年より20年まで「身近な水環境の全国一斉調査」(みずとみどり研究会主催)比良の里人も協力して地元の水の水質調査を行った。
6)地元をあらためて知る
【小松散策】
司馬遼太郎の紀行文「街道をゆく」は旧志賀町、北小松から始まる。地元で暮らしていても、日頃なかなかゆっくりと触れることのできない、
文化・歴史・文学の痕跡をたどりながら散策した。他には、八屋戸などの散策も実施し、江戸時代からの三面石組水路は、歴史を感じさせると共に、現代の近代工法であるコンクリート三面張りに比べ、性能においても美観においても、さらに生物多様性にとってもはるかに凌いでいると再認識した。
【近江舞子内湖視察】
「近江舞子ホテル」の廃業など痛手を受ける中、何かこの内湖の湖面を、観光や地域の振興に生かせないか、ということで、水の様子、動植物の生態を水上から観察した。現在、水質はかなり汚い。内湖の水が汚いのは、もともと富栄養化しやすく、内湖に栄養を貯めることによって、琵琶湖の浜がきれいになるため。水をこれ以上きれいにすることは難しいが、これ以上汚さないようにすることはできる。また、湿地帯 水質を浄化するヨシが枯れてきている。ヨシの背が場所によって低くなってきていた。ヨシの間には、サギが住んでいたり、茎に卵を産みつけ魚の産卵場所になっている。カワセミ、カイツブリ、カメ、トンボの類もたくさんいた。内湖を景観と湖面を活かす方法としては、タライ船を櫓でこぐ・水上運動会・中秋の名月を湖上で見る会・などなどが案として出ていた。
7)休耕田の有効利用に向けて

休耕田の周辺整備
平成17年より継続 的にヤギの放牧事業(ヤギが雑草を食べ、同時に猿害対策にも)と摘んでもいい花畑事業を実施して来た。バジル苗植え付け・種まき、草抜きを実施した。チューリップが終わり、そこにひまわりがいくつか芽をだし、周りの草抜きをした。カモミールは可愛い白い花が満開になった、などの報告もある。バジルはたくさんつくる予定で種まきと苗の植え付けをおこなった。以後、いろんなハーブが花を咲かせ始め、草抜きなどを継続的に実施した。
8)生水の流れる川作り
生水(しょうず)はこの地域では、山からの恵みとして、飲み水や生活用水などに使われて来た。平成24年よりこの生水を活かすための川作りに取り組んでいる。
9)近江舞子内湖活性化と環境学習


たらい舟体験の様子
平成20年には、「内湖シンポジウム」を開催し、今年まで継続的にタライ舟に乗った環境学習を実施してきた。最近は、京都からの参加者もあり、当初の想いが広く認められつつある。「旧志賀町の良さや伝統が伝承されず風化してしまう」と危機感を覚え、地元の魅力を次代へ伝えようと、かつて水泳や魚釣りといった遊び場であり、民家の屋根葺きに使われた葦刈り場、在来魚のよい産卵場でもあった大津市南小松(旧志賀町)にある「近江舞子内湖」で「内湖に関心を持ってもらいたい」と地元の子どもたちへ向けた環境学習を実施した。
環境学習は、「内湖には普通の舟ではなくタライ舟が似合うのでは」と、タライ舟体験を通して行われる。たらい舟は「地元漁師の小屋に置かれていた地引き網を保管する大きな桶を発見し譲り受け、地元で桶などの修復を手がける人に直してもらった」と、最初に地元でタライ舟を作った。しかし、「1艘では学習するには足りない」ことから、タライ舟で知られる新潟県佐渡市まで足を運び、教わったタライ舟の設計図をもとに新たに2艘を製造した。さらに、「操作技術も教えてもらってきた」という。子どもから親まで巻き込みながら実施されるこの学習は、今も継続してる。当日、初めてタライ舟を体験した子どもたちは、法人のメンバーらに舟の漕ぎ方を手取り足取り教わりながら内湖で遊び、舟の上から水の透明度や水深を測り、自生する葦を観察するなど自然環境を学んだ。
この10年で様々な形で地域の良さをあらためて知り、比良の持つ有形無形の様々な地域資源を活かすための努力を会員を中心にしてきたと石塚さんは言う。
4.今後に向けて
最後に、石塚さんから今後の想いについて聞いた。
当面の最大の目標はこの比良の地域の織り成す石の文化を活かした地域づくりとしての「重要文化的景観」地域としての選定になること、と石塚さんは言う。比良を中心としたこの地域から産する石材を利用した多くの歴史的な構造物が今も残っている。これらは、河川や琵琶湖の水害から地域を守るための堤防、獣害を防ぐしし垣、利水のための水路、石積みの棚田、神社の彫刻物などであり、高度な技術を持った先人たちが、長い年月をかけて築き上げてきた遺産である。
しかしながら、その多くは、産業の変化、土地の開発、農業従事者の減少などに伴って荒廃しつつある。先人の残したこれらの地域資産を後世に残し、更には地域全体の活性化の中核的な活動としても当法人が進めていくべきと考えている。このため、今年は「石の文化景観調査」を北小松から和邇南浜まで実施し、あらてめてこの地域の潜在的な資産の多さを知り、12月6日には著名な先生も呼んで「重要文化的景観」認定のためのシンポジウムも開催した。これを具体的な形にするには、まだまだ解決すべき課題は多くあると思っているが、是非、「比良の里人」として活動を進めて行きたい。

百閒堤の調査

NPO10周年記念シンポジウムの様子。比良を「重要文化的景観」にと、皆さん熱心に聞いています。
(淡海ネットサポーター 小久保 弘)
おうみネットサポーターの小久保さんから、平成17年から「比良の景観を愛し、その麓に暮らす”里人”として人と人のつながりを大切にしてゆきたい」という思いで、魅力探訪の散策会の開催や河川の水質調査、休耕田の利活用など様々な活動を続けておられる「NPO法人比良の里人」さんの取材報告が届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
NPO法人「比良の里人」の専務理事である石塚政孝さんを訪問した。
その事務所は、湖西線蓬莱駅を過ぎて161号線の道沿いにあった。比良山系の山の端が迫り、右手には、琵琶湖が数条の浪縞を見せ、静かにその蒼さを見せている。石塚さんもこの地で造園業を経営しながら、地域への想いもあり、永年この「比良の里人」で中核的な活動をされてきた。
先ずは、「比良の里人」について話を伺った。
1.「比良の里人」について
「比良の里人」という名前には、「比良の景観を愛し、その麓に暮らす“里人”として人と人のつながりを大切にしてゆきたい」という思いが込められている。この法人を立ち上げるにあたっては、 「滋賀県の西部に聳える比良山系は標高1000メートルを超える山々が連なり琵琶湖を臨んでいる。そしてその麓には棚田が築かれ、人々は長い歴史を自然と共に暮してきた。日本の里山を象徴するような、この景観は日本人の原風景とも言える。
しかし今この景観が大きく失われてきている。これは、第1次産業の衰退、土地の乱開発、地域コミュニティの喪失など、景観を維持してきた人々の暮らしに大きな変化が生じている為とも思っている。私たちは、営々として築かれてきたこのすばらしい景観を後世に残す為の調査や、地域での社会教育・まちづくり・環境保全の推進事業、学術・文化・芸術・スポーツの振興事業、更には地域の自立を目指した経済活動の活性化事業及び福祉の推進事業などを展開することで、比良山麓の豊かな自然と景観を活かした未来の地域を創造し、社会に寄与していきたい」と考え、この組織を設立した。
今もこの考えに沿って会員や地域の支援者とともに活動を進めているといわれる。
既に法人となって10年が経過した(平成17年4月設立)が、「比良の里人」として、頑張ったのが法人設立記念に催した「比良里山まつり」であったという。放置林の間伐、休耕田の再生、地域の魅力の再発見。市街地域にはない魅力や景観がここにはある。市街地に住む人たちとの交流を通じて、多くの人に比良の魅力を知ってほしいと思っている。このため、「花畑事業」と「放牧事業」の二つの事業を取り組んでみた。いずれも休耕田の有効利用のアイデア募集で採択された事業で、比良の自然な生態系に配慮しつつ、経済性と持続性を考えたものである。「ここは古くから石の文化が栄えたところ。景観は人が自然とのかかわりあいの中でつくっていくもの。景観も文化も所詮は人の為せる業、と
石塚さんは語る。


しし垣の調査 花畑事業の様子
2.比良の里を少し紹介
それでは、この比良の里を少し見て行きたい。
比良の里は、大津市の北部、比良山系の麓に広がり、今でも、琵琶湖との間に豊かな自然を残している。この自然とのつながりが身近に感じられる里に魅かれて、様々な職業の人が多く移住して来ている(これについては以前のレポート「かんじる比良」で伝えている→紹介記事http://ohminet.shiga-saku.net/e1159241.html)。豊かに湧く比良山系からの水が幾筋もの川をつくり、四季折々に様々な色合いを見せる木々の群れ、更には、古代から大陸からの交通の要衝、文化の中継地でもあり、比叡山の仏教文化の影響や比良三千坊と言われる寺院が散在し、歴代の天皇が祭祀したという神社など、多くの神社仏閣とともにかつての文化集積の地でもある。司馬遼太郎の「街道をゆく」の第一巻がこの比良の里周辺から書き始められているのは、偶然ではないのであろう。
また、比良八荒と呼ばれる春を告げる強い風の里でもあり、比良山系を通ってきた清らかな水が湧き出る里でもある。さらには、石の里でもある。神社の狛犬、しし垣、石灯篭、家の基礎石、車石など様々な形で使われて来た。古くは、多数存在する古墳に縦横3メートル以上の一枚岩の石板が壁や天井に使われている。古代から近世まで石の産地としてその生業として、日々の生活の中にも、様々に姿を変え、密着してきた。例えば、南小松は江州燈籠と北比良は家の基礎石等石の切り出し方にも特徴があったようで、八屋戸地区は守山石の産地で有名であったし、木戸地区も石の産地としても知られ、江戸時代初期の「毛吹草」には名産の一つに木戸石が記載されている。
コンクリートなどの普及で石材としての使われる範囲は狭まってはいるが、石の持つ温かさは、我々にとっても貴重な資源である。明治十三年(1880)にまとめられた「滋賀県物産誌」には、県内の各町村における農・工・商の軒数や特産物などが記録されているが、その中の石工に関する記述の中で特筆すべきは、旧志賀町周辺(比良の里も含む)の状況である。
この地域では「木戸村」の項に特産物として「石燈籠」「石塔」などが挙げられているなど、石工の分布密度は他地域に比べて圧倒的である。また、木戸村、北比良村(いずれも旧志賀町であり、現在は大津市)では戸数の中において「工」の占める比率も高く、明治時代初めにおける滋賀県の石工の分布状況として、この地域が特筆されるべき状況であった、と言われる。いまでも、八屋戸地区の家々の庭には、守山石と言われるこの地域で多く採れた石が庭の石畳風景として見られるし、山からの水を引く水路や昔は洗い場として使われた「かわと」、害獣対策としてのしし垣など生活のあらゆる場所で垣間見られる。
3.10年間の活動より
石塚さんの話から活動の範囲について簡単にまとめると、
事業項目として、以下の様な活動を進めてきた。
・地域の特性を生かした自立できるまちづくり/社会環境教育
・地域の自然・文化環境の保全・回復
・第1次産業の活性化(農林業の維持育成、交流)
・景観の維持・創造
・人的ネットワークを広げる
・まちづくりの政策提言
・自然との共生をテーマにした研究と提言
・芸術、文化の発展
などとの事。
さらに、10年間の様々な活動について色々とお話を聞いたが、その活動の広さはまさに「この地を好きだから」が活動の原点にある様だ。
1)比良里山まつりの開催
平成17年から平成21年まで開催し、八屋戸地区の棚田を中心に様々なイベントを実施した。
2)比良の里山の魅力探訪
日本全国で見たとき、これだけまとまった地域に大きな湖があり、山があり、多様な環境、歴史、いろんな資源、生物があるというのは恵まれすぎる位、恵まれている所であり、それを活用する気になれば何でもできそうなものを一地域で備えている。これを知ってもらうため、設立当初から開催して来た。
【例えば】
・南小松・里山歩き~石にまつわる文化的場所・里山の植物観察~
コース:八幡神社→天狗杉→弁財天→野小屋→トンボ車(増尾邸)→琵琶湖湖岸
「江戸時代から、南小松では200軒~300軒、ほとんどの家が石材加工業を営んでいたが、後継者が無く、現在ではほんのわずか数える程になった。しかし石は人々の生活に今も溶け込んでいて改めて、石材加工業の拠点であることを実感した」という。
・比良登山・アシュウスギとブナ原生林を見に行く
比良リフト乗り場→ロープウェイ乗り換え駅→比良明神→カラ岳→八雲が原湿原→金糞峠→アシウスギ原木→青ガレ
「岩ウチワや、シャクナゲ、においこぶし(良い匂いがします)の花がきれいであった。八雲が原湿原付近には、赤ハラも生育し、金糞峠の水には鉄分が染み出していた」の感想もある。
3)石積みの川復活プロジェクト


石積みの川復活プロジェクト活動の様子
平成20年より、びわ湖自然環境ネットワーク“石組の川復活プロジェクト”に参画した。比良山麓をはじめ、県内各地で小河川においてもコンクリート化が進められ、これまで使用され、保存されてきたてきた石積みの川が消滅寸前にある。びわ湖自然環境ネットが進める石積みの川を保存するとともに、壊された所は復元を目指す事業に参画した。
大道川の上流で石積みの残る場所に行き、現地を調査した後、樹木伐採・運搬班、上流・下流石組補修班の2班に分かれて作業を開始。樹木伐採班は、川沿いのスギとヒノキの大木を伐採処理、上下流の石組班は数台の重機を使って壊れた石組みの箇所を次々と補修し、中には直径1メートルもある大石もあったが、3箇所の主な破壊場所を見事に補修できた。参加者は、比良の里人、造園協会、一般・学生など計20名ほどであった。
更にこのプロジェクトは2回ほど行い、大道川の石組区間約300メートルを3回の作業で補修を完成させることが出来た。毎回20名弱の参加者があり、楽しくしかもしっかりとした補修となった。
4)雑木林と間伐整備作業
平成17年11月の2日間、雑木林整備事業を行った。NPO法人としての初仕事であったが、15名ほどの会員が集まり、雨という悪条件でもあったが、無事事故も無く終了した。
5)河川水質調査
平成18年より20年まで「身近な水環境の全国一斉調査」(みずとみどり研究会主催)比良の里人も協力して地元の水の水質調査を行った。
6)地元をあらためて知る
【小松散策】
司馬遼太郎の紀行文「街道をゆく」は旧志賀町、北小松から始まる。地元で暮らしていても、日頃なかなかゆっくりと触れることのできない、
文化・歴史・文学の痕跡をたどりながら散策した。他には、八屋戸などの散策も実施し、江戸時代からの三面石組水路は、歴史を感じさせると共に、現代の近代工法であるコンクリート三面張りに比べ、性能においても美観においても、さらに生物多様性にとってもはるかに凌いでいると再認識した。
【近江舞子内湖視察】
「近江舞子ホテル」の廃業など痛手を受ける中、何かこの内湖の湖面を、観光や地域の振興に生かせないか、ということで、水の様子、動植物の生態を水上から観察した。現在、水質はかなり汚い。内湖の水が汚いのは、もともと富栄養化しやすく、内湖に栄養を貯めることによって、琵琶湖の浜がきれいになるため。水をこれ以上きれいにすることは難しいが、これ以上汚さないようにすることはできる。また、湿地帯 水質を浄化するヨシが枯れてきている。ヨシの背が場所によって低くなってきていた。ヨシの間には、サギが住んでいたり、茎に卵を産みつけ魚の産卵場所になっている。カワセミ、カイツブリ、カメ、トンボの類もたくさんいた。内湖を景観と湖面を活かす方法としては、タライ船を櫓でこぐ・水上運動会・中秋の名月を湖上で見る会・などなどが案として出ていた。
7)休耕田の有効利用に向けて

休耕田の周辺整備
平成17年より継続 的にヤギの放牧事業(ヤギが雑草を食べ、同時に猿害対策にも)と摘んでもいい花畑事業を実施して来た。バジル苗植え付け・種まき、草抜きを実施した。チューリップが終わり、そこにひまわりがいくつか芽をだし、周りの草抜きをした。カモミールは可愛い白い花が満開になった、などの報告もある。バジルはたくさんつくる予定で種まきと苗の植え付けをおこなった。以後、いろんなハーブが花を咲かせ始め、草抜きなどを継続的に実施した。
8)生水の流れる川作り
生水(しょうず)はこの地域では、山からの恵みとして、飲み水や生活用水などに使われて来た。平成24年よりこの生水を活かすための川作りに取り組んでいる。
9)近江舞子内湖活性化と環境学習


たらい舟体験の様子
平成20年には、「内湖シンポジウム」を開催し、今年まで継続的にタライ舟に乗った環境学習を実施してきた。最近は、京都からの参加者もあり、当初の想いが広く認められつつある。「旧志賀町の良さや伝統が伝承されず風化してしまう」と危機感を覚え、地元の魅力を次代へ伝えようと、かつて水泳や魚釣りといった遊び場であり、民家の屋根葺きに使われた葦刈り場、在来魚のよい産卵場でもあった大津市南小松(旧志賀町)にある「近江舞子内湖」で「内湖に関心を持ってもらいたい」と地元の子どもたちへ向けた環境学習を実施した。
環境学習は、「内湖には普通の舟ではなくタライ舟が似合うのでは」と、タライ舟体験を通して行われる。たらい舟は「地元漁師の小屋に置かれていた地引き網を保管する大きな桶を発見し譲り受け、地元で桶などの修復を手がける人に直してもらった」と、最初に地元でタライ舟を作った。しかし、「1艘では学習するには足りない」ことから、タライ舟で知られる新潟県佐渡市まで足を運び、教わったタライ舟の設計図をもとに新たに2艘を製造した。さらに、「操作技術も教えてもらってきた」という。子どもから親まで巻き込みながら実施されるこの学習は、今も継続してる。当日、初めてタライ舟を体験した子どもたちは、法人のメンバーらに舟の漕ぎ方を手取り足取り教わりながら内湖で遊び、舟の上から水の透明度や水深を測り、自生する葦を観察するなど自然環境を学んだ。
この10年で様々な形で地域の良さをあらためて知り、比良の持つ有形無形の様々な地域資源を活かすための努力を会員を中心にしてきたと石塚さんは言う。
4.今後に向けて
最後に、石塚さんから今後の想いについて聞いた。
当面の最大の目標はこの比良の地域の織り成す石の文化を活かした地域づくりとしての「重要文化的景観」地域としての選定になること、と石塚さんは言う。比良を中心としたこの地域から産する石材を利用した多くの歴史的な構造物が今も残っている。これらは、河川や琵琶湖の水害から地域を守るための堤防、獣害を防ぐしし垣、利水のための水路、石積みの棚田、神社の彫刻物などであり、高度な技術を持った先人たちが、長い年月をかけて築き上げてきた遺産である。
しかしながら、その多くは、産業の変化、土地の開発、農業従事者の減少などに伴って荒廃しつつある。先人の残したこれらの地域資産を後世に残し、更には地域全体の活性化の中核的な活動としても当法人が進めていくべきと考えている。このため、今年は「石の文化景観調査」を北小松から和邇南浜まで実施し、あらてめてこの地域の潜在的な資産の多さを知り、12月6日には著名な先生も呼んで「重要文化的景観」認定のためのシンポジウムも開催した。これを具体的な形にするには、まだまだ解決すべき課題は多くあると思っているが、是非、「比良の里人」として活動を進めて行きたい。

百閒堤の調査

NPO10周年記念シンポジウムの様子。比良を「重要文化的景観」にと、皆さん熱心に聞いています。
(淡海ネットサポーター 小久保 弘)
Posted by
BIWAちゃん
at
13:51
│
淡海ネットワークセンター
NPO法人琵琶湖ライフケアシステムさんを訪問しました。
こんにちは。淡海ネットワークセンターの牧野(=^・^=)です。
おうみネットサポーターの小久保さんから、大津市の琵琶湖西岸にあるびわ湖ローズタウンで13年前、主婦を中心とした20数人で、高齢者や障がい者への配食サービスから始められ、デイケアハウス、コミュニティレストランなどと活動を広げてこられた「NPO法人琵琶湖ライフケアシステム」さんの取材報告が届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
大津市の琵琶湖西岸のなだらかな丘陵を住宅団地として開発されたびわ湖ローズタウン。分譲開始から40年ほどを経て、今や4500戸にのぼるベッドタウンではあるが、現在は高齢化が進み以前のような元気な街が消えつつあるようだ。

ここに住む主婦ら女性たちが自分たちの先行きを考えながら、「一人でやるより仲間が集まって」介護支援のグループを、とNPO(民間非営利団体)を13年前に立ち上げた。主婦を主にして20数人。なにができるか? 自分たちにできることを活かして、まず高齢者や障がい者への配食サービスを計画し、近くの民宿の調理場を借りて週2回の弁当配食を始めた。その後、ローズタウン内で閉店していたレストランを借りて、配食に次いで喫茶室へ間口を広げた。カウンターと机3つで最大15人が入れて、週1回開いたミニ喫茶に近所のお年寄りたちが次第に集まりだし、午後からの半日を、おしゃべりしたり、ゲームをしたり、くつろげる空間となってきた。
今回は、このNPO法人琵琶湖ライフケアシステムの理事長である田中さんからこれまでの活動や現在の状況、これからのことなどについて色々とお聞きした。
ここは、湖西線の小野駅の直ぐ横にあり、琵琶湖がそのゆったりとした姿を紺青の色と透き通る青い空の下に見せている。近くには、小野妹子などの小野一族の神社や古墳がある緑と湖と歴史のある街である。そんな中で、元気な女性の方たちが頑張っている場所でもある。
1、琵琶湖ライフケアシステムとは、
このNPOは、田中さんとその仲間の想いがこもっている団体のようだ。「好きな食事作りをみんなでやって、高齢で食事作りが難しくなった人へお弁当を届ける」という想いである。弁当配食を地域の人たちにしたいとの想いの強さからこれまで2回ほど場所を変えてきた。いずれも、元民宿の家を借りてやって来たが、今の場所の立地のよさと高齢者が増えつつあったこの地域での配食や「おしゃべりの出来る場所」などへの要望の高さに期待し、10年ほど前にここに移った。駅の直ぐ横でもあり、店を開いてから徐々にクチコミで人が集まる様になり、様々なサービスを追加しながら、地域の人が集まる現在の姿になっていった、と言う。

まず、田中さんからその概要をお聞きした。
「本法人は、大津市のJR湖西線小野駅南側に喫茶・食堂を開いて、地域の人たちが気軽に交流する「居場所」を提供しています。1階の食堂・喫茶に加え、2階にフリールームを備え、趣味の教室のほか、目前の湖面に群がる野鳥観察が楽しめます。大規模な住宅街の一角に、だれでも、ゆっくりくつろげる地域福祉の拠点となっています。
主な事業は、美湖ちゃん弁当の提供、サークル活動、日常支援、町なかデイハウス美湖、高齢者世帯向け配食に昼食・夕食弁当の配達など地域のコミュニティ作りを主点に様々な活動をしています。
美湖のサークルは、パソコン・手編み毛糸・創作折り紙・健康麻雀・小物作り・絵手紙・ウクレレと現在7講座あります。各々ボランティアの先生の指導のもと、皆さん和気藹々と和やかに活動しています。


日常支援では、植え木の枝を1本1本仕分けして剪定したり、高齢に伴い、他の人に頼みたい日常の小さな仕事を肩代わりして喜んでもらっています。町なかデイハウス美湖は、ローズタウンの中でデイサービスをしています。日々のご利用者の明るい談笑、お互いを思いやる声掛けや心配りに感動し、年を重ねていく事の素晴らしさを学んでいます。今日も楽しかった。また、逢いましょうね、と挨拶をかわされる皆様の笑顔にささえられて来た。このつながりが大きな輪になって、地域に広がっていきますようにと願っています」。
2.現在の主な活動
多くの活動は「コミュニティレストラン ボナペティ美湖」で行われている。食堂・喫茶は月~金曜、午前11時30分から午後3時まで営業だが、食堂や物品販売コーナーやフリールームなどを備えた多機能な拠点として認知度は高い。特に、日替わり定食650円の自慢は、新鮮な地元産の米や野菜を使っていること。近所の農家から直接仕入れるほか、会員からの差し入れなど旬の食材に事欠かない。NPOの会員約60人を中心にボランティア25人が交代で仕事を分担し運営しながら、フリールームの活用も行い、手芸、パソコン、器楽演奏、ゲーム遊技などの教室を開いている。
田中さんは「高齢者だけではなく障がい者や熟年世代、若い世代まで利用されることで、地域の人たちにとってなじみの居場所として定着し、お互いになじみあえる機会を提供していきたいです」と語っている。
1)愛称:美湖ちゃん弁当
高齢者・障がい者の方には心のこもった手作り弁当であり、利用者の方との語らいはスタッフにとっても心の栄養として以下の想いで提供している。
・利用者の栄養バランスを考えた美湖ちゃん弁当
・安心・安全地元の食材を使った美湖ちゃん弁当
・食べ飽きない家庭的な味付けの美湖ちゃん弁当
2)愛称:美湖ちゃん支援隊
顔見知りのスタッフ(会員)が伺って、以下の様な日常生活支援をする。
庭木剪定、下水掃除、庭関係(草取り・片づけなど)、換気扇・風呂・ガラス拭きなど、室内掃除・かたづけ、買い物等
3)愛称:ボナペティ美湖
誰でもいつでも気軽に利用できるコミュニティレストラン。2階のカウンターからの眺めは抜群であり、180度の眺望が開けている。
冬の水鳥2000羽(を超える日もあります)の集結は圧巻、バードウォッチングできる(小白鳥・カモ・キジ・ケリ等)
ボナペティ美湖の名前の由来は、「ボナペティ」はフランス語で「さあ、召し上がれ」という意味。
「美湖(みこ)」は、いつまでも美しい湖であってほしいという願望をこめてつけた。
4)ミニコンサートと歌声喫茶
いろいろなジャンルの演奏家をお招きして、普段触れる機会のない楽器や美しい歌声に触れる機会を提供する場となっている。 生オケで楽しく皆で楽しく過ごすイベントもある。さらに、月1回「歌声喫茶」を開催している。これは、ボランティアで、歌唱力のある歌好きなNPOの会員さんが指導され、昔男声合唱団で活躍した人など、男性も5、6人来られて楽しんでいる。

5)ミニ講座
身近な場所で気軽に聞ける医療の話・防犯の話・歴史の話などの講座。見知らぬ者同士でも趣味を通して知り合い、交流を深める場を提供している。特に小野や和邇周辺の古代歴史は、中々に面白くこの地域の素晴らしさを教えてもらえる。
6)次のようなサークル活動も行っている。
これは、ボランティアの先生が主となる活動となっている。
・パソコン教室
仲間との楽しい交信、写真の保管、世界中の隅々のニュースや画像が一瞬に手に入ります。ご自分が習いたいところだけ教えてもらえます
・健康麻雀
・手編み毛糸教室
・折り紙教室
・ウクレレ
・絵手紙
・小物づくり
・歌声喫茶
歌声喫茶以外の活動では、男性の参加が少なくさらに多くの男性の参加を企画したい。
7)各種教室
外部の先生に指導してもらえる。
・書道教室
・民謡三味線
・俳句
・ミニハープ教室





8)町なかデイハウス美湖
3年ほど前にNPO法人琵琶湖ライフケアシステムが初めて介護事業を開始した。住宅地の中の民家改修型で小規模だが、庭がとてもきれいで落ち着いた雰囲気の中10人ほどが会話やリハビリを楽しんでいる。
場所;大津市朝日1-17-4
電話;077-594-0710
9)介護職員初任者研修
この研修は、高齢化する住民のサービスのために必要なヘルパー育成を目指したものであり、多くの人に成ってもらいたいとの想いがある。
少し具体的に説明をすると、介護職員初任者研修課程は、「介護」に関する講座で、133時間(講義と実習)出席し修了試験に合格すると修了証を取得できます。「介護」は、高齢者・障がい者が自分らしい生活を維持し、住み慣れた地域でいつまでも生活ができるように支援する。
長寿社会を迎える中、老化や、障がいにより、身体の機能の低下や、病気、認知など精神的疾患にも対応できる学習の入り口課程。介護実習施設で実技を学び、講義の内容がより一層理解でき現場の介護に役に立つ講座となっている。
今後は、介護分野に理解のある人、技術を持っている人などが必要とされ、専門性を持った質の高い介護を行うため、 特に、団塊世代の方が地域の一員となって活動をするのに役立つ。
昨年度まで開催された研修会では,10人弱の方が受けられて、地元で活動をしている。
10)美湖ニュースの発行
パソコンの苦手な高齢者が多い中、ボナペティ美湖を中心とした活動や関係ある情報を月1回、小冊子として3500部ほどを会員さんを中心に送付して、地域コミュニティとしての情報提供を8年ほど継続している。健康に関する内容や会員の俳句などその内容は、出歩きが難しい人への情報提供としても参考になっている。
3.これからのこと
田中さんは、
「3年前に街中に作ったデイサービスが好評でもあり、また自身の想いを更に深めるためにも、本格的な介護施設の運営を行うことを具体的に考えていきたい。また、国の動きもあるが、個人的にも「介護予防」のサービスを本格的に行っていきたい。更には、この「コミュニティレストラン ボナペティ美湖」をベースに地域コミュニティ作りを一歩進めて、介護サービスを加えた総合的な地域支援を進めていきたいし、多くの若い人が仲間として頑張って行ってほしい」と想いを語ってくれた。
ボナペティ美湖を訪問して、田中さんから色々と話を聞いていると、この地域でのコミュニティ創りに日々頑張っているのが、よく分かる。このような役目を担うのが公民館や市民センターなのだろうが、多くは単なる場所貸し的なレベルに留まっている。元気な高齢者や介護を必要とする高齢者を中心に、老若男女を問わず集まり、様々な講座やイベントによる「居場所作り」をなお一層進めてもらいたい。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
おうみネットサポーターの小久保さんから、大津市の琵琶湖西岸にあるびわ湖ローズタウンで13年前、主婦を中心とした20数人で、高齢者や障がい者への配食サービスから始められ、デイケアハウス、コミュニティレストランなどと活動を広げてこられた「NPO法人琵琶湖ライフケアシステム」さんの取材報告が届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
大津市の琵琶湖西岸のなだらかな丘陵を住宅団地として開発されたびわ湖ローズタウン。分譲開始から40年ほどを経て、今や4500戸にのぼるベッドタウンではあるが、現在は高齢化が進み以前のような元気な街が消えつつあるようだ。

ここに住む主婦ら女性たちが自分たちの先行きを考えながら、「一人でやるより仲間が集まって」介護支援のグループを、とNPO(民間非営利団体)を13年前に立ち上げた。主婦を主にして20数人。なにができるか? 自分たちにできることを活かして、まず高齢者や障がい者への配食サービスを計画し、近くの民宿の調理場を借りて週2回の弁当配食を始めた。その後、ローズタウン内で閉店していたレストランを借りて、配食に次いで喫茶室へ間口を広げた。カウンターと机3つで最大15人が入れて、週1回開いたミニ喫茶に近所のお年寄りたちが次第に集まりだし、午後からの半日を、おしゃべりしたり、ゲームをしたり、くつろげる空間となってきた。
今回は、このNPO法人琵琶湖ライフケアシステムの理事長である田中さんからこれまでの活動や現在の状況、これからのことなどについて色々とお聞きした。
ここは、湖西線の小野駅の直ぐ横にあり、琵琶湖がそのゆったりとした姿を紺青の色と透き通る青い空の下に見せている。近くには、小野妹子などの小野一族の神社や古墳がある緑と湖と歴史のある街である。そんな中で、元気な女性の方たちが頑張っている場所でもある。
1、琵琶湖ライフケアシステムとは、
このNPOは、田中さんとその仲間の想いがこもっている団体のようだ。「好きな食事作りをみんなでやって、高齢で食事作りが難しくなった人へお弁当を届ける」という想いである。弁当配食を地域の人たちにしたいとの想いの強さからこれまで2回ほど場所を変えてきた。いずれも、元民宿の家を借りてやって来たが、今の場所の立地のよさと高齢者が増えつつあったこの地域での配食や「おしゃべりの出来る場所」などへの要望の高さに期待し、10年ほど前にここに移った。駅の直ぐ横でもあり、店を開いてから徐々にクチコミで人が集まる様になり、様々なサービスを追加しながら、地域の人が集まる現在の姿になっていった、と言う。

まず、田中さんからその概要をお聞きした。
「本法人は、大津市のJR湖西線小野駅南側に喫茶・食堂を開いて、地域の人たちが気軽に交流する「居場所」を提供しています。1階の食堂・喫茶に加え、2階にフリールームを備え、趣味の教室のほか、目前の湖面に群がる野鳥観察が楽しめます。大規模な住宅街の一角に、だれでも、ゆっくりくつろげる地域福祉の拠点となっています。
主な事業は、美湖ちゃん弁当の提供、サークル活動、日常支援、町なかデイハウス美湖、高齢者世帯向け配食に昼食・夕食弁当の配達など地域のコミュニティ作りを主点に様々な活動をしています。
美湖のサークルは、パソコン・手編み毛糸・創作折り紙・健康麻雀・小物作り・絵手紙・ウクレレと現在7講座あります。各々ボランティアの先生の指導のもと、皆さん和気藹々と和やかに活動しています。


日常支援では、植え木の枝を1本1本仕分けして剪定したり、高齢に伴い、他の人に頼みたい日常の小さな仕事を肩代わりして喜んでもらっています。町なかデイハウス美湖は、ローズタウンの中でデイサービスをしています。日々のご利用者の明るい談笑、お互いを思いやる声掛けや心配りに感動し、年を重ねていく事の素晴らしさを学んでいます。今日も楽しかった。また、逢いましょうね、と挨拶をかわされる皆様の笑顔にささえられて来た。このつながりが大きな輪になって、地域に広がっていきますようにと願っています」。
2.現在の主な活動
多くの活動は「コミュニティレストラン ボナペティ美湖」で行われている。食堂・喫茶は月~金曜、午前11時30分から午後3時まで営業だが、食堂や物品販売コーナーやフリールームなどを備えた多機能な拠点として認知度は高い。特に、日替わり定食650円の自慢は、新鮮な地元産の米や野菜を使っていること。近所の農家から直接仕入れるほか、会員からの差し入れなど旬の食材に事欠かない。NPOの会員約60人を中心にボランティア25人が交代で仕事を分担し運営しながら、フリールームの活用も行い、手芸、パソコン、器楽演奏、ゲーム遊技などの教室を開いている。
田中さんは「高齢者だけではなく障がい者や熟年世代、若い世代まで利用されることで、地域の人たちにとってなじみの居場所として定着し、お互いになじみあえる機会を提供していきたいです」と語っている。
1)愛称:美湖ちゃん弁当
高齢者・障がい者の方には心のこもった手作り弁当であり、利用者の方との語らいはスタッフにとっても心の栄養として以下の想いで提供している。
・利用者の栄養バランスを考えた美湖ちゃん弁当
・安心・安全地元の食材を使った美湖ちゃん弁当
・食べ飽きない家庭的な味付けの美湖ちゃん弁当
2)愛称:美湖ちゃん支援隊
顔見知りのスタッフ(会員)が伺って、以下の様な日常生活支援をする。
庭木剪定、下水掃除、庭関係(草取り・片づけなど)、換気扇・風呂・ガラス拭きなど、室内掃除・かたづけ、買い物等
3)愛称:ボナペティ美湖
誰でもいつでも気軽に利用できるコミュニティレストラン。2階のカウンターからの眺めは抜群であり、180度の眺望が開けている。
冬の水鳥2000羽(を超える日もあります)の集結は圧巻、バードウォッチングできる(小白鳥・カモ・キジ・ケリ等)
ボナペティ美湖の名前の由来は、「ボナペティ」はフランス語で「さあ、召し上がれ」という意味。
「美湖(みこ)」は、いつまでも美しい湖であってほしいという願望をこめてつけた。
4)ミニコンサートと歌声喫茶
いろいろなジャンルの演奏家をお招きして、普段触れる機会のない楽器や美しい歌声に触れる機会を提供する場となっている。 生オケで楽しく皆で楽しく過ごすイベントもある。さらに、月1回「歌声喫茶」を開催している。これは、ボランティアで、歌唱力のある歌好きなNPOの会員さんが指導され、昔男声合唱団で活躍した人など、男性も5、6人来られて楽しんでいる。

5)ミニ講座
身近な場所で気軽に聞ける医療の話・防犯の話・歴史の話などの講座。見知らぬ者同士でも趣味を通して知り合い、交流を深める場を提供している。特に小野や和邇周辺の古代歴史は、中々に面白くこの地域の素晴らしさを教えてもらえる。
6)次のようなサークル活動も行っている。
これは、ボランティアの先生が主となる活動となっている。
・パソコン教室
仲間との楽しい交信、写真の保管、世界中の隅々のニュースや画像が一瞬に手に入ります。ご自分が習いたいところだけ教えてもらえます
・健康麻雀
・手編み毛糸教室
・折り紙教室
・ウクレレ
・絵手紙
・小物づくり
・歌声喫茶
歌声喫茶以外の活動では、男性の参加が少なくさらに多くの男性の参加を企画したい。
7)各種教室
外部の先生に指導してもらえる。
・書道教室
・民謡三味線
・俳句
・ミニハープ教室





8)町なかデイハウス美湖
3年ほど前にNPO法人琵琶湖ライフケアシステムが初めて介護事業を開始した。住宅地の中の民家改修型で小規模だが、庭がとてもきれいで落ち着いた雰囲気の中10人ほどが会話やリハビリを楽しんでいる。
場所;大津市朝日1-17-4
電話;077-594-0710
9)介護職員初任者研修
この研修は、高齢化する住民のサービスのために必要なヘルパー育成を目指したものであり、多くの人に成ってもらいたいとの想いがある。
少し具体的に説明をすると、介護職員初任者研修課程は、「介護」に関する講座で、133時間(講義と実習)出席し修了試験に合格すると修了証を取得できます。「介護」は、高齢者・障がい者が自分らしい生活を維持し、住み慣れた地域でいつまでも生活ができるように支援する。
長寿社会を迎える中、老化や、障がいにより、身体の機能の低下や、病気、認知など精神的疾患にも対応できる学習の入り口課程。介護実習施設で実技を学び、講義の内容がより一層理解でき現場の介護に役に立つ講座となっている。
今後は、介護分野に理解のある人、技術を持っている人などが必要とされ、専門性を持った質の高い介護を行うため、 特に、団塊世代の方が地域の一員となって活動をするのに役立つ。
昨年度まで開催された研修会では,10人弱の方が受けられて、地元で活動をしている。
10)美湖ニュースの発行
パソコンの苦手な高齢者が多い中、ボナペティ美湖を中心とした活動や関係ある情報を月1回、小冊子として3500部ほどを会員さんを中心に送付して、地域コミュニティとしての情報提供を8年ほど継続している。健康に関する内容や会員の俳句などその内容は、出歩きが難しい人への情報提供としても参考になっている。
3.これからのこと
田中さんは、
「3年前に街中に作ったデイサービスが好評でもあり、また自身の想いを更に深めるためにも、本格的な介護施設の運営を行うことを具体的に考えていきたい。また、国の動きもあるが、個人的にも「介護予防」のサービスを本格的に行っていきたい。更には、この「コミュニティレストラン ボナペティ美湖」をベースに地域コミュニティ作りを一歩進めて、介護サービスを加えた総合的な地域支援を進めていきたいし、多くの若い人が仲間として頑張って行ってほしい」と想いを語ってくれた。
ボナペティ美湖を訪問して、田中さんから色々と話を聞いていると、この地域でのコミュニティ創りに日々頑張っているのが、よく分かる。このような役目を担うのが公民館や市民センターなのだろうが、多くは単なる場所貸し的なレベルに留まっている。元気な高齢者や介護を必要とする高齢者を中心に、老若男女を問わず集まり、様々な講座やイベントによる「居場所作り」をなお一層進めてもらいたい。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
Posted by
BIWAちゃん
at
16:48
│
淡海ネットワークセンター
「志賀郷土料理の会」を訪問しました。
こんにちは。スタッフの牧野(=^・^=)です。
おうみネットサポーターの小久保さんから、志賀町で地域の郷土食を受け継いでいき、普及活動を通じて地域のつながりを深めるようと、活動されている「志賀郷土料理の会」さんの取材報告の届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
先日、志賀郷土料理の会を訪問した。
皆さん女性ばかりであるが、料理への熱意が横で見ているだけの私にも伝わってくる。中々に熱い会である。
先ずは、指導されている原さんからこの活動の動機や活動内容をお聞きした。
■活動を開始した動機
志賀郷土料理研究会(代表 原康子)は平成13年5月に志賀町(当時)社会福祉協議会のボランティアサークルの一つとして発足した。その後、志賀郷土料理研究会が設立母体となって、平成16年4月に志賀郷土料理の会が組織され、これまで一体となって活動してきた。その動機は、
・昔から食べつないできた地域の郷土食が若い世代に受け継がれていないことに危機感を抱いたこと
・地域の郷土食のなかに培われてきた長年の知恵とわざをお年寄りから学びたい
・郷土食を通して地域のつながりを深め、支え合う社会をつくりたい
とのこと。
参加されていた方々からのお話でも「地域のお年寄りから郷土食を学びたかった」、「子供の頃の味を再び味わいたかった」など14年間経てもその動機と想いは生きているようでした。
■その活動について
このような動機から志賀郷土料理研究会/志賀郷土料理は発足したが、具体的には次のような活動してきた。
・この地域に受け継がれてきた郷土食をお年寄りから学ぶこと
・郷土食の魅力を地域の若い世代に伝えること
・郷土食を広めることによって食生活の改善を図ること
・郷土食の普及活動を通じて、地域のつながりを深めること
郷土食には手間のかかった深い味わいがあり、幾世代もの人々の知恵がつながって作りあげてきたもの。志賀郷土料理の会では、このような魅力ある伝統的な郷土食を地域のお年寄りから直に学び、これをすべてレシピや写真として記録している。
郷土食は栄養的にもバランスがよく健康的な料理が多いので、志賀郷土料理の会では、郷土食を毎日の食生活に取り入れることを進める普及活動にも積極的に取り組んでいる。このような活動を通じて、食生活の改善を図り、地域のつながりを深めることに貢献することも会の大切な活動と思っている。
現在の参加者は地元以外からの人も多く、郷土食を通じた人のつながり、食文化の継承など、都市化し人のつながりが弱くなる最近の傾向とは別に、地域の重要なコミュニティとなっていると感じた。

■何故、14年間も続いているのか
会の発足当初は、80歳代のお年寄りから子供の頃から日常食べてきた料理を丁寧に聞き取り、実際に作ってもらい食べる勉強を2年間続けてきた。その間、調理法を記録し、レシピ作りも重ねて、出来上がったレシピをもとに、当初は、地域で料理教室を何回も開き、その活動を広めてもきた。郷土食は美味しいという50歳~80歳代がいる一方、若い世代、とくに子ども達は食べたことがないために、「美味しくない」、「興味もない」という人が多いという現実にもつきあたった。このような経験を重ねて、郷土食は食材の工夫と調理次第で美味しく食べられることを知ってもらうことも会の大切な役目と分かってきた。
豊かな時代がいつまでも続くか不安がある中、地元で収穫される昔ながらの野菜などを工夫して食べることを伝える必要があり、地元の野菜などを使うことによって、地域の農家も農作物を作ってくれるようにもなると思っている。
参加者のお話でも、若い人たちとの味の違いに悩んだり、地元の食材が手に入らなくなる心配などが出ていた。特に、湖魚は捕れる量も減り、価格が高騰してきていることへの不安は大きい様だ。しかし、自分たちで作った野菜や港まで行って仕入れた魚だけで料理をすることへのこだわりが14年間続いたのは凄い事であり、それが会をここまで支えてきたのではないか、と思う。
また、この会の活動を広く知ってもらうため、2006年に「食べつなぐ ふるさとの食事ー滋賀県志賀町」という本を出版した。その内容を少し紹介すると、
◆春は、「もろこ焼き」「なまり節と竹の子、ふき煮」「イタドリの煮付け」など。
◆夏は、「ハス魚田」「小あゆの山椒煮」「にしんなす」「なかよし豆」など。
◆秋は、「あめのうおご飯」「干しズイキとえび煮」「山菜おこわ」など。
◆冬は、「氷魚のゆず酢」「鴨とクレソン鍋」「いさざ煮」など。
夫々の料理にはレシピがあり、写真とともに美味しさを目で味わえるようです。
さらに、「おせち料理」「きびがら染め赤飯」「はや寿司」ほか色鮮やかな歳時料理の紹介もある。

「ハス魚田」

上記の鮒寿司は会員のご主人が多くの人に食してもらおうと8年かけて創っている「志賀版鮒寿司」。あっさり風で評判は上々
■現在の活動をお聞きした。
今は、30人ほどの人が参加して、月1回の割合で、郷土料理を勉強している。例えば、訪問したこの日の料理は、「野洲・守山の伝統料理のおあえ団子」、「ごはんピザ」、「新たまねぎと鯖水煮」、「ふきご飯」をその日の担当メンバーが中心となりそのレシピに沿って、作っていた。いずれも季節感があり、美味しかった。会の参加者も地元生まれで育ちの方は7、8名であり、東京、京都や熊本、奈良などから移り住んだ人、隣りの高島市からなど多方面の人で構成されており、様々な味感覚で豊かな食作りをされているようである。
参加者の言葉から様々な思いを聞いたが、共通した点は、自然豊かな志賀の味を家族に食べて欲しいと言う強い思いである。
「姑として、嫁にこの地域の味を伝えたかった」、
「母親として子供たちに地域で取れる食材で手造りの料理を食べさせたい」、
「琵琶湖の魚介類を食材にした料理をもっと知りたい」、
「地元のお年寄りからこの地域の食材を使った料理を教えてもらうのが楽しい」、
「季節に応じた食材を使って四季を感じるのが楽しみ」、
「外から来た人間にとって豊富な湖魚の料理は参考になる」、
「冷凍食品や食材になれた若い人に季節ごとの生の食材の良さを知って欲しい」、
「メニューを決める時、レシピもないのに幼い頃食べた記憶だけから料理を再現できた時、”化石を掘り起こした気分”になる」、
「昔、おばあさんが食べさせてくれた懐かしい味が今の若い世代に食べつながれることを信じて活動をしている」
など等。
さらに、会の代表の東さんや他の中核の人たちが強調したのは、「野菜類は自分で作ったものをその日に持ち寄り、魚介類はその日に捕れたものを使う事が大事であり、これは会の発足当時から守るべきこととして大切にしている」との言葉であった。また、今の子供たちや若い人に郷土の料理をそのままでは、味わってくれないので、現代風にアレンジしていく事も大事とのこと。


担当ごとに料理つくり、忙しそう! 「ごはんピザ」

つくったご飯を囲んでの食事会。献立も色々あって、美味しそう!
■これから更に活動を続けるためには
今まで会を支えてきたメンバーも年齢が高くなり、これからも活力ある活動を維持してゆくためにも、若い人たちの参加を進めて行きたい。また、特に湖魚は捕れる量の減少とともに価格も高くなって来ていて中々入手が難しくなっている。野菜類も含め、食材の確保が重要になりつつある。会は、主婦たちを中心とするボランティア活動であり、資金的な基盤も弱く、どのようにして活動を維持してゆくか資金面でも課題があるようだ。
しかし、これらの課題に対応しながら、若い世代や子供たちが郷土食に親しみ、食生活の質を向上させるための取り組みを更に広く知ってもらいたい。そのためには、他の地域の同じ想いの活動グループとの連携や様々なメディアを活用した情報発信を考えて行きたい、との熱い想いも語られた。
先ほどの本を出版した時は、新聞社や様々なメディアからの取材もあり、当初は各地のイベントに参加したりして、郷土料理を広く認知してもらえたが、最近は、その活動も少なくなり、毎月開催の料理教室が中心となっているようである。
ただ会員規模は今の30名ほどがよいが、自分たちの活動をもう少し広く認知してもらいたいと言う思いもあり、その両立をどうとって行くのか悩んでいるようだった。

昨年開催した郷土料理の試食会の様子。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
おうみネットサポーターの小久保さんから、志賀町で地域の郷土食を受け継いでいき、普及活動を通じて地域のつながりを深めるようと、活動されている「志賀郷土料理の会」さんの取材報告の届きましたのでご紹介いたします。
ぜひお読みください。
【取材報告】
先日、志賀郷土料理の会を訪問した。
皆さん女性ばかりであるが、料理への熱意が横で見ているだけの私にも伝わってくる。中々に熱い会である。
先ずは、指導されている原さんからこの活動の動機や活動内容をお聞きした。
■活動を開始した動機
志賀郷土料理研究会(代表 原康子)は平成13年5月に志賀町(当時)社会福祉協議会のボランティアサークルの一つとして発足した。その後、志賀郷土料理研究会が設立母体となって、平成16年4月に志賀郷土料理の会が組織され、これまで一体となって活動してきた。その動機は、
・昔から食べつないできた地域の郷土食が若い世代に受け継がれていないことに危機感を抱いたこと
・地域の郷土食のなかに培われてきた長年の知恵とわざをお年寄りから学びたい
・郷土食を通して地域のつながりを深め、支え合う社会をつくりたい
とのこと。
参加されていた方々からのお話でも「地域のお年寄りから郷土食を学びたかった」、「子供の頃の味を再び味わいたかった」など14年間経てもその動機と想いは生きているようでした。
■その活動について
このような動機から志賀郷土料理研究会/志賀郷土料理は発足したが、具体的には次のような活動してきた。
・この地域に受け継がれてきた郷土食をお年寄りから学ぶこと
・郷土食の魅力を地域の若い世代に伝えること
・郷土食を広めることによって食生活の改善を図ること
・郷土食の普及活動を通じて、地域のつながりを深めること
郷土食には手間のかかった深い味わいがあり、幾世代もの人々の知恵がつながって作りあげてきたもの。志賀郷土料理の会では、このような魅力ある伝統的な郷土食を地域のお年寄りから直に学び、これをすべてレシピや写真として記録している。
郷土食は栄養的にもバランスがよく健康的な料理が多いので、志賀郷土料理の会では、郷土食を毎日の食生活に取り入れることを進める普及活動にも積極的に取り組んでいる。このような活動を通じて、食生活の改善を図り、地域のつながりを深めることに貢献することも会の大切な活動と思っている。
現在の参加者は地元以外からの人も多く、郷土食を通じた人のつながり、食文化の継承など、都市化し人のつながりが弱くなる最近の傾向とは別に、地域の重要なコミュニティとなっていると感じた。

■何故、14年間も続いているのか
会の発足当初は、80歳代のお年寄りから子供の頃から日常食べてきた料理を丁寧に聞き取り、実際に作ってもらい食べる勉強を2年間続けてきた。その間、調理法を記録し、レシピ作りも重ねて、出来上がったレシピをもとに、当初は、地域で料理教室を何回も開き、その活動を広めてもきた。郷土食は美味しいという50歳~80歳代がいる一方、若い世代、とくに子ども達は食べたことがないために、「美味しくない」、「興味もない」という人が多いという現実にもつきあたった。このような経験を重ねて、郷土食は食材の工夫と調理次第で美味しく食べられることを知ってもらうことも会の大切な役目と分かってきた。
豊かな時代がいつまでも続くか不安がある中、地元で収穫される昔ながらの野菜などを工夫して食べることを伝える必要があり、地元の野菜などを使うことによって、地域の農家も農作物を作ってくれるようにもなると思っている。
参加者のお話でも、若い人たちとの味の違いに悩んだり、地元の食材が手に入らなくなる心配などが出ていた。特に、湖魚は捕れる量も減り、価格が高騰してきていることへの不安は大きい様だ。しかし、自分たちで作った野菜や港まで行って仕入れた魚だけで料理をすることへのこだわりが14年間続いたのは凄い事であり、それが会をここまで支えてきたのではないか、と思う。
また、この会の活動を広く知ってもらうため、2006年に「食べつなぐ ふるさとの食事ー滋賀県志賀町」という本を出版した。その内容を少し紹介すると、
◆春は、「もろこ焼き」「なまり節と竹の子、ふき煮」「イタドリの煮付け」など。
◆夏は、「ハス魚田」「小あゆの山椒煮」「にしんなす」「なかよし豆」など。
◆秋は、「あめのうおご飯」「干しズイキとえび煮」「山菜おこわ」など。
◆冬は、「氷魚のゆず酢」「鴨とクレソン鍋」「いさざ煮」など。
夫々の料理にはレシピがあり、写真とともに美味しさを目で味わえるようです。
さらに、「おせち料理」「きびがら染め赤飯」「はや寿司」ほか色鮮やかな歳時料理の紹介もある。

「ハス魚田」

上記の鮒寿司は会員のご主人が多くの人に食してもらおうと8年かけて創っている「志賀版鮒寿司」。あっさり風で評判は上々
■現在の活動をお聞きした。
今は、30人ほどの人が参加して、月1回の割合で、郷土料理を勉強している。例えば、訪問したこの日の料理は、「野洲・守山の伝統料理のおあえ団子」、「ごはんピザ」、「新たまねぎと鯖水煮」、「ふきご飯」をその日の担当メンバーが中心となりそのレシピに沿って、作っていた。いずれも季節感があり、美味しかった。会の参加者も地元生まれで育ちの方は7、8名であり、東京、京都や熊本、奈良などから移り住んだ人、隣りの高島市からなど多方面の人で構成されており、様々な味感覚で豊かな食作りをされているようである。
参加者の言葉から様々な思いを聞いたが、共通した点は、自然豊かな志賀の味を家族に食べて欲しいと言う強い思いである。
「姑として、嫁にこの地域の味を伝えたかった」、
「母親として子供たちに地域で取れる食材で手造りの料理を食べさせたい」、
「琵琶湖の魚介類を食材にした料理をもっと知りたい」、
「地元のお年寄りからこの地域の食材を使った料理を教えてもらうのが楽しい」、
「季節に応じた食材を使って四季を感じるのが楽しみ」、
「外から来た人間にとって豊富な湖魚の料理は参考になる」、
「冷凍食品や食材になれた若い人に季節ごとの生の食材の良さを知って欲しい」、
「メニューを決める時、レシピもないのに幼い頃食べた記憶だけから料理を再現できた時、”化石を掘り起こした気分”になる」、
「昔、おばあさんが食べさせてくれた懐かしい味が今の若い世代に食べつながれることを信じて活動をしている」
など等。
さらに、会の代表の東さんや他の中核の人たちが強調したのは、「野菜類は自分で作ったものをその日に持ち寄り、魚介類はその日に捕れたものを使う事が大事であり、これは会の発足当時から守るべきこととして大切にしている」との言葉であった。また、今の子供たちや若い人に郷土の料理をそのままでは、味わってくれないので、現代風にアレンジしていく事も大事とのこと。


担当ごとに料理つくり、忙しそう! 「ごはんピザ」

つくったご飯を囲んでの食事会。献立も色々あって、美味しそう!
■これから更に活動を続けるためには
今まで会を支えてきたメンバーも年齢が高くなり、これからも活力ある活動を維持してゆくためにも、若い人たちの参加を進めて行きたい。また、特に湖魚は捕れる量の減少とともに価格も高くなって来ていて中々入手が難しくなっている。野菜類も含め、食材の確保が重要になりつつある。会は、主婦たちを中心とするボランティア活動であり、資金的な基盤も弱く、どのようにして活動を維持してゆくか資金面でも課題があるようだ。
しかし、これらの課題に対応しながら、若い世代や子供たちが郷土食に親しみ、食生活の質を向上させるための取り組みを更に広く知ってもらいたい。そのためには、他の地域の同じ想いの活動グループとの連携や様々なメディアを活用した情報発信を考えて行きたい、との熱い想いも語られた。
先ほどの本を出版した時は、新聞社や様々なメディアからの取材もあり、当初は各地のイベントに参加したりして、郷土料理を広く認知してもらえたが、最近は、その活動も少なくなり、毎月開催の料理教室が中心となっているようである。
ただ会員規模は今の30名ほどがよいが、自分たちの活動をもう少し広く認知してもらいたいと言う思いもあり、その両立をどうとって行くのか悩んでいるようだった。

昨年開催した郷土料理の試食会の様子。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
Posted by
BIWAちゃん
at
17:07
│
淡海ネットワークセンター
5月16日、17日に「かんじる比良2015」が開催されました。
おうみネットサポーターの小久保さんから、「かんじる比良2015」の報告が届きましたので、ご紹介いたします。
【かんじる比良2015】取材報告
今年も5月16と17日に「かんじる比良2015」が開催された。
比良山系と琵琶湖に囲まれた自然豊かな湖西の春のイベントとして8回目を迎える。38の出展のお店や作家の工房が約10kmほどの地域に点在するが、琵琶湖の蒼さと比良山系の緑を見ながらの散策は中々に楽しいものである。
今回参加のお店を回りながらも強く印象に残ったのは、比良山麓や林の中にあるお店の柔らかな雰囲気と集う人たちの醸し出すゆったりとした雰囲気だった。雑踏の中で味わうコーヒーや食事とは全く違う世界での体験であり、ここで生活を営む人たちの心地よさをおすそ分けするかのようなおもてなしがある。効率性と非人間性の優先される日常の日々では味わえない空気をその五感で感じることができる。そんな雰囲気を味わいたいのか、今年も二日間とはいえ、大阪、兵庫、京都、福井からの参加も含め5000人ほどの来場者があった。
「かんじる比良の会」代表の山川さんとのお話や当日の情景を交えながら報告する。

 大津市の北に位置する比良は、琵琶湖と比良山系にはさまれ、人々の暮らしと自然が融合した地域である。また、古代から交通の要衝でもあり、多くの古墳や城跡が点在もする歴史や文化が息づいている地域でもある。そのような中に、先祖伝来からこの地に暮らしその伝統や田園を守り続けてきた人、この地に魅せられ移住してきた人、ギャラリー・工房を構え創作活動する人など様々な人々が思い思いの暮らし方で住んでいる。
大津市の北に位置する比良は、琵琶湖と比良山系にはさまれ、人々の暮らしと自然が融合した地域である。また、古代から交通の要衝でもあり、多くの古墳や城跡が点在もする歴史や文化が息づいている地域でもある。そのような中に、先祖伝来からこの地に暮らしその伝統や田園を守り続けてきた人、この地に魅せられ移住してきた人、ギャラリー・工房を構え創作活動する人など様々な人々が思い思いの暮らし方で住んでいる。
「かんじる比良」は2007年11月、19店のショップと作家さんのご協力で始った。比良地域の自然、歴史、アート、文化、食の魅力を発信しようと湖西線沿線の蓬莱から北小松に点在する工房を中心に飲食や雑貨を扱う店などが参加した。また、比良の雑木林や湖はモノつくりの人たちの創作の場としても愛されており、地域の作家さんの協力で比良川の畔で野外造形展も開催された。
2回目以降は「滋賀の作家展」が地域のお寺の本堂で開催され、3回目は、大津市の歴史博物館で比良から離れて開催する事も試みられた。2008年は大津市の新パワーアップ・夢実現事業に認定され、のぼり、巡回バス、ポスター、ガイドブックが活用された。それ以後、手作りから始めたイベントもホームページやfacebookの開設やイベントが終わったあとでも来られる人のために工夫したガイドブック作りなど試行錯誤を重ねながら地域のつながりを更に強めるイベントになって行った。
「かんじる比良」は、比良に住み、仕事場としてその自然に触れながら生活をする陶芸作家、木工の職人、カフェ経営者などが「かんじる比良の会」の実行委員会として、その年の初めから毎年5月の開催に向けて出展者を集め、地元や関連部門との調整、広報のためのポスターやガイドマップ作成、ホームページの更新などを進めていく。今回も40人の会員(うち出店者38店)と10人の協賛会員がそれぞれの役割分担で、イベントを開催した。ガイドマップ作りやホームページ更新などは全て委員会のメンバーの手作りであり、会場の運営もボランティアや協賛メンバーの支援で行っている。人とのつながり、地域とのつながりがこのイベントの特長でもある。当日は、普段は公開していない作家の工房やアトリエを開放したり、ギャラリーなどでは地域にちなんだ展示をしたり、比良にゆかりのある作家たちの作品展、里山コンサート、各参加店では「かんじる比良」限定企画など開催してきた。
「この比良には、琵琶湖と比良の山並に囲まれた自然があり、それに魅かれて移り住んでいる陶芸や漆塗り、木工などの作家が多くいる。また、パンやケーキなどの食を扱うお店も点在している。この人たちを上手く結び付けられないか、ここの良さをもっと知ってもらえないかと思ったのが、始まりです。」と山川さんは話す。
一日目は、少し曇っていたが、二日目は気持よく晴れ上がった。山側の工房やお店を探訪するには、木洩れ日の中をゆったりと歩き、湖畔のお店では、琵琶湖のさざなみの中で一服する。そんな光景も見られた。いずれもこの自然に引き寄せられてきた人々がその想いを分けるような気持ちで訪れる人を招き入れる。その自然体のやり方が、このイベントの良さであり、他では出来ない「おもてなし」なのであろう。
更に、山川さんは、「工房や作家さんたちは、本来の仕事を中断しての出店であり、無理をせず、出来る範囲で出展をお願いしている。ただ、来てもらった人たちが楽しく過ごしてもらいたいとの想いから工房の開放、体験教室、ミニコンサート、期間中の特別メニューなどそれぞれが工夫を凝らし楽しく盛り上げてもらっています。この楽しさが参加者と出店者の共感となって今日まで続いて来たような気がする」。無理をしないという点では、今でも続くこの周辺の遺跡めぐりの「歴史ハイキング」も会員の負担となるため、秋に1回の開催とした。運営も今は、会員の会費と企業からの協賛金のみ、開催に絡む様々な対応は会員のボランティアであり、会員の持つ様々なスキルを上手く使いながらの手作りである。無理をせず自分たちの出来る範囲でやる、これが「かんじる比良」の力となっているようだ。
最後に山川さんが言ったことは地域で何かをやっていきたいと思う人には、あらためてかみしめて欲しいもの。
「かんじる比良はこの地に住む人の間から生まれた活動ですが、これを進めて行く中で、出店者同士のつながりが出来たり、そのつながりが新しいつながりになったり、移住して来たばかりだが地域へすぐに馴染めた、など自然発生的なコミュニティが出来つつある。また、新しく来られた人からこの地域の素晴らしさを古くからの地元の人が教えてもらうといったことも出て来た。比良と言う良さをもっと知り、そのつながりを広め、もっとローカルにやって行きたい」。
かんじる比良2015に開催されたイベントを紹介します。
◆5月15日(金)かんじる比良2015・作家と職人展 作家展は15~17日の3日間
◆5月16日(土)かんじる比良2015・本イベント 歩いて感じる比良の風・作家と職人展
◆5月17日(日)かんじる比良2015・本イベント 歩いて感じる比良の風・作家と職人展
◆5月17日(日)おやこ泥んこ・とうげい教室
同時に、比良麓の会自治会館「森の家」にて、「かんじる比良2015 作家と職人展」も開催されていました。以下の多くの作家さんたちの出店作品があり、木洩れ日の注ぐ中で静かに勧賞できました。
【陶芸】加藤和宏 / 加藤敏雄 / 木村展之 / 木村隆 / 玉川義人 / 中島千英子
中野悟朗 / 村田真人
【染織】中島千津 / 平井恵子 / 宮﨑芳郎
【漆芸】廣田千惠 / 藤井收
【木工】臼井浩明 / 雄倉高秋
【油彩画】岡本裕介
【平面】村井宏二 / 村井由美子
【立体】山内鈴花
【写真】佐伯俊次 / 内藤美智子 / 平田尚加 / 吉田信介
【刺繍】岡村達
【仏像】安田明玄
【仏画】安田素彩
【靴】大村寛康
今回は比良周辺のお店や工房が38店参加しました。
下記が参加店の一覧です。参加店の詳細は下記サイトにてご覧ください。
http://kanjiruhira.org/shops/
1)パン工房ヤックル 2)青木煮豆店 3)FICA 4)靴つくり 5)アルカドッグトレーニング 6)R café 7)ほっとすてぃしょん比良 8)北欧直販 9)Gallery skog(ギャラリー スクーグ) 10)TOPPIN OUTDOOR & TRAVEL 11)森のACHA(もりのあちゃ) 12)Roz & Mary Cafe(ロズアンドマリー) 13)ちゃわん 比良八光窯(加藤敏雄 陶芸作家) 14)アントレ 15)ヒラノハナレ 16)庭工房 “ギャラリー季気” 17)イタリアンピザレストラン “季気 HOUSE” 18)ホリデーアフタヌーン 19)ほとり・ポトリ 20)ドッグスクール「比良ドッグファーム」 21)Cafe COCOKUON(カフェ ココクオン) 22)アンティークハウス DーYrs.(ディーユアーズ) 23)MANA(shop YUMEYA) 24)SOUP FURNITURE(スープファニチャー) 25)古民家風貸別荘 夢湖庵 26)木原食品 27)布工房 モッサリーナ 28)H&K craft 29)慧夢工房(えむこうぼう) 30)純jun-楽布絵 31)コトブキ 32)Cotton Field パッチワーク教室 33)タコス屋 エル・チャンガーロ 34)L.A.S. 35)Mandala’s@一休庵 36)ティーツリーガーデン tea tree garden 37)陶房 木村 38)湖西焼 圓工房(圓口功治(まるぐち こうじ))




3)FICA 9)Gallery skog 11)森のacha 14)アントレ



16)庭工房ギャラリー季気 20)比良ドッグファーム 22)アンティークハウス


24)soup furniture の制作風景 29)慧夢工房(えむこうぼう)
なお、当日の様子は、以下のfacebookページにも載っています。
https://www.facebook.com/kanjiruhira?fref=ts
かんじる比良の参加者は作家から喫茶店、アウトドアや家具の販売店など多種多様です。しかし、そのような多様な人たちの集まりですが、1つ大きな共通点があります。雪に覆われた比良の山々と黒く静かな琵琶湖、春の様々な花々に彩られる里山やかすんだ中に浮かぶ湖、そして深い緑におおわれた山麓に涼風の流れを感じる夏、すべてがここに住む人々に感じられる情景なのです。
皆さん、比良のこの自然に憧れてここに住みたいと思った方なのです。林や森の中にそれぞれが想いの深いお店として点在する地域がここ比良であり、それを見せるのがこの「かんじる比良」の役割なのかもしれません。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
【かんじる比良2015】取材報告
今年も5月16と17日に「かんじる比良2015」が開催された。
比良山系と琵琶湖に囲まれた自然豊かな湖西の春のイベントとして8回目を迎える。38の出展のお店や作家の工房が約10kmほどの地域に点在するが、琵琶湖の蒼さと比良山系の緑を見ながらの散策は中々に楽しいものである。
今回参加のお店を回りながらも強く印象に残ったのは、比良山麓や林の中にあるお店の柔らかな雰囲気と集う人たちの醸し出すゆったりとした雰囲気だった。雑踏の中で味わうコーヒーや食事とは全く違う世界での体験であり、ここで生活を営む人たちの心地よさをおすそ分けするかのようなおもてなしがある。効率性と非人間性の優先される日常の日々では味わえない空気をその五感で感じることができる。そんな雰囲気を味わいたいのか、今年も二日間とはいえ、大阪、兵庫、京都、福井からの参加も含め5000人ほどの来場者があった。
「かんじる比良の会」代表の山川さんとのお話や当日の情景を交えながら報告する。

 大津市の北に位置する比良は、琵琶湖と比良山系にはさまれ、人々の暮らしと自然が融合した地域である。また、古代から交通の要衝でもあり、多くの古墳や城跡が点在もする歴史や文化が息づいている地域でもある。そのような中に、先祖伝来からこの地に暮らしその伝統や田園を守り続けてきた人、この地に魅せられ移住してきた人、ギャラリー・工房を構え創作活動する人など様々な人々が思い思いの暮らし方で住んでいる。
大津市の北に位置する比良は、琵琶湖と比良山系にはさまれ、人々の暮らしと自然が融合した地域である。また、古代から交通の要衝でもあり、多くの古墳や城跡が点在もする歴史や文化が息づいている地域でもある。そのような中に、先祖伝来からこの地に暮らしその伝統や田園を守り続けてきた人、この地に魅せられ移住してきた人、ギャラリー・工房を構え創作活動する人など様々な人々が思い思いの暮らし方で住んでいる。「かんじる比良」は2007年11月、19店のショップと作家さんのご協力で始った。比良地域の自然、歴史、アート、文化、食の魅力を発信しようと湖西線沿線の蓬莱から北小松に点在する工房を中心に飲食や雑貨を扱う店などが参加した。また、比良の雑木林や湖はモノつくりの人たちの創作の場としても愛されており、地域の作家さんの協力で比良川の畔で野外造形展も開催された。
2回目以降は「滋賀の作家展」が地域のお寺の本堂で開催され、3回目は、大津市の歴史博物館で比良から離れて開催する事も試みられた。2008年は大津市の新パワーアップ・夢実現事業に認定され、のぼり、巡回バス、ポスター、ガイドブックが活用された。それ以後、手作りから始めたイベントもホームページやfacebookの開設やイベントが終わったあとでも来られる人のために工夫したガイドブック作りなど試行錯誤を重ねながら地域のつながりを更に強めるイベントになって行った。
「かんじる比良」は、比良に住み、仕事場としてその自然に触れながら生活をする陶芸作家、木工の職人、カフェ経営者などが「かんじる比良の会」の実行委員会として、その年の初めから毎年5月の開催に向けて出展者を集め、地元や関連部門との調整、広報のためのポスターやガイドマップ作成、ホームページの更新などを進めていく。今回も40人の会員(うち出店者38店)と10人の協賛会員がそれぞれの役割分担で、イベントを開催した。ガイドマップ作りやホームページ更新などは全て委員会のメンバーの手作りであり、会場の運営もボランティアや協賛メンバーの支援で行っている。人とのつながり、地域とのつながりがこのイベントの特長でもある。当日は、普段は公開していない作家の工房やアトリエを開放したり、ギャラリーなどでは地域にちなんだ展示をしたり、比良にゆかりのある作家たちの作品展、里山コンサート、各参加店では「かんじる比良」限定企画など開催してきた。
「この比良には、琵琶湖と比良の山並に囲まれた自然があり、それに魅かれて移り住んでいる陶芸や漆塗り、木工などの作家が多くいる。また、パンやケーキなどの食を扱うお店も点在している。この人たちを上手く結び付けられないか、ここの良さをもっと知ってもらえないかと思ったのが、始まりです。」と山川さんは話す。
一日目は、少し曇っていたが、二日目は気持よく晴れ上がった。山側の工房やお店を探訪するには、木洩れ日の中をゆったりと歩き、湖畔のお店では、琵琶湖のさざなみの中で一服する。そんな光景も見られた。いずれもこの自然に引き寄せられてきた人々がその想いを分けるような気持ちで訪れる人を招き入れる。その自然体のやり方が、このイベントの良さであり、他では出来ない「おもてなし」なのであろう。
更に、山川さんは、「工房や作家さんたちは、本来の仕事を中断しての出店であり、無理をせず、出来る範囲で出展をお願いしている。ただ、来てもらった人たちが楽しく過ごしてもらいたいとの想いから工房の開放、体験教室、ミニコンサート、期間中の特別メニューなどそれぞれが工夫を凝らし楽しく盛り上げてもらっています。この楽しさが参加者と出店者の共感となって今日まで続いて来たような気がする」。無理をしないという点では、今でも続くこの周辺の遺跡めぐりの「歴史ハイキング」も会員の負担となるため、秋に1回の開催とした。運営も今は、会員の会費と企業からの協賛金のみ、開催に絡む様々な対応は会員のボランティアであり、会員の持つ様々なスキルを上手く使いながらの手作りである。無理をせず自分たちの出来る範囲でやる、これが「かんじる比良」の力となっているようだ。
最後に山川さんが言ったことは地域で何かをやっていきたいと思う人には、あらためてかみしめて欲しいもの。
「かんじる比良はこの地に住む人の間から生まれた活動ですが、これを進めて行く中で、出店者同士のつながりが出来たり、そのつながりが新しいつながりになったり、移住して来たばかりだが地域へすぐに馴染めた、など自然発生的なコミュニティが出来つつある。また、新しく来られた人からこの地域の素晴らしさを古くからの地元の人が教えてもらうといったことも出て来た。比良と言う良さをもっと知り、そのつながりを広め、もっとローカルにやって行きたい」。
かんじる比良2015に開催されたイベントを紹介します。
◆5月15日(金)かんじる比良2015・作家と職人展 作家展は15~17日の3日間
◆5月16日(土)かんじる比良2015・本イベント 歩いて感じる比良の風・作家と職人展
◆5月17日(日)かんじる比良2015・本イベント 歩いて感じる比良の風・作家と職人展
◆5月17日(日)おやこ泥んこ・とうげい教室
同時に、比良麓の会自治会館「森の家」にて、「かんじる比良2015 作家と職人展」も開催されていました。以下の多くの作家さんたちの出店作品があり、木洩れ日の注ぐ中で静かに勧賞できました。
【陶芸】加藤和宏 / 加藤敏雄 / 木村展之 / 木村隆 / 玉川義人 / 中島千英子
中野悟朗 / 村田真人
【染織】中島千津 / 平井恵子 / 宮﨑芳郎
【漆芸】廣田千惠 / 藤井收
【木工】臼井浩明 / 雄倉高秋
【油彩画】岡本裕介
【平面】村井宏二 / 村井由美子
【立体】山内鈴花
【写真】佐伯俊次 / 内藤美智子 / 平田尚加 / 吉田信介
【刺繍】岡村達
【仏像】安田明玄
【仏画】安田素彩
【靴】大村寛康
今回は比良周辺のお店や工房が38店参加しました。
下記が参加店の一覧です。参加店の詳細は下記サイトにてご覧ください。
http://kanjiruhira.org/shops/
1)パン工房ヤックル 2)青木煮豆店 3)FICA 4)靴つくり 5)アルカドッグトレーニング 6)R café 7)ほっとすてぃしょん比良 8)北欧直販 9)Gallery skog(ギャラリー スクーグ) 10)TOPPIN OUTDOOR & TRAVEL 11)森のACHA(もりのあちゃ) 12)Roz & Mary Cafe(ロズアンドマリー) 13)ちゃわん 比良八光窯(加藤敏雄 陶芸作家) 14)アントレ 15)ヒラノハナレ 16)庭工房 “ギャラリー季気” 17)イタリアンピザレストラン “季気 HOUSE” 18)ホリデーアフタヌーン 19)ほとり・ポトリ 20)ドッグスクール「比良ドッグファーム」 21)Cafe COCOKUON(カフェ ココクオン) 22)アンティークハウス DーYrs.(ディーユアーズ) 23)MANA(shop YUMEYA) 24)SOUP FURNITURE(スープファニチャー) 25)古民家風貸別荘 夢湖庵 26)木原食品 27)布工房 モッサリーナ 28)H&K craft 29)慧夢工房(えむこうぼう) 30)純jun-楽布絵 31)コトブキ 32)Cotton Field パッチワーク教室 33)タコス屋 エル・チャンガーロ 34)L.A.S. 35)Mandala’s@一休庵 36)ティーツリーガーデン tea tree garden 37)陶房 木村 38)湖西焼 圓工房(圓口功治(まるぐち こうじ))




3)FICA 9)Gallery skog 11)森のacha 14)アントレ



16)庭工房ギャラリー季気 20)比良ドッグファーム 22)アンティークハウス


24)soup furniture の制作風景 29)慧夢工房(えむこうぼう)
なお、当日の様子は、以下のfacebookページにも載っています。
https://www.facebook.com/kanjiruhira?fref=ts
かんじる比良の参加者は作家から喫茶店、アウトドアや家具の販売店など多種多様です。しかし、そのような多様な人たちの集まりですが、1つ大きな共通点があります。雪に覆われた比良の山々と黒く静かな琵琶湖、春の様々な花々に彩られる里山やかすんだ中に浮かぶ湖、そして深い緑におおわれた山麓に涼風の流れを感じる夏、すべてがここに住む人々に感じられる情景なのです。
皆さん、比良のこの自然に憧れてここに住みたいと思った方なのです。林や森の中にそれぞれが想いの深いお店として点在する地域がここ比良であり、それを見せるのがこの「かんじる比良」の役割なのかもしれません。
(おうみネットサポーター 小久保 弘)
Posted by
BIWAちゃん
at
09:38
│
淡海ネットワークセンター
おうみ未来塾第12期塾生募集説明会開催決定!
うみ未来塾第12期塾生募集説明会開催決定!
おうみ未来塾第12期塾生募集説明会
あなたも「地域プロデューサー」を目指しませんか!
「おうみ未来塾」は、市民活動やNPOが、地域運営の一翼を担う時代となった今、
新しい地域課題に取り組む「地域プロデューサー」が育つ塾を目指しています。
「地域プロデューサー」とは、地域の問題を発見し、解決のための方策を考え、
そのための運動や事業をおこすことができる人であると考えています。
今回、第12期塾生募集にあたり、説明会を開催しますので、ご参加をお待ちしています!
「地域プロデューサー」に興味のある方、地域の課題解決に主体的に取り組みたいとお考えの方、
是非ご参加ください!
【募集説明会日程】※募集期間:3月15日(木)~4月15日(日)17:00まで
◇3月30日(金)19:00~20:00 【米原市】米原市米原公民館 研修室3-B
◇3月31日(土)10:30~11:30 【高島市】今津東コミュニティセンター会議室2
◇3月31日(土)14:30~15:30 【大津市】県民交流センター302会議室
◇4月6日(金)19:00~20:00 【守山市】守山市民交流センター1階交流室
◇4月8日(日)10:30~11:30 【大津市】県民交流センター302会議室
◇4月8日(日)14:30~15:30 【東近江市】アピア研修室B
おうみ未来塾第12期生募集要項も公開しています!こちら→http://onc.shiga-saku.net/e754005.html
おうみ未来塾の詳細については【こちら】
http://www.ohmi-net.com/article/13960867.html
◆お申し込み・お問い合わせ先
淡海ネットワークセンター (公益財団法人 淡海文化振興財団)
〒520-0801 大津市におの浜1-1-20(ピアザ淡海2階)
TEL 077-524-8440 FAX 077-524-8442
Email office@ohmi-net.com URL http://www.ohmi-net.com/
おうみ未来塾第12期塾生募集説明会
あなたも「地域プロデューサー」を目指しませんか!
「おうみ未来塾」は、市民活動やNPOが、地域運営の一翼を担う時代となった今、
新しい地域課題に取り組む「地域プロデューサー」が育つ塾を目指しています。
「地域プロデューサー」とは、地域の問題を発見し、解決のための方策を考え、
そのための運動や事業をおこすことができる人であると考えています。
今回、第12期塾生募集にあたり、説明会を開催しますので、ご参加をお待ちしています!
「地域プロデューサー」に興味のある方、地域の課題解決に主体的に取り組みたいとお考えの方、
是非ご参加ください!
【募集説明会日程】※募集期間:3月15日(木)~4月15日(日)17:00まで
◇3月30日(金)19:00~20:00 【米原市】米原市米原公民館 研修室3-B
◇3月31日(土)10:30~11:30 【高島市】今津東コミュニティセンター会議室2
◇3月31日(土)14:30~15:30 【大津市】県民交流センター302会議室
◇4月6日(金)19:00~20:00 【守山市】守山市民交流センター1階交流室
◇4月8日(日)10:30~11:30 【大津市】県民交流センター302会議室
◇4月8日(日)14:30~15:30 【東近江市】アピア研修室B
おうみ未来塾第12期生募集要項も公開しています!こちら→http://onc.shiga-saku.net/e754005.html
おうみ未来塾の詳細については【こちら】
http://www.ohmi-net.com/article/13960867.html
◆お申し込み・お問い合わせ先
淡海ネットワークセンター (公益財団法人 淡海文化振興財団)
〒520-0801 大津市におの浜1-1-20(ピアザ淡海2階)
TEL 077-524-8440 FAX 077-524-8442
Email office@ohmi-net.com URL http://www.ohmi-net.com/
Posted by
BIWAちゃん
at
16:44
│
淡海ネットワークセンター