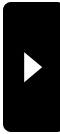棚田百選の畑の棚田で草刈り
2015年07月31日
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと、池田勝です。
またまた、棚田へ。今回は、棚田百選にも選ばれてる高島市の畑(はた)地区です。
参加者は、私も含めて5名。近くは大津市雄琴から、栗東市、そしてなんと大阪と奈良からも来られました!
奈良からの方は、棚田ボランティアで滋賀を回っておられる常連の方。1泊で滋賀を楽しんでおられます。
栗東市の方は、お近くの走井の棚田ボランティアに参加して、今回は足を延ばして来られました。
地域の方も各家から総出で草刈りや溝掃除に出ておられます。

軽トラに草刈り機を積んで、いざ草刈りへ。村の周囲をぐるりと囲んでいる獣害対策の柵の周辺の草を刈ります。
畑は、棚田の景観を保全するために、田んぼのすぐ近くでなく、集落と山の間に柵が張り巡らされているのです。
毎度ビフォアーアフターを忘れているのですが、こんな調子です。

草刈り前の柵のあたり。

草刈り後の様子です。
私が、まだまだ草刈り機をマスターしきれていないのが分かります。
草刈りは、右から左へ刈るのが基本(刃の回転方向が反時計まわりのため)なのですが、斜面と柵と出入口の関係で、逆の左から右となり、上手に刈れていません。
この日は、8時からの作業だったのですが、午前中だけでも汗が滴り落ちました。
休憩時に飲むお茶が、すぐにその後の作業で汗となって出ているような状態。

お昼休憩時は、みな横になり午後からの作業に備えて体力の回復に努めます。

休憩時に、畑地区のさらに上へ。棚田が一望できるポイントから眺めました。
遠くは、びわ湖、そして伊吹山も見えます。
暑い日でしたが、空気が澄んできれいに棚田が見えるので、皆さん「おーいいねぇ」の声。

昼からも山裾へ移動して、草刈り。

そもそも、なぜ草刈りをするのでしょうか?
・棚田の景観を守る。
・鹿や猪が隠れる場所をなくす。
・草が繁茂すると獣害柵の電柵の電流が放電してしまう。
全部の草が刈れると良いのですが、まずは柵の周りを刈って獣害を防ごうとしておられます。

地域の方の努力で、畑の棚田が守られています。
中干しも終わり、畑のきれいな水が各田んぼに引かれ、穂が出始めた稲はドンドン成長しています。

一部、成長の遅い田がありました。これから大きくなるのかなぁと不思議に思いますので、聞きました。
そうすると・・・
「田はほっとくと草が生えるし、あかんようになる。畑の棚田の景色もなくなってしまう。この田では、たぶん稲はとれへんやろうけど、棚田を守るために、田植の時期に間に合わなくても田植をしているんや。喜ぶんは棚田の写真を撮る写真家さんだけやろうけどな。」
笑いながら話されていましたが、その言葉には地域への思いがしっかりと入っていました。

畑は、積極的に活動もしておられます。棚田オーナー制度(大阪からの方も棚田オーナーでした)や、酒米づくり(高島市勝野の萩之露ブランドで、「里山」というお酒を出しておられます)、農家民泊(先日も海外から宿泊されたお客さんがおられたのこと)、そして、棚田みそも販売しておられます。
私も1つ購入して、これから使う予定です。
夕方の帰り際、各家庭の草刈りをしておられました。朝も昼も、そして夕にも作業をされる体力に脱帽!と思い、声をかけました。すると、
「みんなで作業する日は、自分の家や畔回りは、昼間にすると迷惑がかかるからね。それに涼しくなってきたから作業はしやすいよ」との返事が返って来ました。
地域のこと、周囲の人の思いも考えながら作業をしておられる姿に、地域で生きる誇りと心を感じたような棚田の1日でした。
ぜひ、皆さんも棚田ボランティアへ!畑の棚田ボランティアは次回は、8/9(日)です。
詳しくは、おうみ棚田ねっとをご覧ください。
またまた、棚田へ。今回は、棚田百選にも選ばれてる高島市の畑(はた)地区です。
参加者は、私も含めて5名。近くは大津市雄琴から、栗東市、そしてなんと大阪と奈良からも来られました!
奈良からの方は、棚田ボランティアで滋賀を回っておられる常連の方。1泊で滋賀を楽しんでおられます。
栗東市の方は、お近くの走井の棚田ボランティアに参加して、今回は足を延ばして来られました。
地域の方も各家から総出で草刈りや溝掃除に出ておられます。

軽トラに草刈り機を積んで、いざ草刈りへ。村の周囲をぐるりと囲んでいる獣害対策の柵の周辺の草を刈ります。
畑は、棚田の景観を保全するために、田んぼのすぐ近くでなく、集落と山の間に柵が張り巡らされているのです。
毎度ビフォアーアフターを忘れているのですが、こんな調子です。

草刈り前の柵のあたり。

草刈り後の様子です。
私が、まだまだ草刈り機をマスターしきれていないのが分かります。
草刈りは、右から左へ刈るのが基本(刃の回転方向が反時計まわりのため)なのですが、斜面と柵と出入口の関係で、逆の左から右となり、上手に刈れていません。
この日は、8時からの作業だったのですが、午前中だけでも汗が滴り落ちました。
休憩時に飲むお茶が、すぐにその後の作業で汗となって出ているような状態。

お昼休憩時は、みな横になり午後からの作業に備えて体力の回復に努めます。

休憩時に、畑地区のさらに上へ。棚田が一望できるポイントから眺めました。
遠くは、びわ湖、そして伊吹山も見えます。
暑い日でしたが、空気が澄んできれいに棚田が見えるので、皆さん「おーいいねぇ」の声。

昼からも山裾へ移動して、草刈り。

そもそも、なぜ草刈りをするのでしょうか?
・棚田の景観を守る。
・鹿や猪が隠れる場所をなくす。
・草が繁茂すると獣害柵の電柵の電流が放電してしまう。
全部の草が刈れると良いのですが、まずは柵の周りを刈って獣害を防ごうとしておられます。

地域の方の努力で、畑の棚田が守られています。
中干しも終わり、畑のきれいな水が各田んぼに引かれ、穂が出始めた稲はドンドン成長しています。

一部、成長の遅い田がありました。これから大きくなるのかなぁと不思議に思いますので、聞きました。
そうすると・・・
「田はほっとくと草が生えるし、あかんようになる。畑の棚田の景色もなくなってしまう。この田では、たぶん稲はとれへんやろうけど、棚田を守るために、田植の時期に間に合わなくても田植をしているんや。喜ぶんは棚田の写真を撮る写真家さんだけやろうけどな。」
笑いながら話されていましたが、その言葉には地域への思いがしっかりと入っていました。

畑は、積極的に活動もしておられます。棚田オーナー制度(大阪からの方も棚田オーナーでした)や、酒米づくり(高島市勝野の萩之露ブランドで、「里山」というお酒を出しておられます)、農家民泊(先日も海外から宿泊されたお客さんがおられたのこと)、そして、棚田みそも販売しておられます。
私も1つ購入して、これから使う予定です。
夕方の帰り際、各家庭の草刈りをしておられました。朝も昼も、そして夕にも作業をされる体力に脱帽!と思い、声をかけました。すると、
「みんなで作業する日は、自分の家や畔回りは、昼間にすると迷惑がかかるからね。それに涼しくなってきたから作業はしやすいよ」との返事が返って来ました。
地域のこと、周囲の人の思いも考えながら作業をしておられる姿に、地域で生きる誇りと心を感じたような棚田の1日でした。
ぜひ、皆さんも棚田ボランティアへ!畑の棚田ボランティアは次回は、8/9(日)です。
詳しくは、おうみ棚田ねっとをご覧ください。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 17:15
│環境学習センター