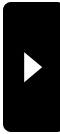西の湖で葦刈り
2014年02月22日
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
今日は、、西の湖(近江八幡市安土町)で葦刈りをしてきましたので、その報告を。
(葦はヨシと読みます。アシとは言いません。滋賀では悪しではなくて良しなんです。)
今回の葦刈りは、ヨシでびわ湖を守るネットワークさん、安土町商工会さん、東近江水環境自治協議会さんが主催され、琵琶湖博物館も協力しています。
県内から26の事業所、約230名の人が集まり、カマを持ってさっそく葦原へ。

葦原に着くと、まずは葦の高さに圧倒されます。今年の葦の生育は例年通りで、先日の雪にも倒れず、約5メートル弱ほどの高さになっています。

1年(というより半年ほどで)で、こんなに大きくなります。
肥料をやるでもないのに、土と空気と、増水時にかぶる琵琶湖の水だけでこんなに大きくなるんです。
葦ってすごいなぁと思います。
葦に比べると人間は小人サイズで、葦原というより、葦の森です。
かくれんぼをしたり、道を刈り取って迷路づくりなんてのも楽しそうです。
真ん中の棒の位置を覚えておいてくださいね。どこまで刈り進んだかの基準です。

ざくざく刈取り、束にしていきます。
と、適当にやっていたのですが、途中で安土の葦を扱っている方が教えてくださりました。
「刈っている処には、葦とオギが混じっている。」「葦の穂は少し黒く、葉っぱが巻きついている。オギの穂は黄色く、節が膨らんでいて、節から枝のようなものが出ている」
「西の湖の水位が低いと、土に水がかぶらずオギやセイタカアワダチソウが出てくる。水がかぶると葦だけが成長する。」
「そして、みんなが刈ってくれた後に、手作業で葦とオギを分けているんだよ」
改めて見ると、葦とは違うもの(オギ)が混ざっていることに気付きました。
刈りながら分けようとすると大変で、後でまとめて分けることにしました。
刈り取る作業も大変ですが、それを1本1本分けていく作業がさらに大変なのですね。
ヨシズの材料や、繊維から紙製品を作ったり、工芸品に加工したりするためには、手間が必要です。
刈り取りながらそのことも考え始めました。
博物館では、体験学習で葦笛づくりを行っています。
今回博物館からの参加で、刈り取った葦は来年度以降、子どもたちの学びの場で利用される予定です。

改めて、この大きさ。博物館のカヤネズミ博士と、交流体験の先生です。
1本1本は軽くて頼りないのですが、まとめて持つとかなりの重さ。風が吹くと一緒に飛びそうになります。

ちなみに、今回の刈取りでは、カヤネズミの巣は発見できずでした。
が、みなさん口々に「去年は見たよ~」とのこと。
カヤネズミは、葦の葉は少し硬くて巣にしづらいそうですが、葦や様々なイネ科の植物が生える原に巣を作ります。萱原が減り、カヤネズミも減ってしまっています。
葦そのもの価値だけでなく、その環境の価値も考えていく必要を感じます。

葦刈りを終えて、束を運ぶ学生さんたち。
長い葦を抱えていると、これから戦か祭りにいくような雰囲気を感じます。

で、刈取り後の写真です。
左の端に黒い棒が立っています。先ほどの写真と比べて、刈取りがどれだけ進んだかわかりますか?

今回全員で刈り取った葦は、この軽トラ23台分。
たくさんの人の行動で、少しずつ琵琶湖全体の環境が保全されています。
刈り取った葦は、コクヨさんで葦紙になったり、農業用の暗渠水路の目詰まり防止材に利用されたり、葦松明に利用されたりします。
葦刈り終了後、安土の方々とお話ししているとこんなことを聞きました。
・以前西の湖を覆いつくすように増えていたホテイアオイが、3年ほど前から一気に消えた。
・同じように水面から見えていたカナダモも、少なくなった。
・ブラックバスが減り、在来魚が増えたように思う。
西の湖の環境が変わってきているようです。西の湖は琵琶湖の縮図のように感じます。
このような変化が、水草が増えたり、外来魚が多い琵琶湖にも表れるのでしょうか?
長い目で見て、良い変化が起こることを期待していますし、悪いことの前兆でないことを祈ります。
今日は、、西の湖(近江八幡市安土町)で葦刈りをしてきましたので、その報告を。
(葦はヨシと読みます。アシとは言いません。滋賀では悪しではなくて良しなんです。)
今回の葦刈りは、ヨシでびわ湖を守るネットワークさん、安土町商工会さん、東近江水環境自治協議会さんが主催され、琵琶湖博物館も協力しています。
県内から26の事業所、約230名の人が集まり、カマを持ってさっそく葦原へ。

葦原に着くと、まずは葦の高さに圧倒されます。今年の葦の生育は例年通りで、先日の雪にも倒れず、約5メートル弱ほどの高さになっています。

1年(というより半年ほどで)で、こんなに大きくなります。
肥料をやるでもないのに、土と空気と、増水時にかぶる琵琶湖の水だけでこんなに大きくなるんです。
葦ってすごいなぁと思います。
葦に比べると人間は小人サイズで、葦原というより、葦の森です。
かくれんぼをしたり、道を刈り取って迷路づくりなんてのも楽しそうです。
真ん中の棒の位置を覚えておいてくださいね。どこまで刈り進んだかの基準です。

ざくざく刈取り、束にしていきます。
と、適当にやっていたのですが、途中で安土の葦を扱っている方が教えてくださりました。
「刈っている処には、葦とオギが混じっている。」「葦の穂は少し黒く、葉っぱが巻きついている。オギの穂は黄色く、節が膨らんでいて、節から枝のようなものが出ている」
「西の湖の水位が低いと、土に水がかぶらずオギやセイタカアワダチソウが出てくる。水がかぶると葦だけが成長する。」
「そして、みんなが刈ってくれた後に、手作業で葦とオギを分けているんだよ」
改めて見ると、葦とは違うもの(オギ)が混ざっていることに気付きました。
刈りながら分けようとすると大変で、後でまとめて分けることにしました。
刈り取る作業も大変ですが、それを1本1本分けていく作業がさらに大変なのですね。
ヨシズの材料や、繊維から紙製品を作ったり、工芸品に加工したりするためには、手間が必要です。
刈り取りながらそのことも考え始めました。
博物館では、体験学習で葦笛づくりを行っています。
今回博物館からの参加で、刈り取った葦は来年度以降、子どもたちの学びの場で利用される予定です。

改めて、この大きさ。博物館のカヤネズミ博士と、交流体験の先生です。
1本1本は軽くて頼りないのですが、まとめて持つとかなりの重さ。風が吹くと一緒に飛びそうになります。

ちなみに、今回の刈取りでは、カヤネズミの巣は発見できずでした。
が、みなさん口々に「去年は見たよ~」とのこと。
カヤネズミは、葦の葉は少し硬くて巣にしづらいそうですが、葦や様々なイネ科の植物が生える原に巣を作ります。萱原が減り、カヤネズミも減ってしまっています。
葦そのもの価値だけでなく、その環境の価値も考えていく必要を感じます。

葦刈りを終えて、束を運ぶ学生さんたち。
長い葦を抱えていると、これから戦か祭りにいくような雰囲気を感じます。

で、刈取り後の写真です。
左の端に黒い棒が立っています。先ほどの写真と比べて、刈取りがどれだけ進んだかわかりますか?

今回全員で刈り取った葦は、この軽トラ23台分。
たくさんの人の行動で、少しずつ琵琶湖全体の環境が保全されています。
刈り取った葦は、コクヨさんで葦紙になったり、農業用の暗渠水路の目詰まり防止材に利用されたり、葦松明に利用されたりします。
葦刈り終了後、安土の方々とお話ししているとこんなことを聞きました。
・以前西の湖を覆いつくすように増えていたホテイアオイが、3年ほど前から一気に消えた。
・同じように水面から見えていたカナダモも、少なくなった。
・ブラックバスが減り、在来魚が増えたように思う。
西の湖の環境が変わってきているようです。西の湖は琵琶湖の縮図のように感じます。
このような変化が、水草が増えたり、外来魚が多い琵琶湖にも表れるのでしょうか?
長い目で見て、良い変化が起こることを期待していますし、悪いことの前兆でないことを祈ります。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 17:28
│環境学習センター