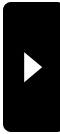かわいい花ですが、大問題。オオバナミズキンバイの除去
2014年07月01日
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
今日は、かわいらしいお花を紹介、ではありません。守山市赤野井湾の内湖で、オオバナミズキンバイの除去活動を行ってきましたので、様子を報告します。

オオバナミズキンバイは、南米などを原産とする外来水生生物。平成21年に守山市の赤野井湾で発見されたのを契機に、南湖にどんどん生息域が広がっており、特定外来生物として指定されています。
現在、赤野井湾や内湖、雄琴周辺、帰帆島周辺、茶が崎あたりで確認されています。

増えると水面から陸までを覆い尽くすように増えていきます。ちぎれた根や茎からも増えるようで、除去の際も注意が必要となります。水面に生えるだけでなく、陸上でも増えていくのです。
水面を覆うと、水中に太陽の光が入らなくなり、また貧酸素化し、ヘドロが増え、生物が減っていきます。
ヨシ帯では、ヨシの芽吹きを抑え、ヨシが生えなくなります。
このように、他の植物を圧倒しながら、急速に増えていきます。
昨年除去作業をしておられた豊穣の郷さんでは、オオバナミズキンバイを刈り取った数ヵ月後に、倍以上に増えていたということもあったそうです。

茎が赤いのが特徴で、茎や根が絡みあい、除去の苦労が想像されます。
写真のように、水面から陸上へも生息域を拡大しています。

知事も来て、オオバナミズキンバイの状況を確認してくださいまいた。

今回は、県庁の職員60名ほどが協力し、手作業で除去作業を行います。
胴長を履き、ライフジャケットをつけて、ゴム長手袋をつけて作業を行います。
水中から根こそぎあげて、また陸上でもオオバナミズキンバイをあげていきます。
これがまた、重いのなんの。根や茎が複雑に絡み、少々引っ張った程度ではびくともしません。
腰を痛めないようにですが、大量のオオバナミズキンバイをあげていきます。
ちぎれた茎や根から再度生えないように、手網を使ってちぎれた茎や根をすくいとっていきます。
60名以上の大人が1時間やった成果がこちら。炎天下の胴長を着用しての作業では、1時間が限界でした。
before 作業前

after 作業後

これだけのオオバナミズキンバイを除去することができましたが、全体のほんの一部です。

ビニールシート上に置いているのは、乾燥させて焼却処分するためです。
ビニールシートも薄いものだと、シートを突き破って根を張る生命力があり、またさらにネットに入れて移動しないと、どこで広がって増えるかもしれない怖さがあります。

人力では限界があるとのことで、今回は重機による除去実験も行われました。
ワイヤーの先に大きな熊手状のものをつけて、沖から引っ張りあげ、除去します。
効率的に、徹底的に、除去しないと、ドンドン増えてしまうため、重機による除去が有効と思われます。
現在南湖全体でオオバナミズキンバイが64,000m2に渡って繁茂していると予想されます。
重機による除去が1日に1,000m2可能となると、単純計算で64日で除去が可能となります。
(現実にはそんな簡単にはいかないことは、みなさんお分かりでしょうが)

新聞、テレビ各社のマスコミも注目くださって、多く取材されていました。
手作業や重機など、いろんな知恵を出し合って、何とか広がるのを食い止め、除去していきたいものです。
南湖どころか、琵琶湖全体がオオバナミズキンバイに覆われた姿は想像したくありませんよね。
今日は、かわいらしいお花を紹介、ではありません。守山市赤野井湾の内湖で、オオバナミズキンバイの除去活動を行ってきましたので、様子を報告します。

オオバナミズキンバイは、南米などを原産とする外来水生生物。平成21年に守山市の赤野井湾で発見されたのを契機に、南湖にどんどん生息域が広がっており、特定外来生物として指定されています。
現在、赤野井湾や内湖、雄琴周辺、帰帆島周辺、茶が崎あたりで確認されています。

増えると水面から陸までを覆い尽くすように増えていきます。ちぎれた根や茎からも増えるようで、除去の際も注意が必要となります。水面に生えるだけでなく、陸上でも増えていくのです。
水面を覆うと、水中に太陽の光が入らなくなり、また貧酸素化し、ヘドロが増え、生物が減っていきます。
ヨシ帯では、ヨシの芽吹きを抑え、ヨシが生えなくなります。
このように、他の植物を圧倒しながら、急速に増えていきます。
昨年除去作業をしておられた豊穣の郷さんでは、オオバナミズキンバイを刈り取った数ヵ月後に、倍以上に増えていたということもあったそうです。

茎が赤いのが特徴で、茎や根が絡みあい、除去の苦労が想像されます。
写真のように、水面から陸上へも生息域を拡大しています。

知事も来て、オオバナミズキンバイの状況を確認してくださいまいた。

今回は、県庁の職員60名ほどが協力し、手作業で除去作業を行います。
胴長を履き、ライフジャケットをつけて、ゴム長手袋をつけて作業を行います。
水中から根こそぎあげて、また陸上でもオオバナミズキンバイをあげていきます。
これがまた、重いのなんの。根や茎が複雑に絡み、少々引っ張った程度ではびくともしません。
腰を痛めないようにですが、大量のオオバナミズキンバイをあげていきます。
ちぎれた茎や根から再度生えないように、手網を使ってちぎれた茎や根をすくいとっていきます。
60名以上の大人が1時間やった成果がこちら。炎天下の胴長を着用しての作業では、1時間が限界でした。
before 作業前

after 作業後

これだけのオオバナミズキンバイを除去することができましたが、全体のほんの一部です。

ビニールシート上に置いているのは、乾燥させて焼却処分するためです。
ビニールシートも薄いものだと、シートを突き破って根を張る生命力があり、またさらにネットに入れて移動しないと、どこで広がって増えるかもしれない怖さがあります。

人力では限界があるとのことで、今回は重機による除去実験も行われました。
ワイヤーの先に大きな熊手状のものをつけて、沖から引っ張りあげ、除去します。
効率的に、徹底的に、除去しないと、ドンドン増えてしまうため、重機による除去が有効と思われます。
現在南湖全体でオオバナミズキンバイが64,000m2に渡って繁茂していると予想されます。
重機による除去が1日に1,000m2可能となると、単純計算で64日で除去が可能となります。
(現実にはそんな簡単にはいかないことは、みなさんお分かりでしょうが)

新聞、テレビ各社のマスコミも注目くださって、多く取材されていました。
手作業や重機など、いろんな知恵を出し合って、何とか広がるのを食い止め、除去していきたいものです。
南湖どころか、琵琶湖全体がオオバナミズキンバイに覆われた姿は想像したくありませんよね。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 16:41
│環境学習センター