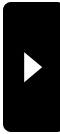愛のまちエコ倶楽部さん、里守隊活動に参加してきました
2014年07月04日
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
ちょっと遅くなってしまったのですが、滋賀でがんばっておられる団体さんを訪問してきましたので、紹介します。
東近江市、旧愛東町をフィールドに活動しておられる「NPO法人愛のまちエコ倶楽部」さん。
まずは、4/20に行われました「菜の花エコフェスタ」にお邪魔しました。
場所は、あいとうエコプラザ菜の花館とその広場。ジェラートが美味しい愛東マーガレットステーション横と言えば分かりやすいですね。

会場では、それぞれのブースでは、販売あり、展示ありで、エコにちなんでとても賑やかでした。
いくつかを紹介します。

里守隊さんの薪を販売しておられました。
当日は、薪割り体験コーナーも設置しておられ、子どもから大人まで、「えいやっー!」と斧を振りおろしておられました。みんな日頃のストレスを発散するかのように、薪づくりを楽しんでおられました。

四方を網で囲われ、安全にも配慮しておられます。

NPO法人碧いびわ湖さん(旧環境生協)です。
雨水利用について教えてもらったのですが、雨水ってすごいんですね。
水道水だとミネラル分などが多く混じっている硬水に近いのですが、雨水はそういったものが混じっていない軟水のため、洗濯の時のすすぎに使うと、洗剤の切れが違うとのこと。

実際に、石けんを溶かした水道水と雨水入りのペットボトルを見せてもらいました。
ペットボトルの表面にカスが残っていないのが見えますでしょうか?
実際に、雨水タンクを家に据え付けたご家族の主婦の方は、雨水使うと水道水には戻れないとのことでした。

こちらは代表の村上さん。せっかくだからと笑顔で、パチリ。
(この後、村上さんになぜかバッタリ出逢うことが連続し、奇妙な運命を感じました・・・)

東近江市のまちづくり協議会で進めておられるダンボールコンポスト(生ごみたい肥づくり)コーナー
これを見まして、私も自宅でダンボールコンポストを始めています。(途中経過ですが、なかなかいい感じです)

子どもたちによる家づくりならぬ、ジャングルジムづくり。
自分で木をつなげて、どんどん高く広く作っていけるジャングルジムです。
めっちゃ楽しそうです。そりゃぁ、自分で作れるんです、楽しいはずです。

こちらは、薪ストーブ「リッシュ」。里山活動で出る針葉樹も燃やせる分厚い鉄板製の優れ物だそうです。
(鋳物製の薪ストーブでは、針葉樹は高温になりすぎるため、杉や檜は燃やさないことが推奨されているそうです)

愛のまちエコ倶楽部の活動の紹介もしてくださいました。
菜の花エコプロジェクトに代表されるように、廃油から、石けんづくりを行ったり、菜の花の栽培から、BDF燃料化・油の販売など、地域の暮らしと技術とエネルギーを地域の人の力でつなげておられます。
愛東のスタイルが滋賀県内に広がればいいのになぁと思います。
というような、賑やかで、楽しいエコ祭りでした。
愛のまちエコ倶楽部さんによる紹介ブログはこちら愛のまちエコ倶楽部のブログ
ということで、愛のまちエコ倶楽部さんの活動に興味を持った私は、さらに里守隊さんの活動にも参加させてもらいました。
菜の花エコ祭りの一月後の5/18(日)、菜の花館に集合して、愛東町の里山へ。

森の中の看板が迎えてくれます。
当日の作業は、森を切り開いての整地(活動で集まる人の駐車場になる予定)
なんと赤ん坊!から高校生、大人まで14名が集まりました。

チェーンソー組の方は、まずは歯の手入れから。道具を安全に長持ちさせるのは、手入れです。

木を切り、運び出す作業です。
大きな木はチェーンソーで、細いものは手ノコで切ります。
うっそうとしていた森がドンドン切り開かれていきます。森に光が当たるのを感じます。

太いのはチェーンソー組です。皆さん、マイチェーンソーをお持ちだそうです。
里山活動をしていると、だんだんと欲しくなるそうです。

重い木を運び出します。
初めて会った同志も、作業をしているうちに声を掛け合い、仲良くなります。
大きな重い木ほど、お互い声を出し目を合わせ、安全にと思い、さらに仲間となっていきます。
こういうことも、里山活動の楽しさかもしれません。

森の奥へ倒れ、人力で搬出できそうにない木は、機械を使います。
こういった重機も活動の中で活用しておられます。

森の中にそびえる、松枯れのアカマツ。
かなり高いのが分かりますか?地面の所に小さく見えるのが人です。
これも危険ですので、倒します。
うっそうとしていた状況では気づかなかったのですが、森にはこのような状態の木がたくさんあり、この森が活用されなくなってずいぶん年月が経っていることが分かりました。

先ほどのアカマツを倒した後、安全に思う方向に倒れたか、この次はどのようにすれば良いか、道具の使い方はどうであったかなどを話合い、安全に技術を高めていきます。

森には、作業小屋の他、炊事場所なども作っておられ、美味しい昼食を作ってくださいました。

大きな一枚板のテーブルでみんなで食べるご飯。今回はマーボー丼と自家製らっきょうでした。
ほんと美味しかった!ごちそうさまでした。

作業終了後の森。枯れた木々、絡みついた葛などが取り払われました。
お話を伺うと、約8年前頃から活動をされておられ、当初はマツタケでも取れないかなぁと、50haほどの里山で少しずつ、松枯れのマツを倒していく所から始められたそうです。
古い松が枯れた状態の森でしたが、伐採して地面に光が当たるようになると、再びマツが芽吹いて来たそうです。
人が関わることによって、森が再生されていくことを感じたそうで、枯れた森を少しずつ無理せずゆっくりと元気な森へと変えておられます。
参加されている方も、薪ストーブから入った方、里山好きから入った方、なんだか誘われて来た方、一度来てはまってしまった方、親に言われて来た方・・・と様々です。赤ちゃんもいます。
様々ですが、みんな笑顔で作業をして、みんなで昼ごはんを食べて、また作業してと楽しい一日を過ごしておられます。
活動は、間伐であったり、草刈りであったり、薪割り(高校生名人もおられます)、腐葉土づくりだったり、その時にあわせて活動し、子ども向けの体験プログラムをしたり、アルプスの少女ハイジが乗っていたブランコもつくれたらなぁと夢も広げておられます。
定例作業日は、毎月第3日曜日とのこと。
詳しくは、愛のまちエコ倶楽部さんのHP、里守隊さんのブログもご覧ください。
ちょっと遅くなってしまったのですが、滋賀でがんばっておられる団体さんを訪問してきましたので、紹介します。
東近江市、旧愛東町をフィールドに活動しておられる「NPO法人愛のまちエコ倶楽部」さん。
まずは、4/20に行われました「菜の花エコフェスタ」にお邪魔しました。
場所は、あいとうエコプラザ菜の花館とその広場。ジェラートが美味しい愛東マーガレットステーション横と言えば分かりやすいですね。

会場では、それぞれのブースでは、販売あり、展示ありで、エコにちなんでとても賑やかでした。
いくつかを紹介します。

里守隊さんの薪を販売しておられました。
当日は、薪割り体験コーナーも設置しておられ、子どもから大人まで、「えいやっー!」と斧を振りおろしておられました。みんな日頃のストレスを発散するかのように、薪づくりを楽しんでおられました。

四方を網で囲われ、安全にも配慮しておられます。

NPO法人碧いびわ湖さん(旧環境生協)です。
雨水利用について教えてもらったのですが、雨水ってすごいんですね。
水道水だとミネラル分などが多く混じっている硬水に近いのですが、雨水はそういったものが混じっていない軟水のため、洗濯の時のすすぎに使うと、洗剤の切れが違うとのこと。

実際に、石けんを溶かした水道水と雨水入りのペットボトルを見せてもらいました。
ペットボトルの表面にカスが残っていないのが見えますでしょうか?
実際に、雨水タンクを家に据え付けたご家族の主婦の方は、雨水使うと水道水には戻れないとのことでした。

こちらは代表の村上さん。せっかくだからと笑顔で、パチリ。
(この後、村上さんになぜかバッタリ出逢うことが連続し、奇妙な運命を感じました・・・)

東近江市のまちづくり協議会で進めておられるダンボールコンポスト(生ごみたい肥づくり)コーナー
これを見まして、私も自宅でダンボールコンポストを始めています。(途中経過ですが、なかなかいい感じです)

子どもたちによる家づくりならぬ、ジャングルジムづくり。
自分で木をつなげて、どんどん高く広く作っていけるジャングルジムです。
めっちゃ楽しそうです。そりゃぁ、自分で作れるんです、楽しいはずです。

こちらは、薪ストーブ「リッシュ」。里山活動で出る針葉樹も燃やせる分厚い鉄板製の優れ物だそうです。
(鋳物製の薪ストーブでは、針葉樹は高温になりすぎるため、杉や檜は燃やさないことが推奨されているそうです)

愛のまちエコ倶楽部の活動の紹介もしてくださいました。
菜の花エコプロジェクトに代表されるように、廃油から、石けんづくりを行ったり、菜の花の栽培から、BDF燃料化・油の販売など、地域の暮らしと技術とエネルギーを地域の人の力でつなげておられます。
愛東のスタイルが滋賀県内に広がればいいのになぁと思います。
というような、賑やかで、楽しいエコ祭りでした。
愛のまちエコ倶楽部さんによる紹介ブログはこちら愛のまちエコ倶楽部のブログ
ということで、愛のまちエコ倶楽部さんの活動に興味を持った私は、さらに里守隊さんの活動にも参加させてもらいました。
菜の花エコ祭りの一月後の5/18(日)、菜の花館に集合して、愛東町の里山へ。

森の中の看板が迎えてくれます。
当日の作業は、森を切り開いての整地(活動で集まる人の駐車場になる予定)
なんと赤ん坊!から高校生、大人まで14名が集まりました。

チェーンソー組の方は、まずは歯の手入れから。道具を安全に長持ちさせるのは、手入れです。

木を切り、運び出す作業です。
大きな木はチェーンソーで、細いものは手ノコで切ります。
うっそうとしていた森がドンドン切り開かれていきます。森に光が当たるのを感じます。

太いのはチェーンソー組です。皆さん、マイチェーンソーをお持ちだそうです。
里山活動をしていると、だんだんと欲しくなるそうです。

重い木を運び出します。
初めて会った同志も、作業をしているうちに声を掛け合い、仲良くなります。
大きな重い木ほど、お互い声を出し目を合わせ、安全にと思い、さらに仲間となっていきます。
こういうことも、里山活動の楽しさかもしれません。

森の奥へ倒れ、人力で搬出できそうにない木は、機械を使います。
こういった重機も活動の中で活用しておられます。

森の中にそびえる、松枯れのアカマツ。
かなり高いのが分かりますか?地面の所に小さく見えるのが人です。
これも危険ですので、倒します。
うっそうとしていた状況では気づかなかったのですが、森にはこのような状態の木がたくさんあり、この森が活用されなくなってずいぶん年月が経っていることが分かりました。

先ほどのアカマツを倒した後、安全に思う方向に倒れたか、この次はどのようにすれば良いか、道具の使い方はどうであったかなどを話合い、安全に技術を高めていきます。

森には、作業小屋の他、炊事場所なども作っておられ、美味しい昼食を作ってくださいました。

大きな一枚板のテーブルでみんなで食べるご飯。今回はマーボー丼と自家製らっきょうでした。
ほんと美味しかった!ごちそうさまでした。

作業終了後の森。枯れた木々、絡みついた葛などが取り払われました。
お話を伺うと、約8年前頃から活動をされておられ、当初はマツタケでも取れないかなぁと、50haほどの里山で少しずつ、松枯れのマツを倒していく所から始められたそうです。
古い松が枯れた状態の森でしたが、伐採して地面に光が当たるようになると、再びマツが芽吹いて来たそうです。
人が関わることによって、森が再生されていくことを感じたそうで、枯れた森を少しずつ無理せずゆっくりと元気な森へと変えておられます。
参加されている方も、薪ストーブから入った方、里山好きから入った方、なんだか誘われて来た方、一度来てはまってしまった方、親に言われて来た方・・・と様々です。赤ちゃんもいます。
様々ですが、みんな笑顔で作業をして、みんなで昼ごはんを食べて、また作業してと楽しい一日を過ごしておられます。
活動は、間伐であったり、草刈りであったり、薪割り(高校生名人もおられます)、腐葉土づくりだったり、その時にあわせて活動し、子ども向けの体験プログラムをしたり、アルプスの少女ハイジが乗っていたブランコもつくれたらなぁと夢も広げておられます。
定例作業日は、毎月第3日曜日とのこと。
詳しくは、愛のまちエコ倶楽部さんのHP、里守隊さんのブログもご覧ください。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 19:35
│環境学習センター