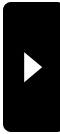「保存食を科学する」第2弾!ふなずし作りに挑戦
2012年08月08日
8月4日(土)、琵琶湖博物館の実習室で講座「保存食を科学する」が開催されました。
前回の「湖魚の佃煮」に続き、今回のテーマは「ふなずし」。
世間は夏休みということもあって、親子でのご参加が多く見られました。

まずは学芸員さんのお話。
なんとあの大将軍、徳川家康がふなずしを口にしていたとのこと!
あっと驚くふなずしの歴史をはじめ、魚と食をめぐる話にみなさん興味津々です。
さあ、講義のあとはふなずし作りを体験!

塩漬けされたニゴロブナたち。
今回は、このフナたちに付いた岩塩を洗い流すところから始めます。

エラを開き、お腹に溜まった岩塩もしっかり取り出します。
さらに、ブラシを使ってフナ全体を青光りするまで十分に磨いていきます。
さて、磨き上げたフナを乾かした後は、ふなずし作りのメインである飯漬け(いいづけ)です。
この飯漬けという作業には、ふなずし特有の酸っぱさや旨味を発生させ、食品の保存力を高める秘密が隠されているのです!

フナのエラを開け、お腹の中に米を詰めます。
子どもたちもがんばっています!

米を詰めたフナは、桶の中に平行に並べます。
フナと米が交互になるように重ねていきます。
参加者のみなさんに体験していただいたのはここまで。
おわりに、去年漬けたふなずしを全員で試食しました!

ニオイが控えめで、ふなずしを初めて口にする方にも食べやすい一品でした。
今回漬けたフナも、来年には美味しいふなずしになりますように。
講座「保存食を科学する」は次回で最後となります。
テーマは「かんぴょう」です。
http://www.lbm.go.jp/event/index.html#kouza
興味のあるかたは、ぜひご応募ください。
前回の「湖魚の佃煮」に続き、今回のテーマは「ふなずし」。
世間は夏休みということもあって、親子でのご参加が多く見られました。
まずは学芸員さんのお話。
なんとあの大将軍、徳川家康がふなずしを口にしていたとのこと!
あっと驚くふなずしの歴史をはじめ、魚と食をめぐる話にみなさん興味津々です。
さあ、講義のあとはふなずし作りを体験!
塩漬けされたニゴロブナたち。
今回は、このフナたちに付いた岩塩を洗い流すところから始めます。
エラを開き、お腹に溜まった岩塩もしっかり取り出します。
さらに、ブラシを使ってフナ全体を青光りするまで十分に磨いていきます。
さて、磨き上げたフナを乾かした後は、ふなずし作りのメインである飯漬け(いいづけ)です。
この飯漬けという作業には、ふなずし特有の酸っぱさや旨味を発生させ、食品の保存力を高める秘密が隠されているのです!
フナのエラを開け、お腹の中に米を詰めます。
子どもたちもがんばっています!
米を詰めたフナは、桶の中に平行に並べます。
フナと米が交互になるように重ねていきます。
参加者のみなさんに体験していただいたのはここまで。
おわりに、去年漬けたふなずしを全員で試食しました!
ニオイが控えめで、ふなずしを初めて口にする方にも食べやすい一品でした。
今回漬けたフナも、来年には美味しいふなずしになりますように。
講座「保存食を科学する」は次回で最後となります。
テーマは「かんぴょう」です。
http://www.lbm.go.jp/event/index.html#kouza
興味のあるかたは、ぜひご応募ください。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 11:05
│環境学習センター