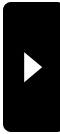朽木の山でトチの実拾い
2015年09月25日
こんにちは。琵琶湖博物館 環境学習センターのまっちゃこと池田勝です。
9/5(土)に、「巨木と水源の郷をまもる会」さん主催の「とちのみ拾い」に参加して来ました。
今回は、朽木針畑地域の山に入り、栃の木が生えている谷を目指し、栃の実を拾い集めるプログラムです。
山帰来に集合したのは、小学生からシニアの方、スタッフを含め30名。みなさん、晴れの空を眺めながら、とても良い表情をしておられます。
(本当に今年の9月は、雨が多かったですからね。晴れがこんなに嬉しいと思いませんでした)

山帰来から移動して、ここから山に入ります。みなさん、ハイキングシューズに、リュック、帽子と格好もばっちりです。

杉の間を歩いていきます。杉に巻かれたビニール紐は、熊の爪とぎ除けです。
杉林を歩いて、沢沿いに進んでいきます。

大きな切り株が散乱していました。何でしょう?
この切り株は、巨木と水源の郷を守る会さんの活動に関わってきます。
昔から朽木の人々は森へ入り、栃の実を拾い、栃餅をつくったりしてきました。
杉やヒノキの植林が始まっても、栃を始めとする広葉樹、そしてその巨木は朽木の森の生態系を支えています。
しかし、近代化によって、栃の実拾いも途絶えてくると、森への関心も薄れ、数年前、朽木の山々で生えている巨木が二束三文で業者へ売られている事態が分かりました。
直径が2メートルも3メートルもある巨木ですから、樹齢何百年の森のシンボルとしても、杉ヒノキ林が多く広葉樹が少ない中、貴重な生態系の一部でもあります。
生態系だけでなく、朽木の人々にとって栃やそれを利用してきた文化や生業としても貴重な栃を守ろうと、巨木と水源の郷を守る会さんが立ちあがりました。

巨木が切られると、森はぽっかり空いて、空が見えます。

業者は、ヘリコプターで利用したい部分だけ持ち去り、後は放置していったそうです。
ただ、良い悪いの問題ではなく、材として木を利用することはとても大事ですし、生態系保全の面からも必要な場合もあります。
単純に自然破壊と対する自然保護ではなく、複雑に絡んだ社会問題(林業、過疎化、経済、獣害、文化の荒廃など)も考えながら、巨木の郷を柱として、会を運営しておられます。
巨木の郷を守る会さんのホームページはこちら
栃の実がなる森へ向かう途中で、森のこと、会のこと、朽木のことなどを聞きながら足を進めていきました。
途中、険しい所もありましたが、事前に会のみなさんが歩きやすいように、ロープを渡したり、石を並べたりして危険がないように配慮してくださっています。

沢沿いに歩くと、これまでの杉ヒノキ林から、雰囲気が変わりました。
葉からこぼれる光の様子、地面を覆っている落ち葉の様子がこれまでと違います。
と、思ったら「ここが栃の森です!」と。よく見ると、栃の実や実の果皮が落ちています。
早速、みんなで栃の実拾いです。

森の中には、ビニール紐が張り巡らされています。
というのは、鹿が栃の実を食べてしまうのを予防するためで、低い高さに紐が張っていると、鹿はいやがって周囲にやって来ないのだそうです。
結果を現すように、ビニール紐が張っていない所は見事に実がなく、果皮のみが落ちていました。
こちらも会の方が、森に入って2日がかりで張り巡らせたそうです。
1時間近くみんなで拾い集めます。
栃は沢沿いが好きな樹のため、落ちた実は川へ落ちていくことも多く、長靴をはいた方は、流れの中で拾います。

この実を拾うという行動の良さは何でしょうか。
ドングリ拾いでも、栃の実拾いでも、銀杏拾いでも、栗拾いでも、人は一心不乱に拾ってしまいます。
人類の体に植えつけられた遺伝子なのでしょうかね。
「おしまーい」の声が掛かっても拾ってしまいます。ただただ拾うのが楽しいです。
しかし、拾った栃が重くて、そして多すぎて、リュックに入るのでしょうかね。
拾いすぎて、帰りに袋が破れて落とさないか不安です。

会の方によると、昔は栃をカゴに入れて、背負って山を降りたとのことです。男性も女性も、子どもも拾って、多い時は一人で60kg以上も背負って山を降りたとのこと。それも奥山からです。
昔の人の働きぶりにびっくりしますし、そんなに人に拾われても栃が森からなくなることなく、残った実から芽を出していつか巨木になっていったという気の長い栃の戦略にもびっくりです。

見上げると、栃の葉っぱが広がっていました。
さて、重いリュックを背負って、山帰来へ。
みんなで、拾った栃の実の個数と、重さを計ります。

たくさん拾ったので、量りに乗せられない人は、体重計を使って。

全体で、なんと 2499個、28kgの栃が拾えました。(おしい!あと1個で2500個でした)
この栃は、栃餅にしてお祭りでふるまったり、保存したり、栃として芽をださせて植樹したりするそうです。
山帰来の前には、植樹して養育中の栃が育っていました。(草に負けずに大きくなってやー)

(会では、下流域の新旭町針江地区と協力して、針江の畑で栃や沢グルミの苗を育て、源流の山へ植樹できるようにしておられます。源流の森と下流の田んぼは、水でつながっているんですね。その大事さをそれぞれ考えておられるんですね。)

採れた栃です。この丸くて、つやつやして、何とも言えない可愛らしさがあります。
山帰来では、栃餅ぜんざいをいただきながら、栃餅づくりについて伺いました。


灰汁抜きが一番難しいそうで、家庭や在所によっても若干方式が異なるそうで、各地に先生がおられるようです。
会でも栃餅を作られたそうですが、「灰汁抜きがうまくできてないねん。難しいわー」と話しておられました。
(その灰汁抜きができていない栃餅もいただきました。私は何ともなくいただきましたが、舌がちょっとピリッとするという方もおられました)
これは水に浸した栃の皮を剥く道具。

このような道具があることも、栃が育む文化です。
巨木があり、栃があり、それを拾う人々がいて、またその食が広まっていく流れが続いていくと良いなぁと思います。
巨木と水源の郷を守る会さんでは、会員が80名近くおられ、会員の方の都合や出来ることに応じて、関わっておられるとのことです。
10/25(日)には、第4回「栃の木祭」を開催されます。
巨木や水源地へのハイキング、クラフトなど多くのプログラムを用意して、運営をされるようです。
ぜひご参加ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
9/5(土)に、「巨木と水源の郷をまもる会」さん主催の「とちのみ拾い」に参加して来ました。
今回は、朽木針畑地域の山に入り、栃の木が生えている谷を目指し、栃の実を拾い集めるプログラムです。
山帰来に集合したのは、小学生からシニアの方、スタッフを含め30名。みなさん、晴れの空を眺めながら、とても良い表情をしておられます。
(本当に今年の9月は、雨が多かったですからね。晴れがこんなに嬉しいと思いませんでした)

山帰来から移動して、ここから山に入ります。みなさん、ハイキングシューズに、リュック、帽子と格好もばっちりです。

杉の間を歩いていきます。杉に巻かれたビニール紐は、熊の爪とぎ除けです。
杉林を歩いて、沢沿いに進んでいきます。

大きな切り株が散乱していました。何でしょう?
この切り株は、巨木と水源の郷を守る会さんの活動に関わってきます。
昔から朽木の人々は森へ入り、栃の実を拾い、栃餅をつくったりしてきました。
杉やヒノキの植林が始まっても、栃を始めとする広葉樹、そしてその巨木は朽木の森の生態系を支えています。
しかし、近代化によって、栃の実拾いも途絶えてくると、森への関心も薄れ、数年前、朽木の山々で生えている巨木が二束三文で業者へ売られている事態が分かりました。
直径が2メートルも3メートルもある巨木ですから、樹齢何百年の森のシンボルとしても、杉ヒノキ林が多く広葉樹が少ない中、貴重な生態系の一部でもあります。
生態系だけでなく、朽木の人々にとって栃やそれを利用してきた文化や生業としても貴重な栃を守ろうと、巨木と水源の郷を守る会さんが立ちあがりました。

巨木が切られると、森はぽっかり空いて、空が見えます。

業者は、ヘリコプターで利用したい部分だけ持ち去り、後は放置していったそうです。
ただ、良い悪いの問題ではなく、材として木を利用することはとても大事ですし、生態系保全の面からも必要な場合もあります。
単純に自然破壊と対する自然保護ではなく、複雑に絡んだ社会問題(林業、過疎化、経済、獣害、文化の荒廃など)も考えながら、巨木の郷を柱として、会を運営しておられます。
巨木の郷を守る会さんのホームページはこちら
栃の実がなる森へ向かう途中で、森のこと、会のこと、朽木のことなどを聞きながら足を進めていきました。
途中、険しい所もありましたが、事前に会のみなさんが歩きやすいように、ロープを渡したり、石を並べたりして危険がないように配慮してくださっています。

沢沿いに歩くと、これまでの杉ヒノキ林から、雰囲気が変わりました。
葉からこぼれる光の様子、地面を覆っている落ち葉の様子がこれまでと違います。
と、思ったら「ここが栃の森です!」と。よく見ると、栃の実や実の果皮が落ちています。
早速、みんなで栃の実拾いです。

森の中には、ビニール紐が張り巡らされています。
というのは、鹿が栃の実を食べてしまうのを予防するためで、低い高さに紐が張っていると、鹿はいやがって周囲にやって来ないのだそうです。
結果を現すように、ビニール紐が張っていない所は見事に実がなく、果皮のみが落ちていました。
こちらも会の方が、森に入って2日がかりで張り巡らせたそうです。
1時間近くみんなで拾い集めます。
栃は沢沿いが好きな樹のため、落ちた実は川へ落ちていくことも多く、長靴をはいた方は、流れの中で拾います。

この実を拾うという行動の良さは何でしょうか。
ドングリ拾いでも、栃の実拾いでも、銀杏拾いでも、栗拾いでも、人は一心不乱に拾ってしまいます。
人類の体に植えつけられた遺伝子なのでしょうかね。
「おしまーい」の声が掛かっても拾ってしまいます。ただただ拾うのが楽しいです。
しかし、拾った栃が重くて、そして多すぎて、リュックに入るのでしょうかね。
拾いすぎて、帰りに袋が破れて落とさないか不安です。

会の方によると、昔は栃をカゴに入れて、背負って山を降りたとのことです。男性も女性も、子どもも拾って、多い時は一人で60kg以上も背負って山を降りたとのこと。それも奥山からです。
昔の人の働きぶりにびっくりしますし、そんなに人に拾われても栃が森からなくなることなく、残った実から芽を出していつか巨木になっていったという気の長い栃の戦略にもびっくりです。

見上げると、栃の葉っぱが広がっていました。
さて、重いリュックを背負って、山帰来へ。
みんなで、拾った栃の実の個数と、重さを計ります。

たくさん拾ったので、量りに乗せられない人は、体重計を使って。

全体で、なんと 2499個、28kgの栃が拾えました。(おしい!あと1個で2500個でした)
この栃は、栃餅にしてお祭りでふるまったり、保存したり、栃として芽をださせて植樹したりするそうです。
山帰来の前には、植樹して養育中の栃が育っていました。(草に負けずに大きくなってやー)

(会では、下流域の新旭町針江地区と協力して、針江の畑で栃や沢グルミの苗を育て、源流の山へ植樹できるようにしておられます。源流の森と下流の田んぼは、水でつながっているんですね。その大事さをそれぞれ考えておられるんですね。)

採れた栃です。この丸くて、つやつやして、何とも言えない可愛らしさがあります。
山帰来では、栃餅ぜんざいをいただきながら、栃餅づくりについて伺いました。


灰汁抜きが一番難しいそうで、家庭や在所によっても若干方式が異なるそうで、各地に先生がおられるようです。
会でも栃餅を作られたそうですが、「灰汁抜きがうまくできてないねん。難しいわー」と話しておられました。
(その灰汁抜きができていない栃餅もいただきました。私は何ともなくいただきましたが、舌がちょっとピリッとするという方もおられました)
これは水に浸した栃の皮を剥く道具。

このような道具があることも、栃が育む文化です。
巨木があり、栃があり、それを拾う人々がいて、またその食が広まっていく流れが続いていくと良いなぁと思います。
巨木と水源の郷を守る会さんでは、会員が80名近くおられ、会員の方の都合や出来ることに応じて、関わっておられるとのことです。
10/25(日)には、第4回「栃の木祭」を開催されます。
巨木や水源地へのハイキング、クラフトなど多くのプログラムを用意して、運営をされるようです。
ぜひご参加ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
そよかぜ第219号を発行しました
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
そよかぜ第218号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2020年1月17日号を発行しました
そよかぜ第217号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年11月15日号を発行しました
そよかぜ「きまぐれ通信」2019年10月18日号
Posted by BIWAちゃん at 15:19
│環境学習センター